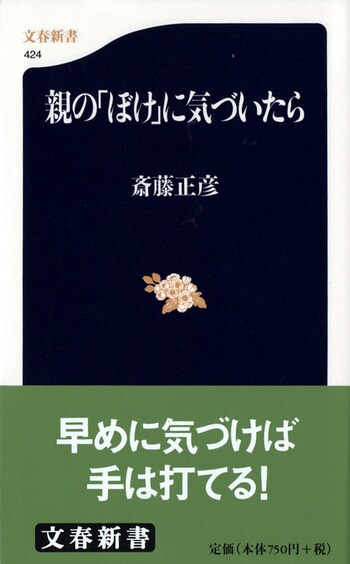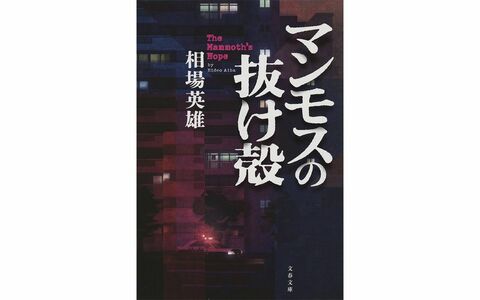ある朝のことだった。
父がベッドの脇で途方に暮れていた。
「どうしたの?」と聞くと、「わしはなにをするんだ?」と心細そうにつぶやいたのである。
「着替えて、顔を洗って。いつものように」
「そうか。着替えるんだな……」
父は当時八十六歳。脳血栓で倒れ、半身麻痺と重い失語症になった妻を娘の私と一緒に十三年間も介護を続け、ついに彼女を亡くし、三年ほどが過ぎた時だった。
私は父が軽い脳梗塞を起こしたのだと思った。すぐに病院に連れて行って調べてもらうと、医者からは、脳虚血発作、と言われた。
「脳の周辺部分の細かい血管が詰まっていますね。ま、お年なのだからしょうがない」
梗塞予防の薬を飲むことになったが、しょうがない、と医者にあっさり言われ、そうか、誰でもこうやって老いていくのだとあきらめるしかなかった。
母は亡くなる前の二年半ほどを近所の有料老人ホームで過ごしていたので、私は「ぼけ」た高齢者(そのホームでは「お分かりにならない方」と呼んでいたが)とは親しんでいたし、いささか高齢で「ぼけ」た父に介護が必要になったことを淡々と受け止めたのである。
けれど、傍でお付き合いするのと、二十四時間、一緒に暮らすのでは大違いだった。着替え、食事、排泄、日常のほとんどすべてに声掛けや介助が必要になり、とりわけ、どっかにスイッチが入ると(私にはそう思えた)父は行き先も告げずに衝動的に出掛けてしまうため、次第に片時も一人にしておくことができなくなっていった。
頑固で厳しかった父は、物を言わなくなり従順な幼子のようになった。介護をしながら、時折、悲しみに襲われた。かつての父はどこへ行ってしまったのか、と。高齢になって生じた父の「ぼけ」は、私にとっては父の喪失だった。一人ぼっちで取り残されてしまったような思いだった。
そんなわけで、斎藤正彦著の『親の「ぼけ」に気づいたら』は、その一行、一行が深く身にしみた。
そもそも、自分の親に起きた事がいったいどういうことで、その起きたことがこれからどうなっていくのか、それが分からないと、介護者は常に不安にさいなまれる。起こったことに一喜一憂し、なにかと情緒不安定になるのである。
「痴呆症」と呼ばれる病気のメカニズムをきちんと理解することが、これからの介護のためにどれほど大切か。
その理解がないと、一生懸命やっているつもりが、当事者のサポートにちっともなっていなかったり、あらぬ葛藤を生じさせていたりするのである。
事実、私はなんとか父を元に戻そうと、ドリルを一緒にやったり、碁を勧めたり、筋トレを強いたりして、「できなくなった自分」と向き合わせ、かえって自信を喪失させるようなこともしてしまっていた。
というのも、いわゆる「痴呆症」の人には、病識がない、と書かれていたものを読んでいたため、「物忘れ」のひどさに落ち込む父は、単なる高齢ゆえと思っていたし、日に何度も出掛けてしまう父が「お前を探しに」とか「コーヒーを飲みに」とか「散歩に」と、その度に理由を言うので、これは「徘徊」ではないのだから、いわゆる父は「痴呆症」ではない、と思っていた。いや、思いたがっていた。
それはたぶん「痴呆」という言葉への抵抗感、「痴呆症」とか「ぼけ」とかあからさまに言われるとなにか父の尊厳が傷つけられるような心境になるということもあった。けれど、本書に記述されているどの事例もどの解説も、介護者や介護される人たちへの優しさに満ちていて、そういう単なる言葉への抵抗感などは払拭させられてしまう力があった。
長い介護体験の中で、私は、医療現場の高齢者へのまなざしのひややかさ、介護者への理解のなさをいやというほど思い知らされてきたが、臨床の現場や介護者の体験からさまざまな発見をし、その専門性を磨いてこられたにちがいない著者に、読み終えて敬意を覚えずにいられない。家族介護の当事者ばかりではなく、効率化とマニュアル化が進行しかねない施設介護の現場にもこのような本が活用されることを心から願いたいと思った。