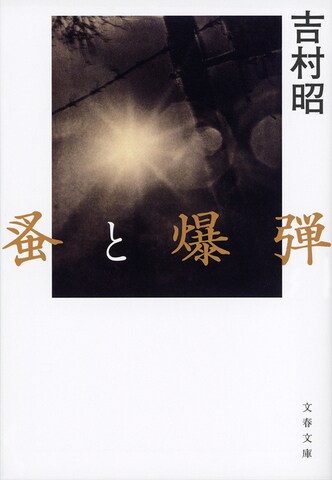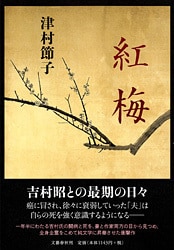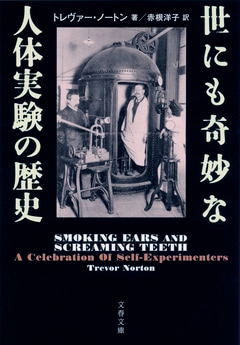一読してわかるが本書では、末尾で一人の陸軍中将の名が書かれているが、固有名詞で語られているのは曾根二郎だけである(戦況を書くときに司令官の氏名などが書かれていても、それは本書の筋立てとは関係ない)。とにかく固有名詞はまったく使われていない。関東軍の参謀長、参謀副長なども職名で書かれていて、固有名詞ではないのだが、そのことは何をあらわすか、は考えるべきであろう。
著者は個々の関係者の固有名詞を提示することにより、この驚くべき「人体実験」が特異なケースとされることを恐れたのであろう。むろん著者はこのテーマにとりくみ、小説としてまとめるためにそれこそ多くの関係者に会って話を聞いていると思われる。なぜならペスト菌を持つ蚤爆弾の説明、人体実験された捕虜たちの生態が細部にわたって描写されているのを見ても、著者の会った取材対象者の数の多さは容易に想像されうる。確かに固有名詞で語ることはそういう人物へ迷惑がかかるという配慮もあっただろう。
しかし固有名詞を一切用いないことによって、逆にこうした「人体実験」という非人間的行為が、戦争という時代にはこれまでも行われてきたし、これからも行われるであろうと考えることができる。人類史はそういう残酷さを抱えながら編まれていると、著者と同じ感覚が共有できるように思う。
さらに指摘すれば、著者はこうした実験に関わった人たち(関わらなければならなかった関係者たち)が、自らの罪業に恐れおののいて「戦後」を生きている姿を暗示させている。かつての仲間であっても、「たがいに眼をそらし合って」という表現にそれが凝縮している。この実験に関わった人たちが、いかに脅えて戦後を生きたかは、本書全体の行間の中からも浮かびあがる。私自身、こうした関係者に会って話を聞いたことがあるのだが、その彼が「私たちはクモの巣にひっかかっている虫のようなものです」と言って、詳細は曖昧にしつつ、自らが戦後も誰かに監視されているとの不安を口にしていた。「二度と中国には行っていません」というのが彼らに共通しているとも洩らしていた。
本書にはそうした関係者たちの、苦しい胸の内を明かす証言が幾つかさりげなく使われている。そこに著者の人間観・歴史観があり、その点に私も強い共鳴を持つ。怒りだけ、あるいはヒューマニズムだけ、そういう単色で本書を書きあげたなら一時的にもてはやされるだろうが、著者はまったくそのような道を選択していない。
著者のノンフィクションに通じる作品には、人間の持つ能力がある制約を超えるととんでもないことをやってのけるという人間省察が描かれている。そうした人間像はいつの時代にも存在する。その人間像を丹念に追うことではからずも時代の本質が見えてくる。著者の言いたいこと、あるいは言わなければならないこと、というのはそこにあるのではないかと、改めて私は受けとめている。その姿勢に共感するのが、自問への私の「答え」とつぶやくのである。