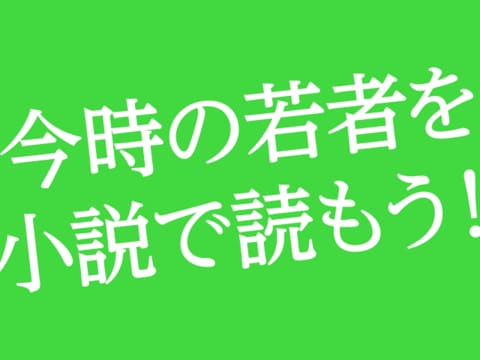Fは特殊な電波送受信装置で常に監視されており、考えていることは全て人事部のコンピュータに記録され、指示を受ける。今日できる仕事を明日に回そうとすると、「先延ばしにするなよ」と上司の声が聞こえ、就業時間に休憩室でコーヒーを飲んでいると「さぼってるんじゃない。働け」と叱責がとぶ。大事な会議をすっぽかしたときには、罰として今までに経験したことのない激しい頭痛を送り込まれたこともあるという。
「電波の強弱を少し変えるだけで、そういう苦痛を与えることができるらしいんだ」
まさに人事ロボットである。
だが人事部は、彼を実験材料にしていることを、そう容易には明さなかった。休職の間も人事部の声は続き、自分の知らない本の題名を脳裏に送り込み、書店で探すと不思議なことに聞いたとおりの本がある。それは政治や経済、歴史、はては電波関係の書籍に至るまで幅広く、今までの彼の経験と知識では決して知り得なかった本ばかりだったという。だが、その本は彼にあることを気づかせた。
「つまり人事部は、オレにその本を読ませることで、頭ん中で聞こえる声についての秘密を小出しにしたわけよ。それでオレもようやく自分に起きてることの意味がわかってきた」
リアクションに窮する私に、「ほんとうなんだ。信じてくれ」とFは訴えた。そしてこれを小説に書いてくれといった。こんなことが許されるはずはない、だから書いてくれ、と。
ごもっともだ――もし彼がいうことが真実なら。
Fの体調が心配だったこともあり、早い時間に駅で別れた。じゃあな、と手をあげ、ひょうひょうと改札の内側へ消えていくFの姿を見送りながら、私は複雑な思いでため息をついていた。
外見はかつて一緒に銀行に入った頃のFのままだ。だがその内面は、銀行という厳しい職場で傷つき、変容してしまったのだ。
翌日、後輩と話す機会があったので、それとなくFのことをきいた。
「Fさんと会われたんですか。あの人は、疲れてしまったんだと思いますよ」
そうだろうなあ、疲れもするさ、Fよ。それは君に限ったことじゃない。君は至極まっとうなんだ。まっとう過ぎたんだ――。
それから何日かしてFから封書が届いた。脳に直接送られた指示で読まされた本のリストだった。便せんに何枚にも及ぶリストだ。唖然とした私は、もう一度Fの話を聞こうとしてはっとなった。職場の電話番号がわからなかったのだ。
「オレなんか名刺も無いんだぜ。信じられるか」
悔しそうな言葉が、私の脳裏に蘇った。
Fとはそれ以来会っていない。たしか職場結婚した奥さんと、小学校にあがるくらいの子供が二人いたはずだ。