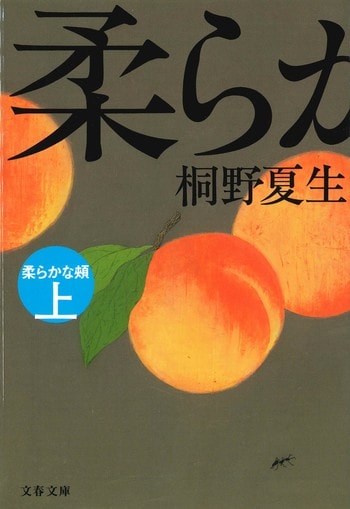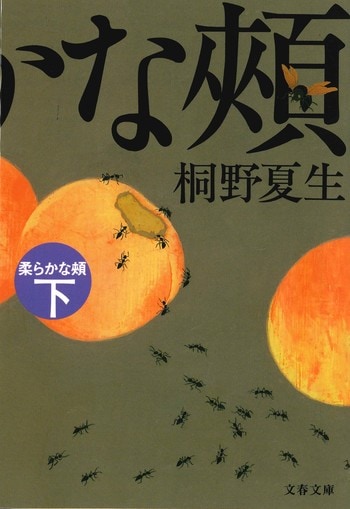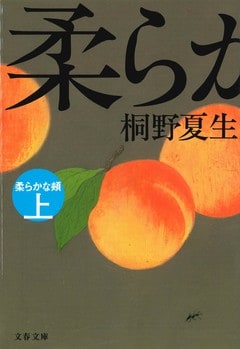〈特集〉桐野夏生の衝撃
・〈インタビュー〉強い虚構性は現実と拮抗しうる 桐野夏生
・桐野夏生の「小説=世界」のマニフェスト 佐々木敦
・私の好きな男 桐野夏生
・キューバ旅行同行記 大沼貴之
・桐野夏生 著作年譜

『柔らかな頬』は、桐野夏生のビブリオグラフィーにおいて、明らかなターニング・ポイントというべき傑作である。この作品は直木賞を受賞しているが、そうした文壇的な評価とはまた別の次元で、ある決定的な重要さを持っている。
一言でいえば、この小説を入り口に、桐野夏生は二度と後戻りすることができないような、前人未到のおそるべき「世界」へと、果敢に踏み込んでいった。
その「世界」とは、無数の「怪物」が跳梁する異形の「物語」としての「世界」であり、また「物語」る「怪物」たちの「世界」でもあり、そしてそれ自体が「怪物」的な「物語=世界」である。
閑静な別荘地で起こった謎の幼女失踪事件。母親カスミは自分の隠された姦通が事件を惹き起こしたのではないかと懊悩し、娘を捜すことに人生を捧げようと決意する。それから四年後、事件に関わった刑事・内海は末期ガンの宣告を受け、警察を辞してカスミと行動をともにする。傷を負った者同士の共感がカスミと内海のあいだで生まれ、いつしか二人の捜査は、終わりのない道行きのようなものになっていく……。
通常のミステリや犯罪小説と同じつもりで読み進めていくと、後半の展開に驚かされることになるだろう。冒頭の一頁からはまったく思いも寄らなかった幕切れが、ラストには待ち受けている。
ごく平凡な、そして平凡であることを運命づけられてもいるかのような人物たちが、何らかの理由で著しく非日常的な状況に陥り、本人も気付いていなかったような内なる力を露わにして、一種の「怪物」へと変貌を遂げていく、といったストーリーを、桐野夏生は繰り返し描いてきた。それはまた同時に、実はどんな人間も「平凡」などではない、というメッセージを含んでもいる。
誰もが己の内に「怪物」を抱えている。それを肯定的にのみ捉えるなら、ハードボイルドでヒロイックな様相を帯びることにもなるが、「怪物」とは制御不可能であるがゆえにそう呼ばれるのだとすれば、遂に「怪物」化してしまった人物たちは、やがて自らの「怪物」性を持て余し、最終的には、文字通りに身も心も“壊れて”いくことにもなりかねない(この過程を描いたのが、たとえば『OUT』であり『ダーク』だ)。
『柔らかな頬』以後の桐野夏生の「世界」においては、この“壊れて”いくさまが、異様な迫力を帯びた筆致で記述されることによって、小説そのものも、ある意味で“壊れて”いくことになる。ディテールの瑕疵(かし)やプロットの破綻は、凡庸な作家ならば単なるマイナス要因でしかないが、桐野作品においては、それ自体が強度の魅力を放つ。
いや、それはむしろ、旧来の予定調和的な小説像を根底から覆す、まったく新しい「小説=物語」の在り方を創始していると言うべきかもしれない。
「物語」は次第に変形し、歪み、捻れ、千切れて粉々になり、嵐のように荒れ狂う。その時、小説の読者もまた、もはや安全地帯に置かれた「物語」の観察者ではなく、「怪物」と化してしまった登場人物ともども、激しい嵐の只中にあり、荒れ狂う「物語」をともに生きることを要求されているのだ。