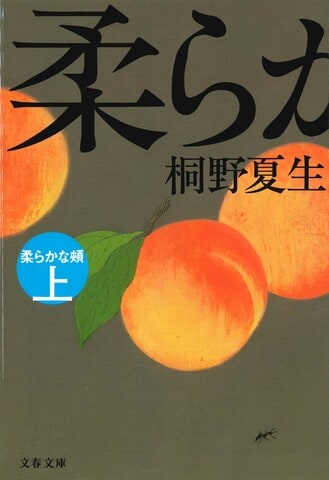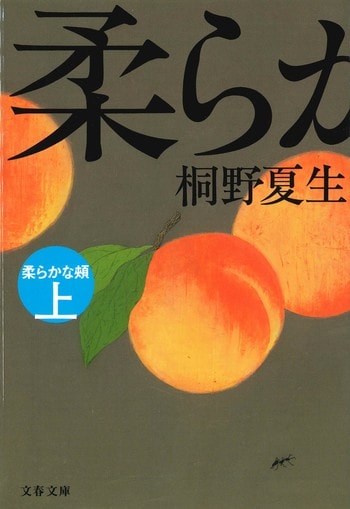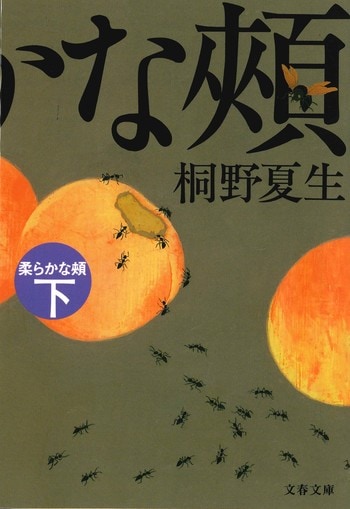小説の中に残した“棘”
――一月に出る初のエッセイ集『白蛇教異端審問(はくじゃきょういたんしんもん)』(小社刊)の中で、事件というのは現実の裂け目であるとおっしゃっています。子供の失踪というのも、大きな裂け目の一つですね。
そうです。その子がどうしているのか。連れ去った人間はなぜそういうことをしたのか。単純な物事など一つとてない。それを単純化するのが小説ではなく、複雑なものを多様な紐を組むように一つの世界に織りあげるものが小説ではないか、と思っています。
――今、現実の世界では、人間としてタガが外れたような理不尽な事件が起こっています。現実がどんどん先に行って、小説は後から追いかける。あるいは小説は現実を非常に平板に説明してしまう。トラウマがあって、悪を行なう人間たちがいて、と。桐野さんは、むしろ現実を超えていく。
虚構性を強めないと虚構の中のリアリティは獲得できない。それは当たり前ですが、だから、作家としては一生懸命虚構性を強めていって、激しい世界を作り上げる。では、その世界は今の現実とどういう関係があるのかといったら、それだけ虚構性を強めたものは、やはり現実とも拮抗しうる。そのぐらい強くないと、今の世の中で小説が必要とされなくなってしまうと思うんです。だから私は必死に戦っているつもりなんですが(笑)。普通の人たちのタガが外れる瞬間は、もっとタガを外した小説でないと解明できないと思います。
――実際に強い虚構を作り上げていくときに、リアリティを失わないものをどうやって作るのですか。
桐野夏生という一人の人間の経験がアトランダムにあって、どこかでパズルがうまくはまる瞬間があるんです。『残虐記』のときの片腕の検事。あの人は、『グロテスク』の取材で法廷に通っていたときの検事でした。毎月一度、同じ殺人事件を傍聴していて、とても印象的な法廷だったのですが、あるときふと、検事の手が義手だと気がつきました。私には、欠損から、その人間を考える癖があるので、片腕がないということはどういうことなのか、考えました。その後、『残虐記』で、検事を登場させることになり、そこで、ふとその検事が浮かんだんです。うまくパズルが合ったという感じですね。あとは、一生懸命、考えます(笑)。
――その法廷の話は『白蛇教異端審問』の中の「一線を越える」というエッセイにも書かれていますね。もし犯人の気持ちを想像して書くとしたら、小説家としてとても重い荷物を背負うことなのだと。書く側の覚悟の話ですね。
だから、怖いですよ。『残虐記』のときも、『グロテスク』のときも、やはり被害者のご家族は、絶対嫌な目にあっているはずだし、私がさらに「これは本当にあった」と言われかねない虚構を書くわけですから。例えば、被害者やそのご家族は、なぜこんなことを知っているんだろう、ということも言いかねない。調べたわけでもないのに、作家の想像力は、ときに真実を探り当てることもある。それも怖い。しかし、書く以上、「これは虚構。私が作った物語です」と言えるだけのものを書かねばという覚悟は常にあります。そして、もっと想像力を鍛え、それ以上にすごいところへいかなければとも思いました。
――先ほどから話に出ている『白蛇教異端審問』には、ご自身のことや石をひっくりかえすのが好きだった元気な子供時代のことなど書いたエッセイ、書評、映画評なども収録されていて、ファン垂涎(すいぜん)のエッセイ集となっています。その中で、創作の秘密といえる“小説の棘(とげ)”の話が面白かったのですが。
小説の中に一カ所、違和感を残しておく。それは自然にできてしまうことが多いんですが、すると、その違和感がまた別のものに膨らんでいく。だから、自分で書いていて、変なところがぽんとできたときは、これはうまくいくな、と思ったりしますね。なぜこの人が、こんなことを言うわけ? というようなことが起こってくると、うまい具合に転んでいく。それが“棘”ですね。
――その棘というのは無意識から生まれてくる?
無意識だと思います。
――原稿を書いていて、フッと浮かぶわけですか。
浮かぶというより、いつの間にか書いています。例えば、五人ぐらいの登場人物が会話しているとすると、一人がとんでもないことを言い出し、そこから場が急転したり……そういうことがあるんで、もう勝手にやらせてます(笑)。自分もどこかへ連れていってもらいたいんですね、物語によって。だから、物語に身を委ねてみる。
でも、全然それが起きないときもあって、そんなときは、人物にまともなことを言わせないようにします。例えば毎日新聞に連載中の『魂萌(たまも)え!』でも、寝たきりの妻が「あなた、私が死んだら解放されるでしょうね。ごめんなさいね」と言うのが普通だとしたら、「絶対死なないわよ」と言わせてみると、ガラッとシーンが変わり、言われた男の魅力が急に上がったりするんです。
――今後、どのような作品を考えていますか?
まず、雇用の問題をテーマにしたニート(学生でもなく、働いてもいず、職業訓練も受けていない若者たち)の反乱小説。最近の若い人の犯罪や集団自殺などは、すべて一種の反乱ではないかと思っているので、今度、新聞小説でやろうと思っています。あと、建国するというのはどういうことか、という話を書き下ろしでしたいと思っています。それから旧石器捏造なども。現実の裂け目として事件を捉えていく作業より、もう少し大きな枠組み、社会や国家などを身近なところから考えていくような仕事をしたいですね。
――小説に書かれたものより、あくまでも入口であるはずの事件をどうこう言われることがありますよね。
『グロテスク』と『残虐記』で、現実の事件を綿密に取材してデータを集めて書いていると思われたんですが、本当はそういうタイプの作家じゃないんで(笑)。おっしゃるとおり、事件はあくまで入口なのですが、小説の捉えられ方は、どうしても矮小になる。そういう見方にはちょっと飽き飽きしたので、じゃあ、誰も知らない世界を構築しようじゃないか、ということですね。
――つまり、分かりたいようにしか分からない。
そうなんです。今まで『光源』にしても『玉蘭』にしても、一言で言えない小説も書いていたんですが、そういうことは誰もおっしゃらない。分かりたいようにしか分かられないんだったら、もっとどんどん分かられないほうに行こうかなという、意地悪な気持ちがあって(笑)。
――作品が出るたびに、枠組みを破壊し続けて、どんどん枠を超えて膨張していっていると思うのですが。
膨張……そうですね、いつかまた縮小していくと思うんですけど(笑)。というか、退嬰(たいえい)とか衰退も悪くないと思うんです。そういう時期が来たらそうなろうと。でも、今は前と同じことをしたくないという気持ちがとても強いです。