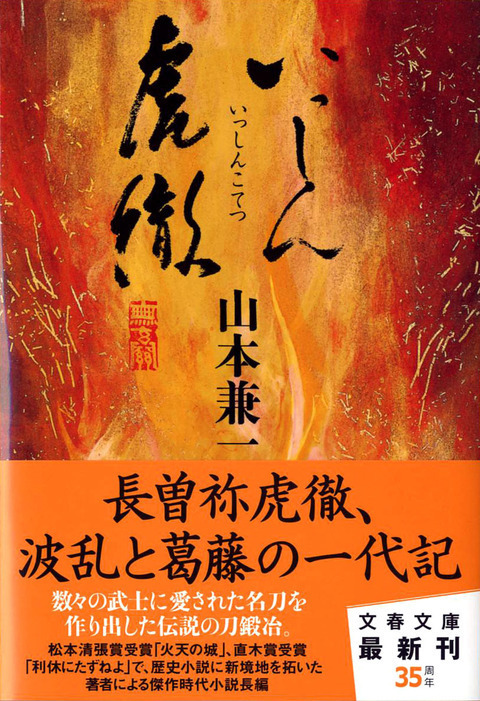――『いっしん虎徹(こてつ)』は、山本さんにとって四冊目の小説です。これまでの三作(『白鷹伝』『火天の城』『雷神の筒』)は、織田信長に仕えた超一流の職人たちに焦点を当てた、いわば信長のテクノクラート三部作ともいえる作品でした。今回は「刀」そのものに正面から切り込んでいますね。そもそも刀という分野になぜ興味をもたれたのでしょうか。
『白鷹伝』や『火天の城』で鷹匠や大工などの職人を書いているうちに、技術というものに対してさらなる興味が湧いてきました。日本には、ほかにももっと凄まじい伝統技術をもった人がいたのではないかと考えた時、日本刀を鍛えた鍛冶がいるじゃないかと気づいた。まずは博物館に行ったり、日本刀の鑑賞会に顔を出したりしているうちに、虎徹に行き着いたわけです。
――数ある名刀の中から、虎徹を選んだわけですね。どんなところが心に響いたのでしょうか。
なによりも緊張感ですね。虎徹の刀はいろんな表現がされています。「怒味(どみ)」と表現する人もいるし、「すすどしさ」、あるいは「ひらりとした感じ」などと言う人もいる。私の場合は、虎徹の刀を目にするたびに、ものすごく緊張感と存在感のある刀だと感じていました。
――それほどの緊張感をもった刀を作った鍛冶はどんな男だろうと考えたわけですね。
どんな男か、というのに興味を持ったのが一つ。もう一つは、日本刀の歴史をみまわした時に、どの鍛冶が最も日本刀のダイナミズムを象徴しているかという点です。その意味でも虎徹は、慶長以前の古刀が消え、江戸時代の新刀が生まれる時期に刀を鍛えた鍛冶で、日本刀と鉄の歴史のダイナミックな転換を描くにはうってつけでした。実際に、虎徹の刀は新刀期(江戸時代)にありながら、古刀と同じで鉄が柔らかい。そこが面白いんです。
――まさに、古くて新しいということでしょうか。
というよりは、新しいのに伝統のよさがあるということでしょうね。新刀期の刀には、ピカピカ光っているものが多い。その分、鉄(かね)そのもののしっとりした潤いが消えてしまっている。でも虎徹の刀は、姿は新刀だけれども、鉄には古刀の深い味わいがあるんです。
――刀の世界は奥が深いですね。この世界を小説にまで昇華させるために、相当の取材をされたと思うのですが。
刀匠の河内國平(くにひら)親方と知り合えたのが大きかったですね。五年ほど前に居合を始めたのですが、その知り合いの縁をたどって、偶然、親方に巡り会えたんです。親方から教えていただいたことばかりでなく、親方の生き方そのものから学ばされることがたくさんありました。
また、親方の紹介で研師の藤代興里さん、さらには小笠原信夫さん(元東京国立博物館刀剣室長・工芸課長)、たたら村下(むらげ)の木原明さんらにお話をうかがう機会ができたのも幸運でした。出雲のたたら操業は三回見に行きました。取材の締めくくりには、河内親方の鍛刀場の弟子部屋に三日間住み込みさせてもらって、炭切りを経験しました。
――まさに、虎徹が、たたらを目のあたりにして驚くシーンを彷彿とさせますね。そもそも虎徹は甲冑鍛冶で、三十代後半から刀鍛冶の修業を始めました。かなり遅い転身だと思うのですが、なぜだと思いますか。
第一の理由は、その時代の越前では、甲冑で食べていけなかったからでしょう。そしてそれ以上に、やはり刀が本当に好きだったからだと思います。
――小説の中ではせっかく刀鍛冶となり、一般的な水準でみれば出来のよい刀を打っても、なかなか銘を切ろうとしませんね。重病の奥さんがいるにもかかわらず……。
自分の作品を世に出すことを考えた場合、やはり納得のいかない刀は出したくない。どうしてもお金が必要で売るにしても、そこに葛藤がある。虎徹は特に、自分に課したハードルが非常に高かった人だと思います。また、刀鍛冶にとっては、いい刀を鍛えることと同時に、その刀を誰が所有するかということが大きな意味を持ちます。出来栄えのよい刀は、その刀をきちんと評価してくれる人に持ってほしい。これらは、現代に生きる刀鍛冶を取材していて感じたことです。超一流の刀鍛冶の矜持は、今も昔も変わらないでしょう。