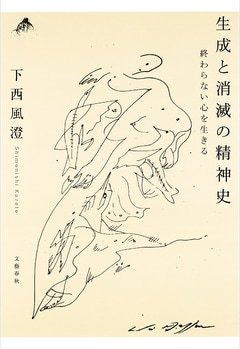本書は、生物多様性が頂点捕食者(トップ・プレデター)の存在によって守られてきたという仮説にいきつくまでの、科学者たちの研究の歩みを紹介している。本書にはさまざまな生態系において頂点捕食者(トップ・プレデター)消失がもたらした驚くべき事例が紹介されているが、読者の中には日本はどうなのか、という好奇心にかられた方も多いことだろう。
私は保全生態学者として、主に、日本のシカの繁殖が日本の植生にどう影響していったか、ということを研究してきた。
本書で紹介されているアメリカの例のように、日本でも、シカの被害は深刻である。私が仙台の近くにある金華山という島で研究を始めた一九七〇年代には、シカが植生に影響を及ぼしている状況を見ようと思えば特殊な場所に行かなければならなかった。しかし現在では、シカがいない県を探すほうがむずかしいという状況である。シカ問題は、初めは農林業被害が主であったが、やがてそのレベルを超え、自然植生への深刻な影響が懸念されるようになった。金華山などで起きていた植物群落の変化が各地で見られるようになり、森林の更新が心配されるようになってきたのだ。
さらに、シカがいなかった場所にまでシカが進出しだした。たとえば多雪地として知られる尾瀬にシカが入って湿原をかき回したり、ミツガシワという植物の地下部を掘り起こして湿原の水流を変えたりするなど、予想もしないことが起きるようになった。栃木県ではニッコウキスゲ、シラネアオイなど山地性の植物がシカに食べられ、ついには南アルプスなど高山地帯にまでシカが「登り」、高山植物を食い荒らすまでになった。
意外に思われるだろうが、シカ問題は東京にもある。東京西部の奥多摩町では、かつてシカは奥地に細々と生き延びていただけなのだが、過去十年あまりのあいだに徐々に増加し、植生にも影響をおよぼすようになった。人工林の多いこの山は地形がきわめて急峻でもある。面積のわりに暗い針葉樹林にはシカの食物が少ないために、植物はほとんどなくなってしまい、大雨になれば土砂崩れが起きるようになった。場所によっては修復のために数億円をかけて大工事を行うという、予想だにしなかった事態をもたらしたのである。
こうした事態を受けて植生学会が二〇〇九年から二〇一〇年にかけておこなったアンケート調査によると、シカの影響が太平洋側を中心に全国に波及していることがあきらかになった。
シカの急増について、いくつかの説明が試みられているが、共通しているのは本書の仮説と同様、日本列島には頂点捕食者(トップ・プレデター)がいないという点である。大型肉食獣としては北海道にヒグマが、本州以南にツキノワグマがいるが、彼らがシカの頭数を抑制するという証拠はほとんどない。ヒグマがエゾシカを攻撃する例はあるようだが、今のところほとんど問題となるほどではないようだ。この点、日本で絶滅したオオカミは、ユーラシアでも北アメリカでもシカの捕食者として不動の位置にあり、高い知能と組織プレーによってシカの頭数を抑制してきた。
ただ、日本の場合、シカの増加がこの二十年ほどで急激に起きている。オオカミが絶滅したのは一九〇五年とされる。オオカミがいなくなったせいでシカが増えたのであれば、約百年間増えなかったことをどう説明するのか。諸説あるが、明快な決定打はない。
はっきりしているのは、「シカ問題」は農林業の盛んな地域から始まったこと、当初はまさに農林業の害獣として個体数抑制がはかられてきたのが、次第に自然植生へ影響を与えるようになり、今では高山植物にまで影響を及ぼすまでになったということである。農林業であれば柵を張るなどの方法も採れ、駆除によって効果もあがるが、自然植生への影響を排除するためにハンターの出動を期待することはできない。高山の国立公園はしばしば特別保護区であり、動植物の採集などは厳しく制限されているから、そこでハンターがシカを射殺するというのは常識的にいってもおかしなことであるし、継続的にできることでもない。
シカが増加して植物群落が大きく変化し、そのことが植物を利用する小動物や物質の流れを変えている。そして、そうした微細な変化が全体として大きな変化につながってゆく。そういう意味で、私は、日本列島で増加し、分布を拡大させているシカの存在を、これまで以上に注意深くとらえるべきだと考えている。訓練をつんだ観察者の目には、最近の関東地方、中部地方のかなり広い範囲でシカの影響が出ていることがわかる。何気なくみれば「豊かな緑がある」としか見えないのだが、そこには、実は重大な変化がある。
さて、著者は第十章で、北アメリカにゾウやライオンを導入するというプロジェクトを提唱した科学者たちのエピソードを紹介している。第八章でとりあげられている、イエローストーンへのオオカミの再導入などとともに、頂点捕食者(トップ・プレデター)を人間の手によって再び、生態系のなかに戻すという壮大な実験の帰趨を追いかけている。
オオカミ再導入に際しては、オオカミの存在の是非を議論し、研究者がデータを出し、復帰のためのプロジェクトを作り、社会合意を形成し、実行に移した。そのために巨額の予算が投入され、すぐれた研究がおこなわれ、十分な準備がおこなわれた。
我が国でもオオカミ復活を提唱するグループが活動している。ただ、本書でも指摘しているように、頂点捕食者(トップ・プレデター)を機械の部品のように、もとに戻せば生態系がもとどおりになるわけではない。どんなに小さな動物でも、それだけが生きているわけではなく、さまざまな寄生虫や病気も保有している。ましてや異なる系に大型の外来生物が侵入した場合に、想定もしていなかったような事態が生じた例は枚挙に暇がない。
日本の例としては、奄美大島で一九七九年に、ハブとネズミを退治するために外来種のマングースを導入した例がある。この事業は成功しなかったばかりか、繁殖力の強いマングースは、天敵のいない環境でまたたく間に繁殖して農業被害を出すようになったうえ、ヤンバルクイナやアマミノクロウサギなどを捕食するようになり、希少な固有種が絶滅の危機に瀕するという皮肉な結果になった。
我が国は動植物の愛好家が多い国といえるだろう。野草の名前をよく知っている人も多いし、バードウォッチングも人気があり、昆虫マニアもいる。しかし、本書が強烈に示しているのは、自然の仕組みを理解すること、生態系における動植物の役割を解明することのおもしろさと、重要性である。本書から学ぶことは多い。