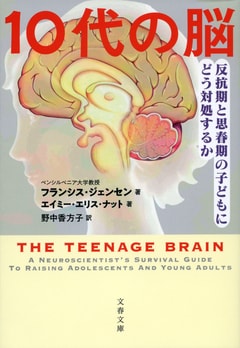この度、『心はすべて数学である』(2015年文藝春秋発行。以下、『心はすべて』と略記)を文春学藝ライブラリーから文庫本として出版することになりました。『心はすべて』はカオス力学を基軸として複雑系脳科学分野を開拓してきた筆者の脳と心の関係に関する一試案を広く世に問うために執筆したものでした。古くから哲学、脳科学分野の多くの天才、俊才たちの間で議論が闘わされてきた脳と心の関係について、筆者のような浅学菲才のものが解決策を見出せるとは到底思えませんが、他方で筆者はこれらの人たちとは全く異なる研究経験をしてきましたので、それを基盤に考えるならばさらなる議論のための新しい視点を提供できるのではないか、という考えが芽生えてきたのでした。
それは、数学という学問の意義に関する視点です。筆者は長年数学という学問と向き合いながら(それを“メシのタネ”にもしながら)、そもそも数学とは何だろうかと自問してきました。そして、数学の成り立ちから、また数学者の数学への向き合い方を日常的に見るにつけ、数学という学問は人の心の動き方、動かし方を抽象化したものであるという考えに至りました。そして、数学は人類共通の普遍的な心の表現ではないかとまで考えるようになりました。この普遍的な心がコミュニケーションを通して個々人の脳に影響を与え、脳を発達させるのだという考えに至ったのです。個々人の脳活動が心を生み出すのではなく、普遍的な心、すなわち数学的構造が個々の脳活動に対する拘束条件として働くことによって脳が機能分化し、その結果個々人の脳に個々の心が創発されるように見えるのだという考えです。少々荒っぽい言い方をすれば、他者の心の集合体が自己の脳に入り脳を発達させているという考えです。最近、これを「拘束条件付き自己組織化」と称して、他者の情報(心)と自己の脳神経ダイナミクス(脳・身体)の総体を変分する(ある種の最適化)問題として提案しています。
自己組織化を定式化する試みは数学者のノーバート・ウィーナーが提案したサイバネティクスの研究運動の中で最初に行われたようです。それ以前にも自己組織という考え方は、例えば哲学者のアンリ・ベルグソンが提唱した創造的進化という考え方の中に生命的なものが持つ特異な機能に共通する創造(創発)の在り方として見出されますが、概念的に明確化され、数学モデルによる理解が開始されたのはサイバネティクスの時代だと考えられます。複雑系研究の先駆者で精神科医のロス・アシュビーは「自己組織化する動力学システムの原理」において、創発するシステムの状態はある集合に収束し最終的にはその“吸引集合”上で新たな創発が行われるという考えを提唱しました。今日の力学系の言葉で言えばアトラクター上で新たな自己組織化が起こるということです。また、物理学者で哲学者のフォン・フェルスターは「雑音の中からの秩序」を強調しました。この意味は自己組織化はランダムな摂動によって促進されるということで、統計物理の考え方を自己組織化理論に取り入れたものだと考えてよいと思います。その後、多くの物理学者、数学者、生物学者、工学者が自己組織化の問題に取り組みました。中でも、特筆すべきはイリヤ・プリゴジンの率いるブリュッセル学派とヘルマン・ハーケンのグループの研究です。両者ともに非平衡状態での非線形システムを扱いました。特に、平衡から遠く離れた非平衡状態を実現するには、系に一定のエネルギーを注入し力学的あるいは化学的な仕事に有効に使えない熱や反応生成物などを系の外に放出し、系を一定レベルの定常状態に置く必要があります。エネルギー散逸が逆に系の自己組織化を促し、「散逸構造」という非平衡構造を生み出します。この非平衡定常状態を非線形熱力学を基盤にして定式化したのがプリゴジンたちでした。ハーケンは非平衡系で典型的な物理系を扱うことで、ミクロな原子、分子の協同的な相互作用がマクロな非平衡の秩序状態を創発する原理を開拓しました。これが「隷属化原理」と呼ばれているものです。これらの自己組織化の数学的定式化は定常状態で行われましたので、系に対する境界条件は固定されています。ですから、この理論(これ自体素晴らしいものですが)を“開かれた外部”と相互作用しコミュニケーションする脳の発達過程や内在する力学則が変化するような“発展系”(脳と心の問題はまさにこのような問題です)にはそのままの形で適用することは出来ません。発展系においては境界条件や初期条件は固定されず、他者からやってくる系全体に作用する拘束条件が新たな自己組織現象を生み出します。ですから、従来の自己組織化理論とは異なる変分が必要になったのでした。これが、右で述べた拘束条件付き自己組織化の問題です。