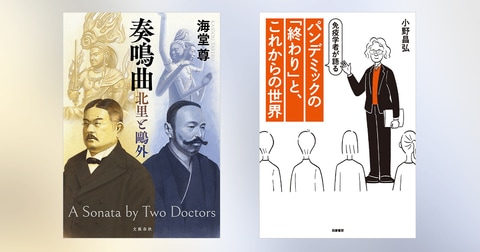科学を無視したコロナ禍のアメリカでの妊娠
2020年、私は渡米14年目の医師として、また妊婦として、新型コロナパンデミックを経験しました。
アメリカのコロナ対策に関して、トランプ政権下の政府と一部メディアの「科学の無視」はひどいものでした。「コロナは存在しない」「マスクで我々の口を封じようとしている権力者には屈しない」と感情に訴える、政治的なメッセージが混ざった非科学的な情報がソーシャルメディアなどで拡散され、多くの人が間違った情報を元に煽られた「なんとなく」の感覚に従い、パンデミック初期から堂々とソーシャルディスタンスを取らない、マスクを拒否する、大勢で会食をするといった行動に出ました。政治的分断が医学や科学的事実の解釈にまで直接影響を及ぼす事態に私は驚きました。
しかしウイルスは、人々の感情や信仰や政治的思想などとは関係なく、感染していくものです。こうしてアメリカでは科学を無視することで、病院には人工呼吸器が必要なくらい重篤な患者さんが次々に運ばれ、国内だけで100万人以上の方がコロナの影響で亡くなる結果になりました。
また、ワクチンがまだ存在しなかったパンデミック初期は、「誰かがかかってしまった」と他人事で終わる状況でもなく、感染者が存在する限り、人々の生活は制限され続け、自分への感染の恐怖と隣り合わせだった時期で、2020年のアメリカでは、とにかく自分や家族の感染を避けたいと怯える毎日でした。私はこのようなアメリカのコロナ禍の中で医師として働き、また3人目の子どもを授かりました。3人目はほしいと思っていたものの、実際妊娠がわかったときには、喜びよりも不安の方が大きかったのです。
妊娠中のコロナ感染は重症化のリスクが同世代の女性よりも高く、重症化してしまった場合は早産の確率が上がったりと、赤ちゃんも数々の身体的なリスクにさらされます。ただでさえ妊娠中は肺が子宮に押し上げられて呼吸が苦しい状況なのに、もし感染してしまったらどれだけ息苦しいことだろう、発熱が続いた場合にはどれだけお腹の中の赤ちゃんに負担がかかるだろう、夫や上の2人の息子たちにはどんな思いをさせてしまうだろうと考えました。
また、アメリカの学校は通常学級に戻っておらず(多くの公立学校は2020年3月より13か月間閉鎖され、リモートのみの授業でした)、我が家は一人にはしておけない5歳と3歳の子どもたちが「ママ、お腹空いた。ママ、これどうやってやるの? ママ、怪我しちゃった」と言う中で、リモートワークを強いられていた時期でした。
何か月間も育児と仕事の役割を夫と午前午後で交代してやりくりし、私の子どもたちはいつになれば普通の学校生活や習い事を経験できるだろうか、日本の両親は孫に会えるだろうか、そしてパンデミック中の、リソースが限られた育児と仕事に挟まれた苦しい生活に私自身はいつまで耐えられるだろうか、と感じていたのです。
妊娠中のワクチン~「接種するリスク」と「接種しないリスク」
ワクチンの安全性や有効性を示す治験の結果や、妊娠には影響を与えにくいと考えられるmRNAワクチンの仕組みを吟味して、妊娠34週だった2021年1月初旬にワクチンを接種できたときには、安堵の気持ちでいっぱいでした。何十年間にもわたるmRNA研究が高い予防効果と安全性を有するワクチン開発につながったことへの感動、また最前線でコロナ治療にあたっている医療者への感謝とともに、「もうすぐ普通の生活に戻れるかもしれない」という希望が胸を占めました。
さらに、世界でも初めてに近い段階で妊娠中にワクチンを接種させてもらった者として、後に続く妊婦さんのためになる情報を提供したい思いが強く、ワクチン接種をした妊婦の追跡研究に参加しました。私の妊娠の経過や、出産後の赤ちゃんの健康状態に関して追跡調査を許可し、また私がワクチン接種して産生した抗体が胎盤を通ってお腹の中の赤ちゃんに渡り、赤ちゃんをもコロナ感染から守ってくれることを確認する研究にも参加しました。
私自身は、妊婦さんのワクチン接種のデータがなくとも、既に充分に存在した基礎研究のデータを見て、このワクチンが私の妊娠や赤ちゃんに悪影響を及ぼすことはなく、重症化予防のベネフィットは大きいと自信を持てましたが、やはり多くの方が大丈夫と思えるには臨床研究が必要です。その後、私も参加した臨床研究によって、妊娠中の新型コロナワクチン接種の安全性と有効性を示すエビデンスが積み上がり、現在では妊娠中の接種は世界的に推奨されています。
私が妊婦としてワクチンを接種した2021年1月の時点で、日本では未だ新型コロナワクチンは承認もされておらず、mRNAワクチンのメカニズムの説明も十分になされないなかで、「なんとなく怖いワクチンなんじゃないか」と漠然とした不安を抱えた方が多い時期でした。
また、ワクチンを打つと流産する、不妊になるという全くのデマが知識層にまで蔓延しており、お腹の大きな私がワクチンを接種した姿を写した写真を私の勤めている病院がSNSに投稿すると、想像を遥かに超える反響がありました。毎日のように日本メディアからの問い合わせがありましたが、その頻度の高さからもインタビューの質問内容からも、どれだけ日本人がワクチンへの忌避感を抱いているかが伝わりました。
その状況を理解した上で、私はワクチン接種の意義、そして現段階でわかっている情報とわかっていない情報を考え合わせて、「接種するリスク」と「接種しないリスク」を天秤にかけた説明をしてきました。ワクチンを打つべきかどうかを決めかねている日本の方々、そして特にお腹の中の赤ちゃんのことを一番に考えて悩んでいる妊婦さんたちに、正確な科学情報を基に自分の気持ちにしっくりくる判断をしてもらいたいと強く思ったからです。
確かにmRNAワクチンという、従来とは異なるメカニズムで開発されたワクチンが全世界的に大規模接種されるといった事態は歴史的にも初めてのことで、たとえワクチンの安全性がさまざまに説明されても、不安が完全には払拭されないのもよくわかりました。mRNAの性質を考えると長期的な悪影響は非常に考えにいくいのですが、本当にないのだろうか、といった不安も多く聞かれました。でも、だからこそ、日々積み上げられていったデータを示しながら、一人ひとりの接種の判断を、とりわけ感染するとリスクの高い妊婦さんたちの判断を後押しするような情報発信ができればと思ったのです。
その結果、社会に対して大きくポジティブなインパクトを残すことができました。共に新型コロナワクチンに関する正確な科学情報を伝えたいと志す異なる専門知識を持った医師仲間にも出会い、メディアからの取材対応や行政機関への講義、非営利プロジェクト「こびナビ」によるSNSのライブ配信といった活動を連日行いながら、日本のワクチン接種率を世界有数の高さに上げることに貢献できたことを誇りに思っています。この活動は医療啓発活動に授けられる賞である、「上手な医療のかかり方アワード」の最優秀賞「厚生労働大臣賞」を受賞しました。
偽の「死産報告書」
しかし、啓発活動を続ける中で直面したのが誹謗中傷の言葉の数々でした。
最悪の母親、ブス、幼児虐待、発達障害を作り出す母親、といった言葉はSNS上で数千件にもおよび、「死産報告書:死因は母親のワクチン接種」などと書かれたメッセージも届きました。もちろん誹謗中傷によって私の妊娠経過が変わるわけもなく、誹謗中傷の言葉がコロナウイルスの性質やワクチンのメカニズムを変えるわけでもないので、実際の生物学的な影響力は無に等しく、私自身がお腹の中の子ども、そして家族を守るために妊娠中の接種を決意した事実も変わりません。
しかし、その選択が正しいと論理的にわかってはいても、お腹の中の赤ちゃんが死ぬという言葉をかけられ続けると、胎動が気になってしまったり、また、妊娠中にワクチンを接種したとメディアで紹介された私自身が健康な子を産まなければ、日本のワクチン忌避はさらに深まりかねないと要らぬ責任を感じてしまいました。
親(特に母親、あるいは将来母親になるであろうと思われる人)は、自分自身と家族(あるいは将来の家族)を守るための責任ある判断を迫られる場面が多々あります。しかし、その判断をするために必要な情報は必ずしも手の届きやすい場所にあるわけではありません。
そして最良の判断をバックアップしてくれるサポートに出会えないことも多いのです。それにもかかわらず、どんな判断をしたとしても、親としての判断は批判の対象になってしまう。妊娠中に新型コロナワクチンを接種した私へのネガティブなコメントはこういった現象を象徴していました。多くの判断を迷う母親たちの声に触れるなかでも同じことを感じ、実際、ワクチン接種をした妊婦さんのなかには、近しい人から批判をされた人も少なくなかっただろうと推測します。
ワクチン啓発活動を応援して下さる方々からのコメントの中にも、しばしば悪意のない「マイクロアグレッション(microaggression、小さな攻撃)」が潜んでいました。
「最初はいわゆる『勝ち組女性』の意見かと疑っていましたが、目にするたびに真剣さが伝わってきました」という応援メッセージを見て、「勝ち組女性」とはどういうイメージなのだろう、そして勝ち組とカテゴライズされた女性の意見はどうして疑われるのだろう、と考えさせられました。仮に発言しているのが男性の医師であったならば、「勝ち組男性」という言葉が出てきたでしょうか? 専門家としての意見が学歴の高さゆえに疑われることがあったでしょうか?
また、誹謗中傷で「死産報告書」を送られた件について、涙を交えて話すと、「女の涙は演技、泣き落としと言った悪しき偏見が向けられてしまうのが現実ですし、他者の目をもう少し気にして脇の甘さをなくしていただきたい」という声も寄せられました。胎児が死ぬと脅された妊婦が泣くという自然な感情さえも「これだから女は」と批判の対象になること、また一見味方と思われる人からの牽制的な声には二重の辛さがありました。
「マイクロアグレッション」とは、「政治的文化的に疎外された集団に対して日常の中で行われる何気ない言動に現れる偏見や差別に基づく見下しや侮辱、否定的な態度のこと」と定義されますが、日本社会の中で「女性」が未だにマイノリティであること、無意識のバイアスから生まれる小さな攻撃は日常の中のあらゆる場面に潜んでいることにも気付かされました。
科学、ソーシャルジャスティス、人間に惹かれた生い立ち
私は現在ハーバード大学医学部アソシエイトプロフェッサー、またマサチューセッツ総合病院の小児うつ病センター長という立場で、小児精神科医として子どもの精神疾患を診察する臨床、人間の感情や判断に関わる脳機能を解明する脳科学研究、そして医学生や研修医の医学教育に携わっています。研修医時代を過ごしたイェール大学で出会った愛するチェリストの夫と共に息子を3人育てており、子どものメンタルヘルスは単に職業にとどまらず、まさに自身に直接関わるテーマとして情熱を持って取り組んでいます。
人生を通してテーマとなっているものが三つあります。科学、ソーシャルジャスティス(社会正義)、そして人間が大好きだということです。振り返るとこの三つのテーマがちょうど重なった部分が小児精神科医という職業だったのだと思います。
私が生まれたときに母は医学部の4年生でした。幼少の頃の思い出として覚えているのは、母が医師国家試験のために猛勉強する姿、その後は研修医として駆け回っていたこと。大抵保育園の中で一番最後だったお迎えのあと、母とスーパーに寄って「今日の夕飯は何にしようか」と話したこと。たまにどうしても保育園に行きたくないと訴え、母の病院に付いていき、医局にあった箱庭療法の砂や人形で遊んでは他の先生に声をかけてもらったこと。
分子生物学者の父は、母の国家試験と同時期に博士論文を書いていて、大人は皆勉強しているものだと思っていたこと。父が仕事の後いつも急いで文字通り走って帰ってきていたこと。母の当直の日は、スポーツマンの父からサッカーや野球など様々なスポーツを教えてもらったこと。まだまだ「女性の医師」も「働くお母さん」も珍しかった時代に母が医師になる姿を見ることができただけでなく、その母をこよなく愛し、自分のキャリアも前進させる父、そんなカップルに育ててもらえたことが、どんなにラッキーだったことか、当時の私は全く知りませんでした。
父の研究のために、小学校入学前にアメリカに引っ越し、小学校時代はアメリカ、スイス、日本の3か国で5回の転校を重ねました。誰にでも合う生い立ちではなかったと思いますが、きっと両親は私の性格や反応を見ながら引っ越しや転校の判断をしてくれたのだと思います。
私は幼い頃から「人」が大好きでした。違う国に引っ越して転校する度に新しい友達を作る機会にワクワクし、様々な人と会話をするのが好きでした。また、人間がどのように感じて考えて行動に出るか、そんな人間がたくさん集まってできる社会では、グループとしての動きがどう生まれるのか、ということを考えるのも好きでした。人間が何かを感じたり考えたりするのを司っているのが脳という臓器です。その脳がどんな働きをしているかを知りたいと小学生の頃に強く思ったことも覚えています。
アメリカやスイスで過ごしたことで、多様性、多文化、そして人種差別を経験しました。ヨーロッパはアメリカ以上に白人至上主義の伝統が残っており、アジア人は馬鹿にしていい対象というような扱いを頻繁に受けました。同い年くらいの子どもたちに公園で囲まれて、ドイツ語(スイスの公用語の一つ)が話せないアジア人であるという理由で唾をかけられたこともありました。
人種差別の経験を経て日本に帰国したときには、小学校でのいじめが気になりました。小学校の文集で友人から寄せられたメッセージを見てみると、クラス内でいじめられている子がいたら、私が必ずその場でいじめっ子を止めたことや、仲間はずれにされた子に積極的に声をかけたりしていたことを書いてくれた友人が多く、実際理由のない偏見や差別、いじめといったものの無意味さに関してホームルームの時間に演説したこともありました。
人は、他人に完全に理解してもらえていると錯覚したり、理解されずに悩むこともあるものですが、実は理解されるためには努力しなければいけないということも、この変化に富んだ幼少期に学ぶことができた気がします。異文化を経験し、各国の常識の違いを体感する中で、周りからの期待に応えるのではなく、私自身はどのような人間になりたいかということもよく考えました。
また、私は幼い頃から科学が大好きでした。保育園の頃、分子生物学者の父が私を寝かしつける際、ヨットはどのように風の力を使って前に進むのか話してくれたのを覚えています。
小学生の頃にはリチャード・ドーキンスの『遺伝子の川』(草思社文庫)という本の内容を、ところどころ要約して聞かせてくれました。高校時代の生物の授業でプランクトンを探す課題が出されたときは、放課後も顕微鏡でプランクトン探しに熱中し、見つけた一つひとつをスケッチしました。その課題をこなす中で、偶然ミドリムシの分裂の瞬間を目にし、何千万年も繋がる遺伝子のリレーの中で新しい個体が誕生した瞬間を目にしたことに感動し、なんだか天から光が降りてきたような心地がしたのを覚えています。
高校2年生の夏休みにはアメリカの大学が主催した女子高校生のための科学プログラムのサマーキャンプに参加し、犬のロボットを作製しました。このサマーキャンプを通じて科学的な探究と創作の楽しさに目を開かされ、科学への思いを再認識した私は、科学を通して人間を理解し、人間と社会を支える医師になろうと決意しました。
科学が大好きでソーシャルジャスティスの意志が芯にある私は、科学が軽視されることにより、誰かが苦しむ様子はどうしても黙って見ていられません。日本のワクチン忌避を放っておけなかったのもそのためです。
オンラインヘイトとメンタルヘルスの関係
そして、私自身にも向けられたヘイトや誹謗中傷発言についても、いじめと同じ構図を感じ、ときにはそれが本人の意図や同意と関係なく拡散されて「炎上」といった現象になっていく様子は、メンタルヘルスとの関係からも見過ごせないと思うようになりました。
ネットメディアやソーシャルメディアでの人間関係の衝突や敬意を欠いた言動は、パンデミックが進行してから、各国で増えているという調査結果が出ています。例えばアメリカではオンライン上の会話で相手を中傷する発言がパンデミック前と比べて70%も増え、オンラインゲームなどでの喧嘩や悪口などが40%も増えたと報告されています。また、アジア人に向けられたネット上でのヘイトスピーチはアメリカでは倍増したそうです。
これは延々と続くコロナ禍の不安やもどかしさ、人々のメンタルヘルスの不調の表れでもあるのではないかと言われています。アメリカでは2021年に、私の専門分野である子どもたちのメンタルヘルスが「国家の危機と認定せざるを得ない状況にある」と国と学会による発表があり、日本ではコロナ禍に小中高校生の自殺者数と小中学生の不登校者数が過去最高を記録したとの報道があったように、子どものメンタルヘルスは未だかつてない危機にあります。
ただ、コロナ禍では、子どもに限らず辛い思いをしていない人はいなかったでしょう。将来の計画がなかなか立てられないもどかしさ、コロナの新たな波が来るたびに感染者数の増減を気にして外出を控えたり、友人との集いをキャンセルしなければならない残念な気持ちなど、終わりが見えない薄暗い気分、やり場のない思いを抱え、SNSでつぶやいたり書き込んだりした人も多いと思います。
しかし、そうした不安やもどかしさは心の正直な発露であって共感できる一方で、顔の見えない漠然とした「敵」を見つけたときに誹謗中傷に早変わりしてしまうこともあります。実際、コロナ禍では、ネガティブなコメントやソーシャルメディアでの攻撃的なやりとりも日常的に目にするようになりました。
炎上案件に巻き込まれる当事者である場合にはもちろん、自分宛のものでなくとも、誹謗中傷に溢れたSNSやコメント欄を日常的に目にしていては、鬱々としてしまったり苛立ちを覚えたり、何かと心に悪影響があるものです。
対面と違って匿名で発言できるバッファーのない空間であるからこそ、ある意味で本音むき出しの攻撃的な発言がなだれ込む。そのことは理解できても、でも、どうしてこんなに頻繁に「炎上」などという現象が生じるのか? どうして何かを推奨する派と忌避する派の分断の溝はここまで深いのか? そして、こうした分断は埋められないのだろうか? 自分自身に向けられた誹謗中傷や周囲の炎上を眺めながら、このような疑問を抱き、自問自答するようになりました。その結果、悲観的な気持ちになることもあるのですが、脳科学を研究する精神科医の立場からも、私は分断は乗り越えられるものだと希望を持っているのです。
“Them”と“Us”の色分け
ワクチン啓発活動を通して、多くのワクチンを忌避する方々とお話しする機会がありました。そこで毎回気付かされたのが、科学的事実を提示してワクチンを推奨する私たちも、ワクチンに対して漠然とした不安を抱く方々も、自分と家族などの大切な人たちの健康を守りたいと思う気持ちは同じだということでした。
ウイルスという見えない敵と戦うこと、重症化予防という可視化の難しいベネフィットを理解することの難しさ、薬害エイズ問題などの社会的に負のものとともに語られる医療の歴史の重み……。全てが複雑に融合して、漠然とした「怖い」という負のイメージが浮かぶ中で、ワクチン接種という大切な人を守る選択をすることは、想像以上に難しかったのだとわかります。
私は科学的事実を検証した結果、世界中で公的に推奨されているワクチンの接種を勧めてきました。しかし、ワクチン忌避の源にあると感じる「個人や社会の過去のトラウマの影響」にも、「明瞭に理解できないリスクやベネフィットに対する不安や混乱」にも、またそれにより構築された漠然とした負の印象から抜け出せないことにも、とても共感するのです。
“Them”と“Us”のように対比される対象に見えても、実はそんなに単純な色分けではないのです。その色合いの複雑さも含めての共感があったからこそ、私たちのワクチン啓発活動は分断を超えて、日本の接種率を上げることに貢献できたのではないかと感じます。そんな気づきの声が共鳴するたびに、社会を前進させられることにも気付かされたパンデミックでした。
「分断を超える」色が生まれた
私は以前、政治的分断や思想の分断といった社会の「分断」とは、グループが真っ二つに割れ、意見が相互にまったく交わらない状況を表しているという印象を持っていました。また「分断を超える」とは、多様な意見が認められるというよりも、全員が同じ意見を持つようになることだと思っていた気がします。しかし、実際にはその色分けの中には様々なグラデーションがあり、また色は様々な濃淡で多様に混じり合うのです。
経験や思いを共有することで、全員が「同じ色」になることはなくても、あると思っていた分断の線を超えて、個人が他の個人にエンパシー(empathy、共感)を感じること。経験がそれぞれ異なっていても、他者の思いや経験に思いを馳せてみること。エンパシー一つひとつはささやかで心の内にとどまることが多くとも、エンパシーが寄り集まって何かを強く変えたいという変化の原動力になることもある。コロナ禍のアメリカではより可視化された分断もありますが、逆に「分断を超える」現象も目に見える社会変化をもたらしました。
例えば、コロナ禍のアメリカで広がったStop Asian Hate 運動。新型コロナウイルスが最初に確認されたのが中国だったためにアジア人に向けられたヘイトに対して、Black Lives Matter 運動(黒人に対する警察の暴行や差別意識を撲滅するための運動)に影響される形で生まれた差別撲滅に向けたムーブメントでした。奪われた命は私だったかもしれない、ヘイトを向けられたのは私だったかもしれない──遠い誰か他人の身に起きたことだから関係ないと遠ざけるのではなく、無実の人が人種という属性によって暴行を受けたり、殺されたりしてしまう事態を目にした多くの人が「このままではいけない」と感じ、立場を超えて行動を起こしました。
特定の人種や性別に対して無意識に偏見を抱くのは誰であっても同じ。だからこそ無意識の偏見に気付く努力の大切さが広く語られ、その結果、教育現場や職場環境にも構造的変化がもたらされました。また、アジア人のスーパーヒーローの映画が作られたり、メディアのなかで描かれる人間像にも今までにない変化が見られました。もちろん人種差別やアジア人ヘイトは未だ存在し、分断がなくなったわけではありません。しかし、皆が同じ色になったわけではないけれど、多くの人の共感が「分断を超える」色として交わり、社会の変化を促したことは間違いありません。
変化というものは起きてから気付くことも多く、起きる前は望む変化後の社会がどのようなものかを想像できずに、諦めの心が先行してしまうこともあります。しかし、こうした激動の時代を生きてみると、「自分の力で変化を起こすことができる」、そして「変化を望んでもいい」と勇気が湧いてくるのです。
「ではどうしたら炎上や分断を超えられるの?」という質問に私も明確な答えはありませんが、心理学も含めた脳科学の知見、そして私自身の経験や子どもたちと過ごす日々から気付かされたヒントをこの本で紹介させてください。
「プロローグ 妊婦のワクチン啓発で気づいたThemとUs」より