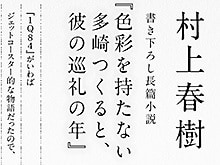「弟子」とか「ファン」というのは、「読書経験を通じて、今の自分と違うものになりたい」という開放的な立場でテクストに相対する構えのことです。テクストの中に、ごく微細なものであっても、それが「自分を変えてくれそうな予感がする」徴候であれば、それを決して見逃さない。そのような貪欲な姿勢でテクストを読むのが「弟子」であり「ファン」だと思う。遠目から、身じろぎもしないで、無感動に作品を語ることが学術的に正しくて、作品そのものの中に身を投じて、触れるものすべてを味わい尽くそうとするような接近の仕方は学術的に誤っていると僕は思いません。現に、読み手にそのような破格の愉悦を与えてくれる作品だけが「論じるに価する作品」として文学史にその名を残しているわけですから。誰しもが遠目からクールかつリアルに論じられるような作品はそもそも文学研究の対象にならない。なるはずがない。
でも、まことに残念ながら、僕が実践してきた「ファンとして、崇拝者として、弟子として語る」という方法は学術的にはいまだに認知されておりません。せいぜい個人的なメモワールや、エッセイのようなものとして扱われている。そういう構え、そういう文体によってしかたどり着くことのできない学術的な「深み」や「高さ」があるということを認めてくれる人は少数です。
では、学術研究の主観性・客観性はいったい何によって査定されているのか。例えば、文科省の科研費の採否は当該学術研究の価値についての“客観的”判定基準に基づいていると思われていますが、僕に言わせればそれもまた「ある歴史的状況下における、ある社会集団に固有の“民族誌的偏見”」という以上のものではありません(「当代の政権の文教政策との親和性」に過ぎない場合だってあります)。教育予算分配の査定権限を持っている権威に対して現に「従者として」ふるまっている研究者だっている。
誤解しないで欲しいのですが、別に僕はそれが「悪い」と言っているわけではありません。「そういうものだ」と言っているのです。研究の価値はアプローチの適否によって決まるのではない。どんなアプローチだって構わない。その研究が結果的に“研究対象についての集合知をどれほど賦活したか”によって決まる。僕はそう思っています。
文学研究なら、その作家論なり作品論が書かれたことによって、多くの人がその人の本を読み、作品について作家について語ることを欲望するようになったとすれば、それはすでにひとつの知性的な達成だろうと思うからです。
書いているときには別に明確な方法論的自覚はなかったのですが、こうやって改めてまとめて読み返してみると、僕はかなり挑発的な文学批評を志していたのであるなあと思いました(自分で言うのもあれですけど)。そういうわけですので、どうぞ本文にお進みください。
二〇一四年十月
(「文庫版のためのまえがき」より)