
世界最大の岩壁。そのスケールが、どれくらいかご存じだろうか?
基部からの標高差は四八〇〇メートル、東京スカイツリーを七つ重ねてもまだ足りず、富士山の標高を千メートルも上回るという。
この想像を絶する岩の巨壁――ルパール壁があるのは、パキスタンのギルギット・バルティスタン州。標高八一二六メートル、登山者の生還率の低さから「魔の山」、「人食い山」の異名を持つ高峰――ナンガ・パルバットだ。笹本稜平『大岩壁』は、四十八歳のベテランクライマー――立原祐二が、ルパール壁を振り仰ぐ場面から幕が上がる。
五年前、立原は冬のナンガ・パルバットに敗北していた。西面ディアミール側からの冬季初登頂を狙い、ふたりのパートナー――二歳年下の木塚隆とハードクライミングのエキスパートである二十四歳の倉本俊樹とともに挑んだが、猛烈な嵐に行く手を阻まれ、凍傷により手の指を三本と足の指を五本、そして下山中に倉本の命を失ってしまう。
その倉本が死の直前、登頂を断念することも考え始めていた立原にいった思いも寄らない言葉が、いまふたたび立原をナンガ・パルバットへと赴かせていた。
「もう一度やるとしたら、ルパール壁を狙いませんか」という、あの言葉が――。
笹本山岳小説は、作品を重ねるごとに洗練され、透明度を増している印象を受ける。エベレスト頂上付近に墜落した人工衛星をめぐる謀略アクション『天空への回廊』から始まった流れは、『還るべき場所』で“謀略”要素を脱ぎ捨て、マッキンリーに魅入られ消息を絶った孤高のクライマーを追う『その峰の彼方』でひとつの到達点を迎えたように思う。「おれはただ、生きているふりをしているのが嫌なだけなんだ」、「未来を決める権利は人間にはないかもしれないが、信じることはできる。信じる力は涸れることのない勇気の泉なんだよ」という、思い返すだけで胸の奥に熱が生じる“魂の言葉”(単行本帯の惹句より)は、余計な細工や装飾を施すことなく、山に畏敬の念を抱き、憧れ、真摯に挑戦する者を真正面から描いているからこそ、強い説得力をもって深く響く。
『大岩壁』も、亡きパートナーの遺志を汲んだベテランクライマーによる再挑戦という、じつにシンプルなストーリーだ。そして笹本稜平は洗練と透明度の到達の先に、木塚の台詞としてこのような問いを読み手に投げ掛けてくる。「金にもならない。世間がそれほど注目してくれるわけでもない。そのうえ命まで失いかねない。そんなことに夢中になれる馬鹿がいるから、逆に世の中は正気を保っていられるんじゃないですか」と。
冬のルパール壁を攻めるにあたり、立原はパートナーとして木塚ともうひとり、倉本の弟――晴彦を新たに加えることになる。ミックスクライミングと高所順応では兄に負けないと豪語し、兄との関係を「命の恩人です。体も魂も共有している、特別な兄弟なんです」と語る少々度を超えた敬愛ぶりを見せ、冬季初登頂に異常なまでの執念を燃やす晴彦。しかし立原の耳に、つぎつぎとよからぬ噂が届き始め、ついにある局面で不安が的中してしまう。
第六章以降、二〇一〇年代山岳小説の第一人者が描く登攀シーンは、さすがのひと言に尽きる。やはりルパール壁側からの初登頂を狙うロシアのパーティーとの駆け引き、立原を翻弄する晴彦との極限の勝負、クライマックスを経て立原が目にする信じられない光景……。
涙で視界が滲むこと必至のラストシーンで、木塚の台詞が改めて甦る。この境地を理解できない人も、なかにはいることだろう。しかし、そこに描かれた美しさを否定する人は誰もいないはずだ。命を懸けて自らの夢を果たし、果たした夢を惜しみなく称える、そのなにものにも代えがたい美しさを。

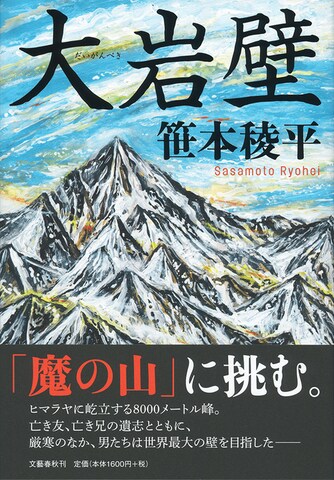
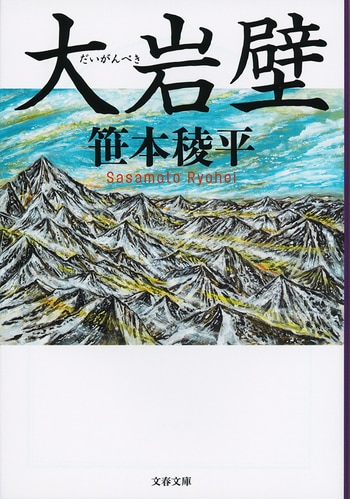
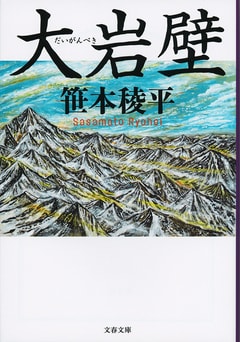


![[映画化記念対談]笹本稜平(原作者)×木村大作(映画監督)山小屋に希望を託して](https://b-bunshun.ismcdn.jp/mwimgs/c/6/480wm/img_c649310d5205e54d5cae3c7b6d09dfad43969.jpg)











