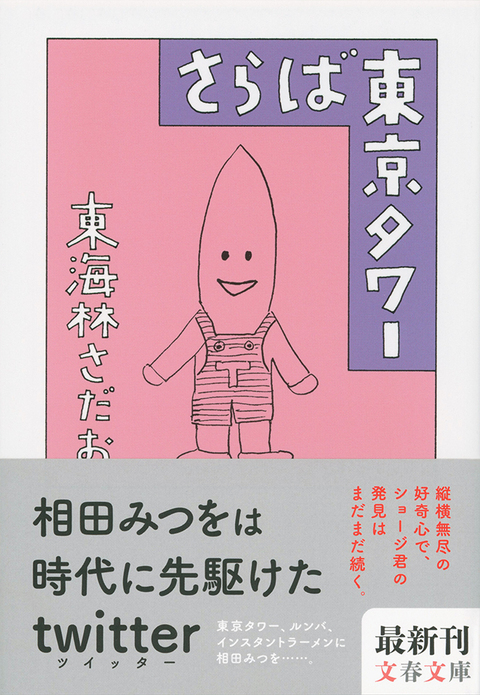
熟年、老人の社交ダンスが、はやっているという。そういう場では、女のほうから男にペアをくみたいともちかけるケースも、あるらしい。ダンスにとりくむ者は、女のほうが多いから、男の売り手市場がなりたつ。この本におさめられた最後の対談では、そんな昨今のホール事情が、話題になっている。
毎日いそいそと会場へやってくる某女性のことを、話し相手の小林照幸はこう描写する。「キャスター付きのバッグにドレスやシューズを入れて来るんですよ」、と(二五八頁)。私は、このくだりにハラハラさせられた。一冊を読みとおすなかで、いちばん胸さわぎをおぼえたのは、ここである。
そこから、二十五ページほど、さかのぼってほしい。「鞄の哀れ」という文章のなかで、著者はつぎのようにのべている。
「鞄の底に車がついていて、手で引っぱるワッカのようなものもついていて、ズルズル引きずって使う鞄。あの鞄、どう思いますか。ぼくはあの鞄を自堕落にズルズル引っぱって歩いている人が嫌い。大っ嫌い。あれをズルズル引きずって歩いている人を見るとムカムカする。だいたい馬鹿面をしている人が多いですね、あれを引っぱって歩いている人は」(二三三頁)。
なぜ、そんなにいやなのか。著者は、「いまだにその理由がよくわからない」という(二三四頁)。とにかく、いやだというのである。この嫌悪感には、けっこう根深い何かがあると、読み手の私はうけとめた。
その十数分後に、でくわしたのである。「キャスター付きのバッグ」で、連日ホールへやってくる女性の話に。どきどきするなというほうが、無理だろう。
もちろん、著者はそこで話の腰をおり、対談をぶちこわしたりはしていない。そういう女は自堕落なやつにきまっている。馬鹿面をしていたにちがいない。とまあ、そんなふうに小林の語るエピソードをさえぎりはしなかった。社交ダンスをめぐる会話の流れはとめずに、話をすすめている。大人の対応をしたのだと思う。
しかし、著者の脳裏には、わだかまりがのこりつづけたのではないか。「キャスター付きのバッグ」で、毎日やってくるんだって。ろくな女じゃあないだろう、そんなのは。以上のような感情をぬぐえぬままに、対話を継続していたかもしれない。
無難に見えるやりとりだが、潜在的には破綻の可能性もひそんでいた。そう想って読みすすめば、ウエルメイドなこの対談でも、読書のスリルがあじわえる。誤読かもしれないが、私はその可能性に想いをはせつつ、これをたのしんだ。
私見だが、「キャスター付きのバッグ」を愛用する女性にも、すばらしい人はいる。チャーミングな人も、いなくはない。そういう人とであった時、著者はどう対応するのだろう。心を鬼にして、自堕落な馬鹿面はいやだと、意地をはりとおすのか。小林との対談では、そこを浮きぼりにしてほしかったなと、私は思っている。
いや、ひょっとしたら、著者は「キャスター」の意味がわからなかったのかもしれない。じっさい、「鞄の哀れ」にも、「底に車がついて……引きずって使う鞄」と、ある。「キャスター」という言葉は、一度もつかっていない。なじみのない言葉だったから、対談では聞きすごしてしまったのだろうか。
もし、そうであるのなら、波乱の気配を感じとった私が、まちがっていたことになる。しかし、「キャスター」というカタカナがわからないというのも、失礼な想像である。私としては、対談の背後にさざ波を想いうかべ、ふたりのやりとりをあじわいたい。
キャスターとかかわることどもについては、まだまだほりさげたいところもある。しかし、気がついたら、これだけであたえられた紙幅を、半分ぐらいつかってしまった。ひとつのことにこだわりぬく著者の書きっぷりが、私にものりうつったようである。未練はあるが、この問題はほどほどにしておこう。
全体をとおして感じたのだが、著者には、けっこう雄々しいところがある。
たとえば、自分に部下ができたらどうするかを論じたところへ、目をむけてみよう。著者は「舐(な)められてはいけない」と、まず自分に言いきかせるらしい。有能な上司であることより、「ただひたすら舐められないことを最優先に考える」という(二四頁)。
少々部下にからかわれてもいい、したしまれる上司でありたい。そう考える私なんかとは、心のかまえようがちがっている。蒸気機関車のような人柄を良しとするところからも、そのマッチョぶりはうかがえる。
ただ、この男らしさには、傷つきやすさの裏がえしめいた一面も、ありそうだ。



















