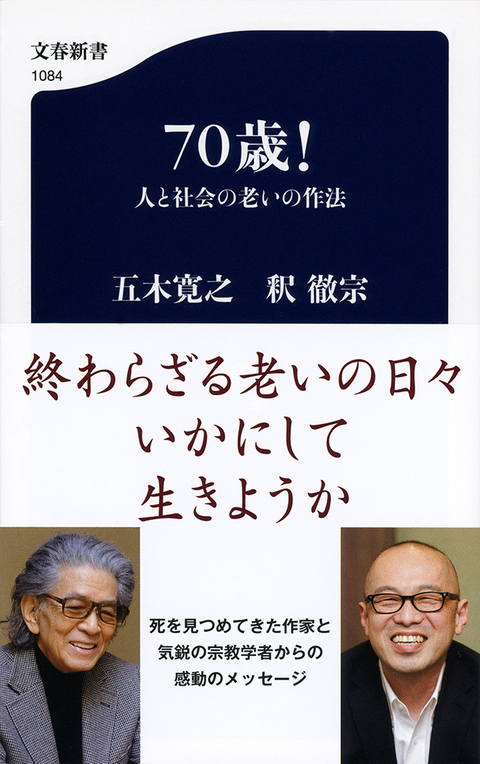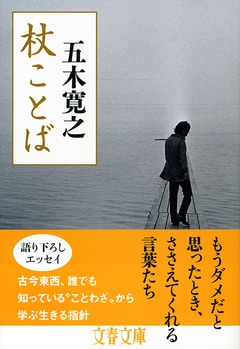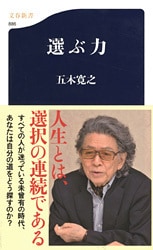それほど「死」は、明治以来、この国に充満していたのだ。敗戦によって、その空気は一挙に吹きはらわれた。そして「生きる」ことをひたすら追求して七十年が過ぎた。
いま、声にならない声、音としてはきこえない音が静かに迫ってくる感じを受けるのは、私だけだろうか。見えない津波のように押し寄せてくるのは、「死」という現実である。
私たちはいま再び「死」を意識しはじめている。それは、お国のためでもなく、世界のためでもない自分自身のための死の確認ではあるまいか。「われ一人のため」の死。
死後の世界は、だれも語ることができない。そこへ行って再び生の世界へもどってきた者がいないからである。ブッダは死後について口をとざしかたろうとしなかった。「無記」という表現でそのことは伝えられている。しかし世界は常に見る者によって見られる者が存在する。「生」が「死」を前提にしてあることは自明の理だ。すなわち私たちは死に対してさまざまな想像力を働かせることによって、現実の生をいきいきと実感できるのである。
釈さんは「死」を語るために「死後」の世界に踏みこむのではない。私たちの現実がより切実に、より深味をますために、反対側の世界を語ろうとするのだろう。
この対話の中の釈徹宗さんは、まさに私が子供の頃に夢見た孫悟空のイメージそのものだった。仏教に関する思索が、ときには落語の世界に飛び、ときにはアジアの民の現実に触れ、ときには枕経を読むエピソードとなり、縦横無尽にキン斗雲(キン=角へんに力)に乗って飛翔するさまは、私にとってまさに未体験ゾーンにいざなわれる実感があった。
私はこの対話の中で、何度となく不謹慎な表現や言い回しをしている。しかし、それは本当のことを言わない、言わせない世界への苛立ちのなせるわざである。若い釈さんが老人の短気を自在になだめすかしてくださったからこそ、この対談は成ったとあらためて思う。私たちは今、新しい旅立ちの前夜を迎えているのだ。この一冊が、そのスタートの合図になれば、と心から願っている。