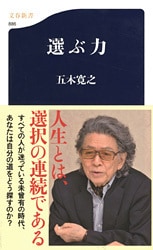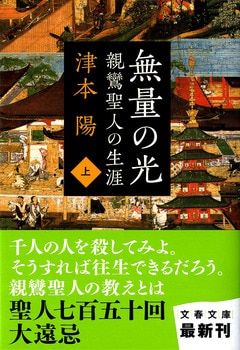この『金沢あかり坂』と名付けられた短篇集を読みつつ、ある一つの奇妙な感慨にとらわれずにはいられなかった。それは金沢という都市は何かしら文学者の胸奥に潜む情熱をかき立ててやまない、蠱惑(こわく)的とでも呼ぶべき呪力を秘めているのではないか、という想いである。こうした想いを具体的に証明するものとして私は例えば『石川近代文学全集 全十九巻 別巻一』(昭62・7~平10・12)という特異な全集をあげざるを得ない。もちろん、ここに収録された作品の舞台は石川県全域にわたっているが、その多くは金沢を中心とする作品なのである。編集・刊行にあたったのは金沢に設立されている石川近代文学館の関係者であり、もちろんこの全集は金沢で刊行されている。こうした文学全集は『北海道文学全集 全二十二巻 別巻一』(昭54・12~昭56・11 立風書房)を例外として、他府県にはあり得ないのではないか。寡聞にして私は他の例を知らないが、ともかくも石川県とくに金沢という都市は文学者を魅了して作品を生み出させる力を秘めているだけでなく、その作品の多くはその土地に住む人々の胸に大きく響き渡っているようなのである。
この中でも金沢という都市に生まれ育った文学者にとってこの土地はそのまま彼らの文学風土と化している。中でも泉鏡花、徳田秋声、室生犀星の三人は最も著名であり、それぞれこの地に根差した固有のすぐれた作品を生んでいる。しかし一方ではこの金沢を郷里としているわけでもない作家たちもこの土地に魅入られたかのような作品を数多く執筆しているのである。例えば先述した『石川近代文学全集』の第十巻(昭62・11)には曽野綾子(昭6生)、五木寛之(昭7生)、古井由吉(昭12生)の三作家の作品が収録されているが、彼らは皆いちようにこの土地の生まれではない。例えば曽野綾子は昭和二十年に一年足らず金沢に疎開したに過ぎないし、古井由吉も昭和三十七年四月から昭和四十年三月まで金沢大学に勤務していただけの関係なのである。にもかかわらず、この二人にとって金沢という都市は後に小説に書かざるを得ないほどの不思議な魅力を秘めていたようである。そして、この二人と同じように五木寛之もまたこの金沢とはある時期までほとんど無関係であった。
周知のように五木寛之は福岡県八女市に生まれているが、直後に父が朝鮮半島に教師として赴任したため、家族と共に半島に渡っている。昭和二十二年に帰国し、八女市で高校卒業まで暮しているが、昭和二十七年早大露文科へ入学してからは東京での生活が始まっている。この東京での生活は特に大学中退後波瀾をきわめ、様ざまな職業を転々とせざるを得なかったようである。そうした疾風怒濤(シユトルムウントドランク)とでも言うべき青春の終焉を自ら宣言し、昭和四十年彼は金沢への移住を決意したらしい。エッセイなどによれば彼はそれまでかかわっていた放送の世界からの離脱を誓い、文学に専念するために金沢への転居を実行したようである。この点では彼の金沢との関係は先の曽野や古井とはいささか異なっているようだが、文学的自立をかけた土地が金沢である必然性はどこにあったのか。