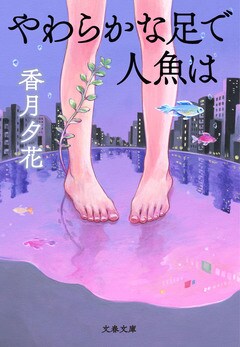沖縄の離島、久高島は人口約260人。周囲8キロほどの細長い島である。この島にも過疎化の波が押し寄せ、中学生がわずか2名という状況になり、学校の統廃合の不安も広がる中、2001年に「久高島留学センター」が開設された。
全国各地から15名ほどの子供たちが集まり、共同生活をし、島の人々と交流しながら人間として変化、成長していく姿が本書には描かれている。
留学センターにやってくる子供たちのほとんどが不登校。しかし、その9割以上が回復しているという。
2006年から現在まで6年間、この留学センターに通い続けた奥野修司さんは、子供たちがこれまでの生活から脱皮し、劇的に変化していく姿に寄り添い、克明に記録している。そうした一人ひとりのドラマに感動し、読んでいて思わず引き込まれた。
この留学センターを開設したのは坂本清治さんである。1960年に横浜で生まれた坂本さんは、青年時代に日本の食糧問題についての危機感から琉球大学農学部に進学する。学生時代には1年間休学して全国の過疎地を歩いている。卒業論文は「帰農試論」。さらにインドへの旅も含め、資本主義社会の次に来るオルタナティブ社会を担う次世代を育てる仕事をしたいという夢を抱いていた。学習塾経営、山村留学、そして鳥山敏子さんの「賢治の学校」のスタッフなどの経験を積んだ後、久高島にたどりつく。
留学センター開設の翌年、沖縄大学に赴任したぼくは、坂本さんに社会臨床学会のシンポジストや、大学でのゲスト講演をお願いしたりした。その時、坂本さんがE・フロムの「自由からの逃走」について熱っぽく語っていたのを今も忘れない。
留学センターには3人のスタッフがいる。内村珠子さん(タマちゃん)はお母さん役。坂田竜二さんは世界のトライアスロンレースで優勝した経験もあるスポーツマン。大曽根明子さんは世界各地を歩き、さまざまな体験を積んできた。さまざまな問題を抱えた子供たちと向き合い、気の抜けない日々であったと思う。
ある時、内村さんの母親が倒れて仕事ができなくなったため、富田美代子さん(トミー)がスタッフとして加わった。ところが彼女が海での指導中に溺死するという大きな悲劇が起こってしまった。トミーはまだ25歳という若さであった。
深い悲しみの中、島の人々は坂本さんやスタッフを支え続けた。一時は留学センターを閉じることも考えていた坂本さんは続けることを決意し、昨年、10周年を迎えることができた。
現在、タマちゃんは民宿を経営し、坂田さんと大曽根さんは結婚して渡嘉敷島で山村留学「わらびや」を経営している。
久高島は「イザイホー」などの神行事でも有名なのだが、島にはコンビニもスーパーもない。子供たちの好きなゲームセンターもない。したがって、ゲームやテレビから子供たちは自然に遠ざかっていく。
そして仮想の世界よりも現実の世界、とくに身体で感じる世界の楽しさを知っていく。追い込み漁や海への飛び込みに夢中になり、年中行事の祭りや島内3000メートル走にもはまっていく。野菜や魚中心の食事にも慣れ、肥満体形の子がスリムな若者に変身していく。
島の人々は、留学センターの子も自分の子や孫のように声をかけ、家に誘う。島ぐるみ地域ぐるみで子育てをしてきた伝統と文化が今も色濃く残っている。
センター内の関係も「友達以上兄弟未満」と言われているが、いったん実家に帰ったまま島に戻れない仲間がいると、休暇をつかって会いに行き、島に連れ戻したりしている。問題を共有し、ともに苦しみ悩む。そして一緒に支えあう関係が生まれてきている。
「子供の問題行動は親へのメッセージ。親がそれを受け止めて学習し、変わらなければ、問題行動は繰り返される」と坂本さんは言う。
久高島には土地共有制があり、16歳を超えると島民は誰でも平等に一定の土地が与えられることになっている。留学センターはこうした久高島の文化を背景として、現代版「若衆組」としての重要な役割を果たしているようにみえる。
ぼくは奥野さんとはかつて日雇い労働者の街・寿町で一緒に活動したことがある。ドヤ街の人々と親しく語っていた奥野さんが、留学センターの子供たちや島の人々とも語り合っていることが本書から伝わってきて、嬉しかった。
本書には混迷の時代を切り開いていく視点がちりばめられていると実感した。








![[第8回 高校生直木賞全国大会レポート]四時間かけた議論の末“同票”で史上初の二作受賞](https://b-bunshun.ismcdn.jp/mwimgs/8/e/480wm/img_8ecbfa907f82de0fc58fac5476017aaf219466.jpg)