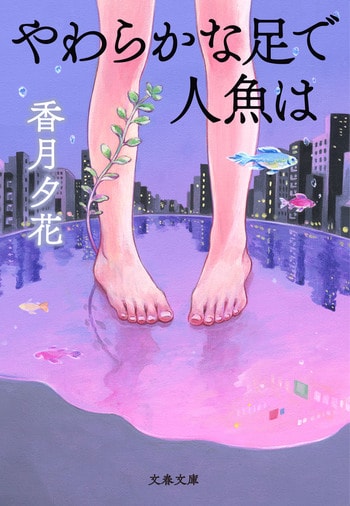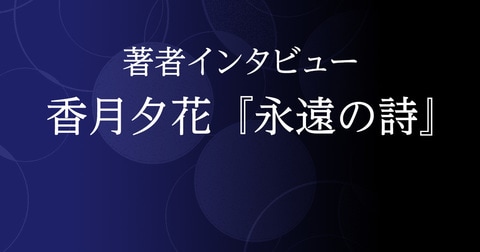誰にでも悲しみはある。しかし、その悲しみを他人に伝えるのは難しい。言葉にしたとたん、悲しみは嘘っぽくなってしまうし、語られた相手がきちんと悲しみを受けとめてくれるかも分からない。
いつしか悲しみは、心のなかにたまってゆき、行き場をなくしてしまう。
香月夕花は、この悲しみという厄介(やっかい)な感情になんとか言葉を与えようとしている作家である。
「逃げてゆく緑の男」は、電話詐欺の真似事をする若者が主人公。女友達にそそのかされるようにして、ある時、思い立って六十二歳の女性に、息子と称して電話を掛けてみる。意外なことに女性は、電話に応じ、子供を叱る母親のように冷ややかに答える。
「破産でも破滅でも勝手にすればいいわ。言っておくけど、こっちには一切持ち込まないでよ。あたしは知らないからね、お前がどうなろうと」
冷たく拒絶された若者は、そのあと「母親」のことが気になり、何度も偽電話をするようになる。そのつど「母親」に「毎日毎日、ご苦労さまだこと」「なんど話しても無駄よ」と軽くあしらわれる。
無論、この「母親」は電話を掛けてくる若者が「偽息子」だとは知っている。若者はそのことを知っている。その二人のあいだで、電話での会話が続いてゆく。
二人を会話へと結びつけているものは何なのだろう。お互いに寂しいから。それぞれ心に屈託を抱えていて誰かに話を聞いてもらいたいから。偽物の母親と偽物の息子による会話が芝居のようで面白かったから。
理由はいろいろ考えられるが、二人がそれぞれに悲しみを抱えていたことが後半になって分かってくる。若者は、両親が離婚していてどちらともうまくいっていない。女性のほうは、老いた母親をもてあましていた。
二人は人にはいえない悲しみを抱えていた。
その悲しみを、普段、他人に素直には語れない。「偽電話」という嘘の会話だから、悲しみを伝えられるのではないか。「嘘でしか言えない真実」というものがある。大都会で生きている十九歳の若者と六十二歳の女性。見知らぬ二人が嘘によって結びついている。そしてもしかしたら二人の「悲しみ」も「偽」なのかもしれない。そこに現代の孤独の深さがある。この短篇の怖さがある。
「逃げてゆく緑の男」に比べると「水風船の壊れる朝に」は、素直に人の心の悲しみを語っている。
海の見える町に、ある時、家探しに若い女性がやってくる。そして売りに出されている古い住宅を買い取るばかりか、その家が営んでいた生花店を自分でも始めたいという。
家を売ることになった女性は、この来訪者に反発する。金に余裕があるようだし、はじめての町でいきなり店をやろうとする無鉄砲が傲慢にも見える。
しかし、徐々に分かってくる。この来訪者には、人に言いたくない過去があった。ヘリコプターを操縦していて墜落事故を起した。同乗していた父親が死んだ。この父親は詐欺まがいの悪徳商法で金儲けをしていた。そのために、事故は誰の同情も呼ばなかった。むしろ「世間は満場の拍手で迎えた」。