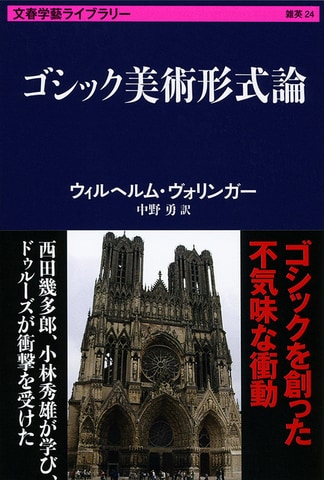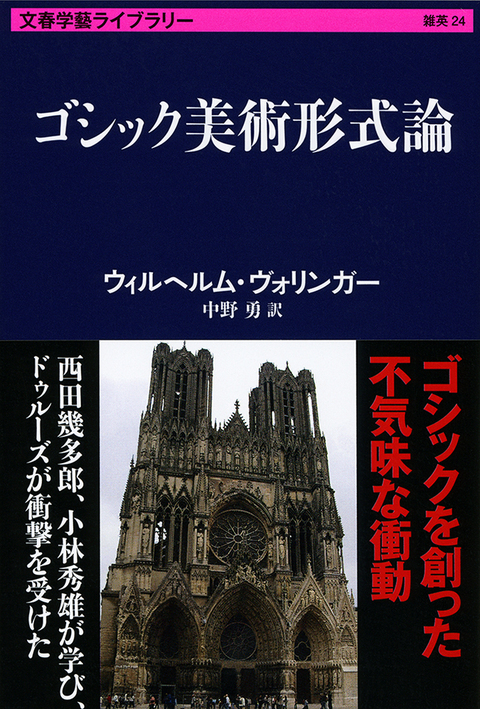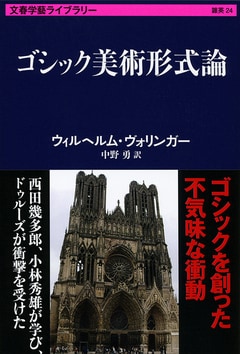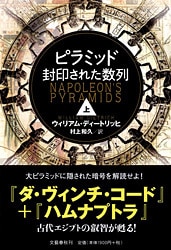ヨーロッパ中世に花開き、大聖堂で頂点を極めた「ゴシック美術」はどのように産み出されたのか? ドイツを代表する美術史家が、芸術を創造する人類の根本的衝動にまで遡り、ゴシックの内奥に潜む情念を鮮やかに描き出した歴史的名著の解説より、その一部を2度に分けて公開する。
抽象美術のマニフェスト
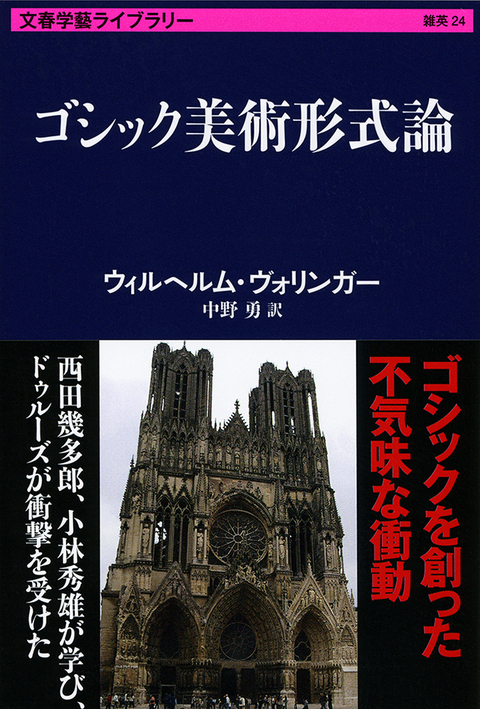
本書『ゴシック美術形式論』は、美術史家ウィルヘルム・ヴォリンガーが一九一一年に刊行したFormprobleme der Gotik(直訳すると『ゴシックの形式問題』)の日本語訳である。本訳書は、一九四四年に座右宝刊行会から中野勇訳で刊行された後、一九六八年に岩崎美術社の「美術名著選書 7」として阿部公正による校訂を経て刊行された版を底本としている。
一八八一年にドイツのアーヘンで生まれ、一九六五年にミュンヘンで亡くなったヴォリンガーは、主として博士論文の『抽象と感情移入』(一九〇八)[1]と本書によって知られている。いずれも専門的な美術書としては例外的なまでに広範な読者を獲得し、版を重ねた。その理由としては、文章そのものの魅力に加えて、刊行当時勃興しつつあった同時代美術の動きと呼応し、実作者の支持を得たことが挙げられよう。
『抽象と感情移入』がもっぱら古代エジプトやビザンチンなどの美術を扱い、『ゴシック美術形式論』が中世美術を扱っているにもかかわらず、両書は二〇世紀のドイツ表現主義の理論的支柱となり、また広く抽象美術のマニフェストとみなされたのである。このことは一見奇妙な事態であるが、ヴォリンガーの一貫した関心が「古典美術」や広義の「自然主義」の判断基準では正当に扱うことができない対象に向けられていたことを考えれば納得がいく。第一次世界大戦前夜という刊行のタイミング、そして詩人のパウル・エルンストが『抽象と感情移入』を一般書と誤解し、書評で広く芸術愛好家に紹介したこと[2]などの好機に恵まれた『抽象と感情移入』、そしてその双対とみることができる『ゴシック美術形式論』は、喧騒と混沌に満ちた二〇世紀文化史における重要なマイルストーンとなっているのだ。