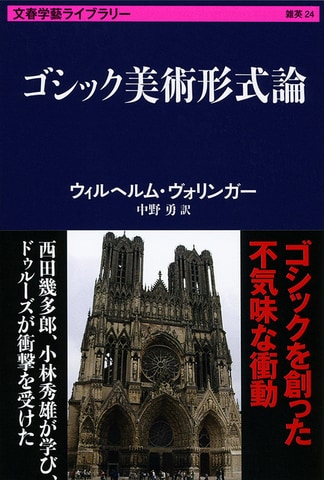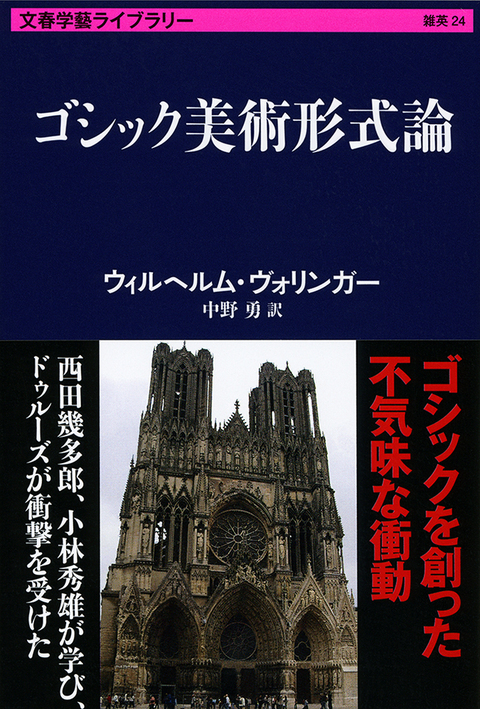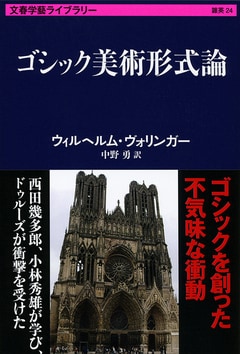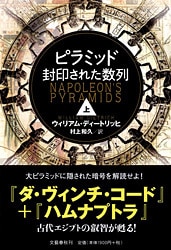ヴォリンガーは何に異議を唱えていたのか
ヴォリンガーの問題関心は、先行するドイツ語圏の美学・美術史学者たちの学説を、独自の仕方で先鋭化させつつ組み合わせていくことにあった。より具体的に言えば、ウィーンの美術史学者アロイス・リーグルの著作『様式の問い』[3]および『末期ローマの美術工芸』[4]から受けた示唆をもとに、テオドール・リップスの心理学的美学における「感情移入 Einfühlung」説を批判的に検討しつつ、主としてアルプス以北の「北方芸術」の独自性を探っていった。
欧州において規範化された「古典美術」とは、古代ギリシア・ローマ美術を範とするイタリア・ルネサンス以後の伝統を指し示す。「北方芸術」との対比でいうなら「南方芸術」にあたり、より具体的には地中海沿岸地域の芸術ということになるだろう。例えば、ルーヴル美術館が所蔵する《ミロのヴィーナス》(ギリシア・ローマ)および《モナ・リザ》(ルネサンス)が、現在でもしばしば「美の殿堂」を形成するものとして「西洋美術」そのもののシンボルとされていることは、この強力な伝統が健在であることを物語る。
他方、ルネサンス期に確立された物体・空間描写(人体デッサンと遠近法)を徐々に退けていったフランス印象派以降の近代美術においても、視覚印象の再現という形での広義の「自然主義」は、美を判断する一つの基準であり続けた。現在でもなお「絵が上手い」かどうかの基準は、対象の模倣的再現の巧みさに置かれる傾向が強く、「デッサン力」という言葉の内実はそのことを示している。
リーグルやヴォリンガーは、このような判断基準があらゆる芸術に適用されることに対して異議を唱えた。なぜなら、そのような判断基準は、原始美術や東洋美術などの所産が、発展段階において劣り、いまだ美に到達していないとみなす偏見を伴うことが多かったためである。リーグルの著作が「装飾文様」(『様式の問い』)「末期ローマ芸術」(『末期ローマの美術工芸』)、そして『オランダ集団肖像画』[5]といった、古典美の基準からみて逸脱的に映る対象に新たな光をあて続けたのは、そうした偏見を打破するためであった。
リーグルの美術史的著作を導く重要概念に「芸術意志(あるいは芸術意欲)Kunstwollen」がある。この概念は、写実性を目指していない芸術様式について、単に写実の「能力 Können」が欠如している(例えば「デッサン力がない」という言い回しがしばしば示すように)のではなく、写実性とは異なる「意志 Wollen」が見出されることを示すために導入された。他方ヴォリンガーの著作は、リーグルの成果を受け継ぎ、さらに「感情移入」を美の基準とみなす心理学的美学を批判的に分析しつつ、新たな対抗理論を打ち出すことにその眼目があった。