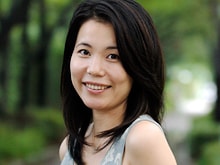「ぴろり」
修善寺を訪ねた主人公の女性が葬儀屋の男に声をかけられ、彼の会社のマイクロバスで街をドライブする。この短篇に関しては多くは語らないほうがよいだろう。一行目から違和感を抱かせるので彼らの事情にすぐ気づく読者もいるはずだ。秀逸なのは視点人物を、決着を付けなければいけない側にして他者視点の安っぽいセンチメンタリズムを排除したことと、途中で彼らの事情に気づいたとしても最後までしみじみと読ませる筆力だ。
「ラストシーン」
飛行機内での会話で進行していく一幕劇。周囲が次々と口を挟んでくる様子が楽しい滑稽譚と思わせて、最後にいきなりぐっと深い話になる。登場する映画を観たくなる人が続出すると思われるので一応書いておくと、ここではみな英語で話している設定なので映画タイトルを原題の直訳である『検察側の証人』(小説・戯曲の邦題もこちら)としているが、映画の邦題は『情婦』だ。
「桂川里香子、危機一髪」
タイトルから分かる通り、コミカルな一篇。バイタリティあふれる五十代女性の、若かりし頃の新幹線にまつわる苦い思い出とは? 駅のホームで彼女が体験したやりとりに一緒になって苛立ち、最後の彼女の行動(映像で想像するとかなり笑える)に快哉を叫んだ人は多いだろう。その後彼女がどうなったのかを含めて、とにかく痛快!
「母の北上」
父が死んでから、実家の母の拠点がリビングの南側から少しずつ移動して、今では北側の小さな部屋になっている。長男はその理由を父の不在にあると思っているのだが、果たして……。こちらも、視点人物の目を通して見える景色が途中でガラリと変わっていく。先入観で人を決めつけることの浅はかさが、クスクス笑いをともなって提示される。
「異国のおじさんを伴う」
奇妙な招待を受けてオーストリアへ旅立った作家の〈私〉。目的地まで迷いまくった挙句、勘違いで恥をかいたり歓待を受けたり、やっかいなお土産をもらったり……。心が振り乱されっぱなしの行程でふと立ち止まって考えた時、彼女は作家としての自分の現状について最悪の結論に辿りついてしまう。彼女が導き出した日常と精神と小説の関係について、必ずしもそうだとは言えないだろう。ここでは彼女が真実に辿りついたわけではなく、そうした結論に辿りついてしまうほど彼女が行き詰っていることが示されるのだ。そこからの一歩を予感させるラストに光が見える。
どの短篇も登場人物がなんらかのことに「気づく」様子が描かれている。なんでもない、あるいは少しだけ異質な日常の瞬間が描かれているようでいて、そこに潜むのは大きな心の動きなのである。人生にはそういう刹那があることを、きっと私もあなたも知っている。だから、森さんが描き出す光景は、読み手の心を揺さぶる力があるのだ。
すべての短篇に当てはまるわけではないが、『架空の球を追う』が日常の微笑ましい瞬間を描いた作品集で、本書が人々の心が動いた刹那を丁寧に掬ったものだとすると、第三弾『漁師の愛人』の表題作と「あの日以降」の二作は、心が動いた後の日々を丁寧に追った中篇と言えそう(他の三篇はプリンが重要な役割を担っている〈プリン三部作〉で、こちらも傑作)。その時々によって、著者の作家としての興味のベクトルの変化が作品に表れているようで興味をそそられる。『オール讀物』での短篇執筆はもちろんまだ続いており、今後書籍も第四弾以降続いていく予定だ。著者のベクトルがどのように変化をしていくのか、楽しみで仕方ない。