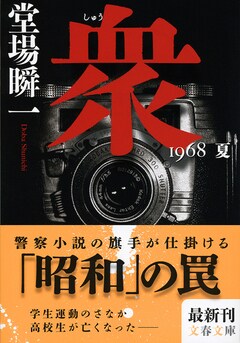私立探偵という言葉から、アナタは何歳くらいの人物を思い浮かべるだろう。
恐らく、多くの人が“四〇歳前後の男性”と答えるのではないか。
なるほど、他人の内情を探り出すような仕事には人を観る目が大切。勘の鋭さや臨機応変さも問われる。それにはある程度の人生経験がないとダメだし、そのいっぽうで尾行や張り込み等を考えると体力もないと務まらない。女性にはちょっとキツそうだし、あれこれ鑑みると、アラフォー世代の男の顔が浮かんでくる。
実際、明智小五郎や金田一耕助はデビュー時は二〇代だったが、三〇代から四〇代にかけて脂がのってくる。同じ探偵でも、ハードボイルド探偵のほうがアラフォー指向は顕著で、結城昌治が生んだ真木探偵や原尞の沢崎探偵はその典型例だ。海外作品を見ても、ダシール・ハメットのサム・スペードも、チャンドラーのフィリップ・マーロウ、ロス・マクドナルドのリュウ・アーチャーもデビュー時三〇代で、そこから作品を重ねていく。
もっとも中には例外もあって、大沢在昌が生んだ青年探偵・佐久間公はハードボイルド探偵のアラフォー指向を逆手にとって注目された。その逆に、もう人生も引退していいんじゃないと突っ込みを入れたくなるような老いぼれ探偵も存在する。L・A・モース『オールド・ディック』のジェイク・スパナーは格好の例だが、七八歳という彼の最高齢記録は、ダニエル・フリードマン『もう年はとれない』に登場したバック・シャッツによって更新された(御年八七歳!)。
藤田宜永が生んだ探偵・竹花は登場時四二歳。孤独を愛するストイックな中年男だったが、その後著者が仕事の軸を恋愛小説のほうに移していき、シリーズは中断された。このまま恋愛小説作家として人生をまっとうしてしまうのか――そんな思いが脳裏をよぎり始めたときしかし、著者は一八年ぶりに作家の出発点となったハードボイルド私立探偵小説の世界に戻ってきたのである。
探偵・竹花復活の第一歩は書き下ろし長篇『再会の街』(ハルキ文庫)――と思っている人も多いと思うが、実は短篇作品のほうでひと足先にカムバックしていた。本書『孤独の絆』はそのカムバック短篇「サンライズ・サンセット」の他三篇を収めた連作集である。二〇一三年二月、文藝春秋から刊行された。
あらかじめ竹花のプロフィールを紹介しておくと、一九五〇年生まれ(著者と同い年!)で両親は早くに他界、兄弟も妻子もなく、天涯孤独の身だ。高校時代は哲学研究会に在籍、大学を出た後探偵事務所に勤めるが、やがて独立。当初は探偵マニアの不動産会社社長がパトロンにつき、恵比寿駅前に事務所を構えていたが、その後社長は脱税で失脚、竹花も旧防衛庁技術研究所に程近い恵比寿南二丁目に転居、さらに二〇〇〇年代半ばに麻布十番商店街の外れにある「ボロマンション」に引っ越し、現在に至る。愛車は往年の名車スカイライン二〇〇〇GT(の改造車)で、たびたび元暴走族の疑いをかけられる。喫煙家で、ジャズの愛聴者。