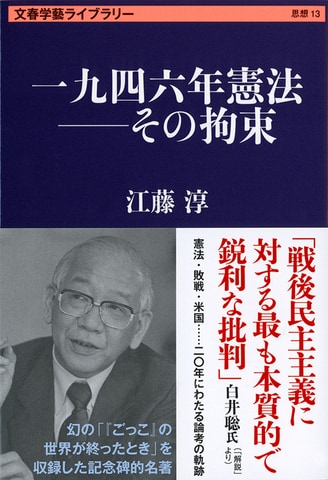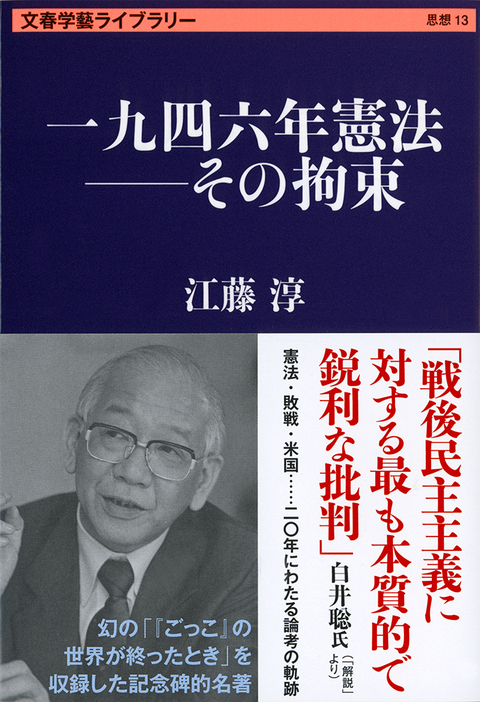江藤淳の遺した仕事のうち、本書に収められた戦後憲法批判ならびに占領期検閲の研究が持つ意味は、今日ますます高まっている。それはもちろん、敗戦以来の日本の特殊な対米従属姿勢によって根本的に規定されたレジームが、冷戦構造の崩壊と同時にその存立根拠を失ったにもかかわらず、現在に至るまで無限延長され、それによる歪みがここかしこに噴出する危機的な事態が今日生じているからである。
例えば、安倍晋三総理は「戦後レジームからの脱却」を絶叫しているが、このスローガンはこうした事態に対する応答であると言葉の上では見える。しかし、その具体的内容たるや、一方では対米従属のさらなる深化――安倍は米国からの二〇年来の要求である集団的自衛権の行使容認を請け合い、「アメリカの戦争」を自衛隊がお手伝いする義務を引き受けた――を追求するものでしかない。他方、いよいよ自民党は党の悲願たる憲法改正(自主憲法制定)に突き進もうとしているが、提示された草案は、戦後憲法の柱たる基本的人権の尊重や民主主義の原則を後退させようとする意図を濃厚に感じさせる時代錯誤も甚だしい代物であり、これに対しては年来改憲賛成の立場を取ってきた識者からさえも、強い批判と疑義が発せられている。つまり、「自主憲法」なるものは、あの「占領改革」の「成果」を単純に否定するものであるとしか見えないのである。
ここに、戦後日本の主流派ナショナリズム(すなわち、「親米保守」派によるナショナリズム)の支離滅裂、外国のプレゼンスによってナショナリズムを支えてもらうというそのグロテスクな在り方が内包する精神の分裂が、はっきりと現れている。彼らは、敗戦の帰結としての戦後民主主義を否定して大日本帝国の亡霊を呼び出すことに熱中する一方で、同じく敗戦の帰結である対米従属をあらゆる犠牲を払ってまで永遠化しようとする。
かつ、この分裂は、権力中枢だけでなく、3・11、特に福島第一原子力発電所の事故によって突きつけられた「平和と繁栄」の時代としての戦後の終わりという時代感覚が喚起する不安の感情と、悪い意味で共鳴している。例えば、街頭での人種差別的ヘイトスピーチの横行は、戦後改革によってもたらされた基本的人権の尊重の実践的否定である。あるいは、東京都議会という公的空間で女性の人権が毀損されるような発言が実質的に許容される事態は、男女同権というこれまた戦後改革がもたらしたものに対する否定である。なるほど、こうした動きを支持する人々が、敗戦によって持ち込まれ押し付けられた戦後民主主義など全否定されるべきだと言いたいのなら、それはそれでひとつの考え方ではある。だが、そのような立場をとる勢力が、まさに敗戦の結果の象徴である外国軍の永続的駐留(米軍駐留)に対して非難・抗議の声を上げないばかりか、米軍駐留をめぐる長年の不平等な仕打ちに抗議する沖縄に対して、「中国共産党に操られた反日分子」などというピント外れのレッテル貼りをしているのは、完全に首尾一貫性を欠いており、その姿は病的である。