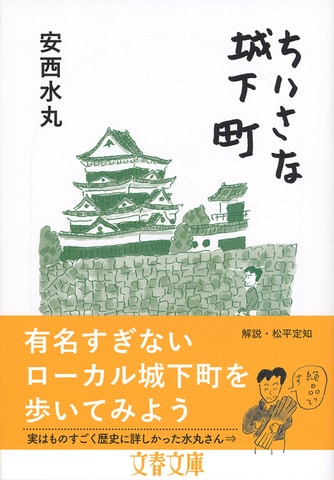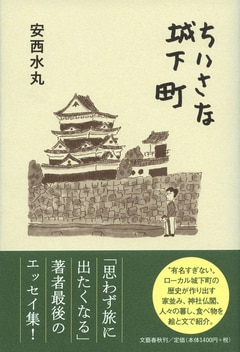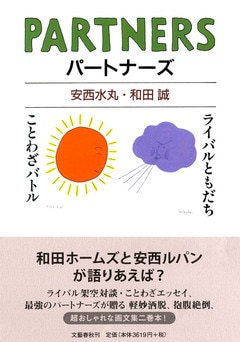安西さんが「いい」と仰ってくださった、前述の、NHKの「その時歴史が動いた」は2000年4月から(この年は正確には3月29日から)2009年3月までの丸9年間続いたが、この番組を制作するにあたってのコンセプトが三つあった。それは、『史料至上主義を排す』『敗者にも慮(おもんぱか)りを』『歴史を結果からみて論評しない』の三つだったが、最初にお目にかかった時、私がそのことをおずおずと切り出すと、安西さんは「あの番組が好きだったのは、それらのことが、きちんと私にも伝わってきたからです」と仰って下さった。以下は、例えば、そんなことについて、私たちが、お互い、ぼそぼそと、時間をゆっくりかけて話した概要である。
まず、『史料至上主義を排す』。
「そんなことは史料に残ってないから、ない!」「それは、あった。だって史料の文書にそう書いてあるから」――つまり、信じるモノは、あくまで「書かれて残っている」史料で、「書かれていないもの」は信じない――こういう傾向が「学校での歴史授業」を無味乾燥なものにしてはいまいか、というのが二人の最初の合意点だった。もちろん文書として残っている史料には最大限の敬意は払うけれども、たとえば、『山本勘助殿。これより、貴殿は速やかに上杉陣営に赴き、敵軍の武器弾薬の量を内偵し報告すること。永禄3年×月×日。武田信玄。花押』なんて文書(史料)は、そもそもが「密命」なのだから存在する筈はない。でも「史料」として存在はしなくても、「そうしたこと」が「あった」確率は高い。つまり「文書史料として残ってないから、なかった」とは言い切れないのだ。逆もまた同じで、例えば、信長公記、徳川実紀や太閤記といった「一族もの」の史料には、「オラが大将」を少しでも好印象で後世に伝えたいと、関係者が書き手に脚色を交えて書くよう命じた部分もあるだろうし、書き手が勝手に周囲を慮って、本来ないものを「ある」と書いた部分もあるに違いない。つまり、『書いてあるから、そうなのだ』と思いこむことも、正しくない。
「受け」狙いだけの、荒唐無稽な想像話は論外だけれども、「あったかもしれないこと」に関しては、もっと想像の翼を大きく広げて歴史を見る柔軟性を持つべき、というのが私たちの合意点「その1」だった。
次。『敗者にも慮りを』。
保元元年(1156)の「保元の乱」で勝ったのは後白河天皇方。その功労者は平清盛と源義朝だった。清盛も義朝も叔父や父を敵に回して一族入り乱れての戦いになったが、天皇側勝利への貢献度は、清盛・義朝、甲乙つけ難かった。それなのに、戦後の恩賞に著しい差が生じた。清盛は恩賞の一つ「播磨守」の役職で瀬戸内の航行利権を手にすることが出来、併せて拝受した大宰府における役職で、対宋貿易の権益もしっかり確保した。これらの「富(とみ)」が後の「平家政権」を支えもした。一方、義朝の恩賞は右馬権頭任官だった。この官は武士たる者の憧れの役職だったかもしれないが、「実利的」には、清盛とは『著しい差』である。3年後の平治の乱は、教科書的には後白河上皇の院政か二条天皇の親政かの争いで、それはそれで正しいのだが、底流には、この恩賞問題の遺恨があった(と思う)。戦(いくさ)に敗れ、頼朝、義経らの息子を残して、落ち延びる途中の知多半島で謀殺された義朝の「言い分」を聞いてみたい。敗者に思いを致すことで、「一つの事件」の様相は「従来のモノ」とは違ってくる可能性が高いというのが、合意点「その2」。