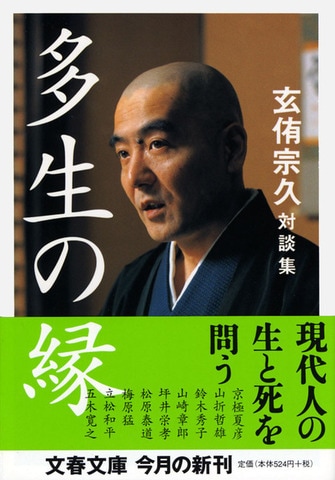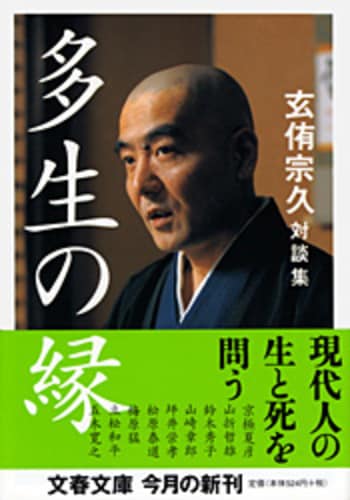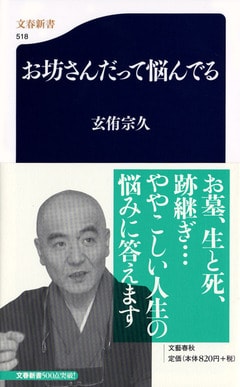――本書は、玄侑さんにとっての初めての対談集ということになります。そのタイトルの「多生の縁」という言葉には、何か特別な意味合いがこめられているのでしょうか。
玄侑 「多生の縁」というのは不思議な言葉で、文字通り「多くの生」を表しています。つまり輪廻(りんね)を前提としていて、前世とか、あるいはもっとその前の生の中のどこかで、今回この世で出遭うご縁ができたんだよ、ということです。そう言ってしまうと、おがみやさんの論理と一緒だし、単なる偶然でしかないと受け取ることもできるでしょう。
けれど、最近流行っているプロセス思考心理学などでも、たとえば嫌いな人との出遭いを何かの必然だといいます。それは、嫌いな人というのは自分の嫌な部分そのものを持っている、あるいは見せられてしまうから嫌いになるわけで、無自覚でも自身の中に在るものなんです。だから、その人から逃げても、自分の中に原因があるのだから、また同じような類の人間に出遭ってしまう=因果というものがあるわけですね。でも因果というものは、われわれの目に見える世界で起こるとは限らないし、むしろ、それはすべて目に見えないんだというのが、仏教的な因果の基本です。だから、見えないご縁のことを、「お蔭さまで」と「様」を付けて呼ぶんですね。今回お目にかかった方々とのご縁も、敢えて必然だと思うことで、深いものが生れてくるんじゃないかと思っています。
――九人のお相手は、それぞれ文学、宗教、哲学、医学などの分野で道を究めていらっしゃる方々ばかりですが、各々の宗派は、真宗であったり、キリスト教であったり、玄侑さんの臨済宗とは異なる場合もありましたね。

玄侑 普通の坊さんには、他の宗教の方との交流の機会はあまりないんですが、お蔭さまで(笑)、芥川賞の受賞以降、宗派にほとんど関係なく、いろいろな依頼をいただいています。キリスト教系の病院のガン病棟にいらっしゃる牧師さんが、わざわざ「日本人の末期のターミナルケアには仏教が必要だから、話をしに来てもらえないだろうか」とおっしゃってくれたこともありました。
意外に思われるかもしれませんが、キリスト教であっても、禅宗とつながっている部分というのはかなりあるんです。一番に似ていると思うのは、思考の範囲の外――瞑想という言葉にも置き換えられますけれど、そういったものを重視するところですね。カトリックを信仰されている鈴木秀子さんが、対談のために私のお寺に見えたときに、「黙識(もくしき)」と書かれた額を見て「私たちと一緒です」と感激されていましたが、神に会うときというのは、左脳が休止して、思考も完全にストップした状態なんです。なぜなら、神というのは思考の対象ではないわけですから。これはいわゆる禅的な悟りと同じだと思います。
――対談に登場する五木寛之さんや、梅原猛さんも、キリストならキリストだけ、アラーならアラーだけしか認めない価値観が、現代社会のさまざまな対立の原因を生んでいるとおっしゃっています。
玄侑 『ヨハネによる福音書』に「はじめにロゴスありき」という言葉がでてきますが、「ロゴス」と名づけられた時点で、それはもう知性がとらえる対象になり、比較することもできるようになっていますよね。たとえ同じものであったとしても名づけ方によって、アラーになったり、神になったりして区別され、細分化されていく運命にある。瞑想というのは、そういう思考の範疇外です。それがもっと重視されていけば、キリスト対イスラム、二つの世界の対立みたいなものも解消していくのではないでしょうか。
ただし、ものに名をつけることが出来ないと、何も考えられなくなってしまうわけで困ってしまう(笑)。そのときに、じゃあ何が穏当な名づけ方かになりますが、日本古来の「八百万(やおよろず)」っていう表現は非常に格好いい。クールです。ただし、日本人は宗教という考え方が欧米から渡来してきたときに、自分たちの考え方に自信を持てず、その良さというものを失っていってしまったのは、本当に残念です。
玄侑 先日の直木賞の受賞は本当に私も嬉しかったんですが、京極さんは「日本が好きです」と明言し、あんな風に日本を掘り下げてくれる、まさに仕事人ですよね。おどろおどろしいところもあるかもしれないけれど、目指しているものは同じ志向を感じます。結局、合理だけではとらえられない人間の深み、というものを京極さんは妖怪というもので表し、私は末期のビジョンで表したわけです。
どうしても説明のつかない不思議な出来事というのは、宇宙においても人体においてもたくさん起こります。そうした現象は、「心の問題」として起きる実感を、僧侶としても小説家としてもずっと持っていました。ただし、それは心だけではなく、身体も伴ったものなんです。今回の対談集では、日本医師会会長の坪井栄孝さんが、お医者様の立場から「理論だけでは、人間は解決出来ない。いくら遺伝子の研究が進んでも、まだまだ何百万分の一ぐらいしか人間のことなんて分からないでしょう」という認識を示してくれました。それは、とても有難いことだし、広く支持されていい考え方だと思います。お医者さんが統計をとった平均値で判断して、ある患者さんが余命数カ月、という状態であったとしても、その平均値というのは患者さんにとっては自分の数値ではないわけで、「自分においてだけは奇跡が起こるかもしれない」とみんなが思っているわけですからね。
――「生」あるいは「死」ということについては、ほとんどの対談でかなり深いところまで掘り下げていますね。
玄侑 私自身が「死」というものを小説のテーマにしていることもあるのでしょうが、最近は「死」というものが、まともに話されるようになってきた気がしています。そうした話題がこれまでは、忌み嫌われてきたというより、不必要とされていたんでしょう。死後については「無」という考え方が一般的でしたからね。しかし、その「無」というのは違うのではないか、そうした考え方が医学側からも、宗教側からも起こっている感じがするんです。
ある人が「時代の先を行き過ぎているものは芥川賞にならない。まもなく時代が追いついてくる、そういうものが結果的には芥川賞をもらっている」とおっしゃったことがあるんですが、近頃、私の『中陰の花』もそうだったのかもしれないという気がしてきました。目に見えない世界、合理で説明がつかない世界のことが、知的な会話の中でも割と普通にされるようになってきたんじゃないか、そう私は思っているのですが……。
――ただ、若者同士で以前なら頻繁に語られていた、たとえば「愛」や「正義」といったテーマ。そういったものが真摯に語り合われる機会が、現代には失われていないでしょうか。
玄侑 確かに『三太郎の日記』といったものを読み、人間いかに生きるべきか、といったことを徹夜で語り明かすような雰囲気は、昔はありましたが、最近はそうではないのかもしれません。けれど、そうした青春の悩みというものは、インターネットの掲示板なんかが流行っていて、代わりになっているところがあるように思います。私のホームページにもたくさんのメールが寄せられてきますしね。
徹夜でどうこうする、といったことは今はもうスマートではないんでしょう。熱くなるタイプは逆に生き辛かったりする。濃密な関わりが現実の中ではできないのは、まあ、時代といえば時代と言うしかないのかもしれません。
みんな誰かに認めてほしい
――玄侑さんは小説以外にも、仏教を扱ったご本で、さまざまな悩みや迷いをかかえている読者の方々に強い影響を与えていらっしゃると思います。
玄侑 人は他人に何かを言われても、すぐに変われるものではないんです。その人達が望んでいることは「そのままでいいんじゃないの?」って言ってもらうことなんです。だから「そのままでいいんじゃないの」って認めてもらえる価値観というものを、非常に歓迎するのではないでしょうか。岡倉天心も『茶の本』のなかで言っているんですが、私は禅というものは極めて個人的なものだと思うんです。正しさ、というものを認めない老荘思想の上に乗り、あれもあり、これもあり――誰にでも通用する真理というのはないんだ、と心の底から思っています。よっぽどのことでない限りそれぞれの生き方があるでしょうし、八百万的に認めてしまうので、そういう考え方が読者の方々には喜ばれているんでしょう。
つまり、私の今までの人生これでよかったんだ、って周りに言ってほしい人が大勢いるんですね。「頑張っているね」「よくやっているね」って、誰にも言われないと自分で言いたくなるでしょう。それは不幸のはじまりで、みんな誰かに認めてほしいと心の底では思っていることは、よく感じます。まあ、坐禅なしで伝授、というのもいいんでしょうね。坐禅つきではどうでしょう?(笑)でも、今まで私の読者の中心ではなかった三十代の男性がメールをくれたり、感想を手紙でくれたりもしています。
――ご自身の中では、かつて僧侶になる以前にさまざまな職業に就かれ、そこでは迷いもあったと伺いました。そうした状態から「いまの自分でいいんだ」と思えるようになったきっかけは、あったのでしょうか。
玄侑 やっぱり禅との出会いであり、修行道場での体験なんだと思います。ただ、もっと単純に考えると、たとえば外を見ていても、メジロがいて、スズメがいて、ヒヨドリがいて、餌を色々食べにくるわけですが、今頃は冬眠しているケモノもいるわけですよ。こんな寒いのに餌集めをしなければいけない生き方もあるわけですが、かといって冬眠している動物を責めることは出来ないわけで、そういう生き方もありますよね。人間の中にも冬眠しているような人だっています(笑)。そういう色んな場面を見ていたら、こちらが正しくて、こちらは間違っているなんていうことはどんどん言えなくなってきます。
――それが、仏教における「慈悲」という考え方ですか。
玄侑 基本的に「慈悲」というのは、誤解されるかもしれませんが、ある心の状態になるときに、生理的に発散されるものだと思うんですよ。太陽に当ったら暖かい、といったようなもので、あくまでもロジカルで思索的なものではないと思いますし、その発散は誰にでもできるんですが、ただ、時として「自己」というものがそれを邪魔しているような気はします。ただ、その自己っていうものをフィクションだと私は思っています。もし、自己というフィクションが人間から取っ払われれば、色んな現象が起こるんじゃないかと思うんですけれど……。
対談をした中で、五木さん、梅原さん、京極さんといった作家の方々が、特に日本の固有の文化をもう一度見つめなおしたい、というようなことをおっしゃっていました。それは、小説が明治以降に造られた近代的自我というフィクションを乗り越え、新しいものを生み出す時代にきたということかもしれません。
立松和平さんは、「小説は神通力で書く」という話をされていましたが、もともと人間が持っている能力が、すんなり出たものが、神通力です。だから、自我というか、自己というフィクションがあって、それを打ち破れば神通力というものを出せるんだと思いますね。
――次の小説も、どんなことを題材にされるのか楽しみです。
玄侑 いま書いているものは、共時性がテーマですね。シンクロニシティ、つまり同じ時間に、まったく別の場所で起こっていることが、実は何らかの形で関連し得るのではないか、ということをテーマにしたものです。情報伝達というのは、ある臨界点に達すると、口から口へという方法でなくても、離れたところに伝わることがあります。インフルエンザなんかでも、「あれは宇宙からとんでくるんだ」という人が未だにいますが、人から人への感染だけでは説明のつかない速度で広がっていくのも事実です。
多生の縁じゃないですけれども、われわれには見えない因果、あるいは因果律を補う世界観のひとつとして、シンクロニシティは重要なんではないかと思います。ある自殺をめぐるその現象を、初の長編小説として仕上げるつもりです。ただ坊さんの仕事も忙しくてね(笑)。
――今回の対談集『多生の縁』では、お坊さんとしての玄侑さんからも、たくさんの考えるヒントをいただきました。
玄侑 決して結論ではないですけれどね。でも、多分、読者の皆さんにとっても結論でなく、ヒントがいいんだと思います。「それとなく」という風に情報が入らないと、素直に飛びつけない、っていうところがあって。これが命令形でこられると、どんな正しいことでも嫌でしょう。だから、対談という形で、それとなさというものに溢れているのが、この本の良さかもしれないですね。