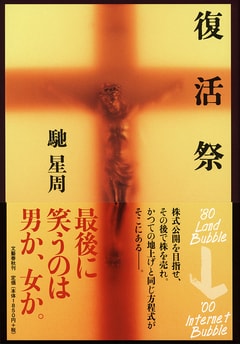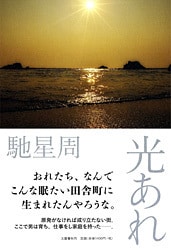一風変わった小説である。
“この物語は伝統的なやり方では語られない”とプロローグでこの物語の語り手であるディーン・ヒコックが語っているが、そのとおりだ。実際、物語の語り手が物語そのものに深く関わり、プロローグ以外はすべて三人称で描かれるというのは“伝統的な”語り方とは言えないだろう。また作中、語り手の声に加えて作者自身、もしかしたら神(?)の声さえ聞こえてきそうなくだりがあるが、それも通常の書き方とは言えまい。
こんなふうに紹介すると、作者その人が作中に登場したりするメタフィクション、難解なポストモダン文学を思い浮かべる方もおられるかもしれない。が、読めばすぐにわかるとおり、こむずかしさとはまったくもって無縁の小説だ。描かれているものはむしろいたって“伝統的”だ。真善美、そして愛。小説、ひいては芸術全般に古来不変のテーマである。それらがどこまでもどこまでもまっすぐに、率直に語られる。
中でも善。ギヴという犬の持つ善良さと同時に、人の持つ善意が描かれ、その尊さが作中繰り返し訴えられる。こう書くとまた誤解されるかもしれない。なんだ、説教小説かと。とんでもない。むしろ一度読みはじめたら止まらなくなること請(う)け合いの面白本だ。そして、なによりいい話だ。すがすがしくて温かい話だ。ギヴとともにはらはらどきどきしながらアメリカを旅した読者の多くが、心をぽっと温められて最後のページを繰られるはずである。
本書はギヴという名の犬を主人公に、その犬の旅を追うことを核とした物語だが、どんな物語なのかについては、あえてここではあらすじを省きたい。というのも、まったくさきが読めない話で、そこがまたこの本の面白さになっていると思うからだ。といって、もちろんそれはストーリーが荒唐無稽だからではない。むしろプロットのよくできた小説だ。アンナにまつわる最初のちょっとした逸話が最後のクライマックスで大いに意味を持ってくるところなど、ああ、そういうことだったのか、と多くの読者が納得されるはずである。これまた訳者として請け合っておこう。
また、本書はいわゆる“犬もの”だが、潔いほどに作者は犬を擬人化していない。あくまでも現実の犬が描かれている。擬人化なんかしなくても、犬というのはもともとちゃんと人と心を通わすことができる生きものなんだよ、と言わんばかりに。実際、等身大で描かれるギヴの可愛さ、健気(けなげ)さに自然と頬がゆるむくだり満載である。これとは逆に、モリソンという犬に関する逸話には思う存分涙していただきたい。微笑みと涙、どちらに心が振れるにしろ、犬好きにはたまらない。また、人間に従順な生きものとして常にその筆頭に挙げられる犬だが、実のところ、犬は神に逆らって人間についたという言い伝えが最後に紹介され、尚一層、犬という生きものが愛おしくなる。
作者テランによれば、ヒコックとギヴが出会うシーンは、テランがアメリカ国内を旅行中、実際に経験した出来事がヒントになっているという。また本書の登場人物の大半も旅の先々でたまたま出会った実在の人物がモデルになっているそうだ。だからなのかもしれない。ほんのチョイ役に至るまで丁寧に愛情深く描かれている。それも本書の魅力のひとつだ。自分の墓碑銘にはただひとこと“母”と刻んでくれとアンナに頼む名もない老婆も、亡き妻に本の朗読を続けている時計屋のボブも、イラク帰還兵のヒコックにまっとうな敬意を示す警官も、過ちを正すに憚(はばか)ることなくヒコックに率直に謝るヴェロニカも、みな出番は少なくとも心に残るキャラクターだ。そして、みなどこかしら懐かしいキャラクターだ。そんな彼らひとりひとりを通じて、テランが意図した“アメリカ人の暮らしの壁画”が読者の眼のまえに見事に現われる。