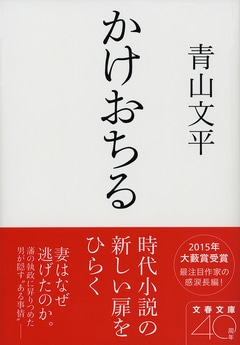ともあれ、受ける。もう、丸一年、能の所作を喋っていない。話を振られると、唇が勝手に語りたがる。それに、能を語っている限りは、己れのもろもろに触れずとも済む。
「それも、ずいぶんと派手に反るそうではないか」
そのつもりではある。が、どれほどできているかは自分では見えぬ。
「反れば反った分だけ、頭が舞台に近づく。つまりは、打ちやすくなる。まっすぐでも十分に危あやういのに、なんで反る?」
「頭はまっすぐを心がけても、躰は知らずに庇(かば)おうといたします」
躰を仰向けに戻して、剛はつづけた。
「まっすぐのつもりが、つい前がかりになってしまいがちになる。反ろうとして初めて、まっすぐを保てるのではないか、と」
「釣りを用意しておくというわけか」
言葉を交わすうちに、だんだんと頭がはっきりしてくる。
「しかし、おぬしの弓形(ゆみなり)は誰がどう見てもきついようだぞ。怖くはないのか」
「いえ」
むろん、怖い。
「慣れておりますれば」
倒れるたびに怖い。
「それに、自分は能装束を着けたことがありませぬが……」
ひどく怖いが、その怖さを喜び勇んで引き受けない限り、能で生き延びる目はない。
「シテの装束はたいそうで、身にまとうと己れが巨像になったかのごとくに感じられると聞きます。その上、どこもかしこも直線を押し立てる仕立てで、生身の人の線を消し去る。それゆえ、動きを小さく見せるとも耳にしました」
剛は、取ってつける。
「仏ダオレにしても、反り返るようにしていないと、まっすぐに映らぬのではないかと判じましてございます」
自分で語っていても、それらしく聴こえる。当たっていなくもないのだろう。けれど、言葉は心底(しんてい)から出たものではない。そんなまっとうな理由で、怖さを退(の)けているのではない。自分が反り返るのは、ただ心配でたまらぬからだ。居ても立ってもいられぬからだ。誰よりも高く跳び、誰よりも恐れを消し去って倒れてようやく、己れを能役者と見なすことができる。毛ほども守らずに倒れても、割れぬ頭を持っていたらどんなにいいだろう。
「どうやら……」
ふっと息をついてから、武家は言う。
「頭のなかも無事のようだな」
来たぞ、と剛は思う。
仏ダオレを切り出されたときから、あるいは、と想っていた。
武家は語りやすい能の話にかこつけて、剛の受け答えを吟味していたのだろう。
お互い様だ。
剛とて、初めて会う武家としごくまともな能の話を交わしながら、武家のまともではない部分を探っていた。
武家の話は、いかにもおかしい。
鵜呑みにすれば、武家は自分の仏ダオレを人づてに聞いたらしいが、その人とは、いったい誰だ。