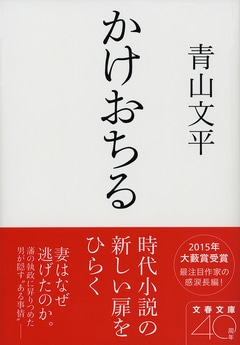自分は野宮(のみや)でしか稽古をしない。目にしたことがある者といえば、保(たもつ)とノミヤの二人だけだ。でも、仏ダオレと向き合ったのは保が海へ流れたあとだし、自分にさえ二度と姿を見せようとしないノミヤがこの武家に顔を向けるとも思えない。となれば、武家がわざわざ人をつかって自分の稽古を見張らせたということになるが、それこそ、ありえんだろう。おそらくはこの屋敷の主(あるじ)なのであろう、目の前の上士(じょうし)らしい武家が、捨て置かれることに慣れ切った若造に、なんの用がある?
とはいえ、そのありえぬことがあったのは、いま、自分がここでこうしていることで明らかだ。自分は石舞台で倒れた。武家か、あるいは武家の手下(てか)が台地を下り、野宮に立って、崖を回り、石舞台を訪れない限り、自分が助け出されることはない。
いったい、どういうことだ。
ひょっとすると、野宮で砂金でも見つかったか。
それで一帯を探り回って、化外(けがい)の地だった上流まで踏み入り、石舞台に出くわして、想わぬ厄介者を見つけてしまったか。
ならば、野宮のつい脇で、意識を失って倒れておるのだ。そのまま打ち捨てておけばいい。よしんば、救い出したにしても、こんな上等の座敷に置かず、納屋にでも放り込んでおくことだ。すくなくとも、当主みずから、「おぬしの仏ダオレは反り返るらしいな」などと、語りかけてはいけない。捨て置かれるのに慣れた者へのいちばんの功徳(くどく)は、目もくれぬことである。
「おぬし、ここでどれほど眠っていたかわかるか」
どこまで見透かしているのだろうか、剛の疑念を去(い)なすかのように、武家は言う。
「いえ」
剛もとりあえず答える。石舞台に立ったのは朝だった。表は見えぬが、行灯が点(とも)っているのだから、いまは日も暮れているのだろう。自分の見当ではほぼ半日といったところだが、武家が話を切り出すことからすると、あるいは丸一日を越えているのやもしれぬ。
「三日だぞ」
すっと、武家は口にする。
「その間、水気(みずけ)も摂(と)らぬ」
どうりで渇いていたわけだ。
「あるいは、戻らぬのではないかと危惧した」
それ、その物言いがいけない。自分を、砂金探しの路すがらで心ならずも見つけてしまった名もなき厄介者と思えなくなる。
「道具役、屋島五郎(やしまごろう)の嗣子(しし)の屋島剛だな」
武家はくっきりとつづけて駄目を押す。自分を屋島の者と知っていると言う。
「嗣子ではありません」
それならそれで断わっておくことがある。
「長子ではありますが、跡取りではない」
自分は屋島剛ではある。けれど、屋島五郎の嗣子ではない。屋島の家の跡取りをお望みなら、それは自分ではない。道具役を継ぐのは六つ齢下の弟、正(まさし)だ。「こっちも跡取りに用があるわけではない」
事(こと)もなげに、武家は言う。
「用向きは、おぬしだ」