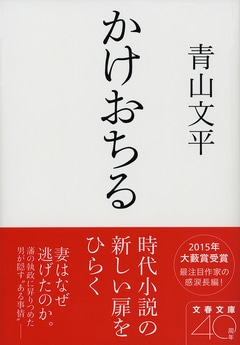目覚めると、横になっている。
すぐには、訳がわからぬ。
わからぬ訳を、頭の後ろの疼(うず)きがほのめかして、石舞台(いしぶたい)での仏ダオレにたどり着く。
また、しくじった。
首をもたげるのが遅れたか、遅れはしなかったものの、石の衝撃で支え切れなかったか……ともあれ、頭を打ったのだろう。
思わず、ノミヤの姿を探す。
けれど、仰向けになった目に映るのは台地の星月夜(ほしづくよ)ではなく、行灯(あんどん)にうっすらと浮かび上がった天井の板目だ。躰(からだ)は戸板の上ではなく座敷にあって、夜具に包まれている。どうやら、どこぞの屋敷に居るらしい。道具役のそれが、納屋に見えてくるような屋敷だ。
とっ散らかろうとする頭をなんとか呼び戻して、とにかく、躰を起こそうとする。なにがなにやらわからぬが、そこが自分の居る場でないことだけはわかる。
とたんに、疼きがずっくんと脈を打って、背中から落ちた。
ふーと息をついて、仰向けのまま両手の指を動かし、そして両足の指を動かしてみる。
だいじょうぶ。動く。躰は破(や)れていない。
もう一度、こんどは横を向いて、半身になってから床を離れようとする。
と、横臥(おうが)した目が、座した袴の両膝を捉えた。
人、なのだろうなと思いつつ、袴の上をなぞる。腹があって、肩があって、頭がある。人、である。
腰に目を戻すと脇差が見えるから、武家なのだろう。
齢(とし)の頃は三十を回ったあたりか、組んだ単衣(ひとえ)の袖から覗く二の腕が、膂力(りょりょく)の強さを伝えてくる。
ここはどこか、と尋ねようか、助けてもらった礼を述べようか、いや、まだ助けられたとは限らんな、などと、淀(よど)みが抜け切らぬ頭が言葉を見つけあぐねていると、武家の方から先に声を発した。
「水を飲むか」
言われてみれば、たしかに喉がひどく渇いている。「ゆっくりな」と念押しされつつ差し出された水差しの吸い口を含むと、染み渡っていくようだった。
「おぬしの仏ダオレは……」
ひと息ついた剛(たける)に、武家はいきなり仏ダオレを口にする。「反(そ)り返るらしいな」
いかにも、反り返る。多かれすくなかれ、皆、反りはするようだが、剛はとりわけ背を大きく反らして倒れる。
「ええ」