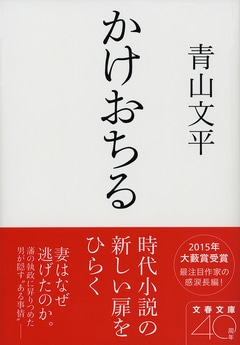前回までのあらすじ
藤戸藩の道具役・屋島五郎の長男として生まれた剛。しかし、幼くして母を亡くし、その後やってきた父の後添えによって嫡子としての居場処を失う。以来、三つ齢上の友・岩船保の稽古を覗かせてもらうほかは、野宮と呼ばれる河原で独りひたすら能の稽古に励む日々を送っていたが、突如、さらなる不幸に見舞われる。唯一の頼りであった保が切腹を命じられたのだ。いよいよ独りきりになり、稽古に没入していたはずの剛は、ある日、知らぬ屋敷で目を覚ます。横には藩の目付だという鵜飼又四郎なる人物がいて、剛に藤戸藩の身代わり藩主になるよう告げた。

江戸上がりまでの五日はあっという間に過ぎた。
その五日のあいだ、鵜飼又四郎は変わらずに要る話も要らぬ話も語りつづけた。
剛のほうからも、訊いた。
跳んで抜けるべき練り塀が、頭から消えたわけではない。己れのうちに、なにを居座っていると謗るもう一人の己れが居る。
日を経るに連れ、そやつはますます声高になっていくのだが、訊きたいことは次から次へと湧いてくるのだった。
なぜか、最初に浮かんだのは、平たい海の魚が乗った一汁二菜の膳についてだった。どうせ問うなら、もっと他に問うことが幾らでもあるだろうに、こうと想い込んだ子供のように、そこからどうにも離れられない。
あのとき、箸が止まった剛に、今朝は残してもよいが、躰が戻ったらけっして残すな、と又四郎は言った。求められた用を毒味と想っていたときは得心していたあの言葉が、身代わりとわかってからはずっと引っかかっている。
又四郎はつまり、本物の御藩主ならば断じて残さぬ、と言ったことになる。以来、なんで、御藩主ならば残さぬのか、繰り返し考えているのだが、答が出ない。箸を持つのは誰でもない、御藩主だ。御国のてっぺんに居るはずの御方だ。なにをどれほど食べようと、あるいは食べなかろうと、なんの不都合もあるまい。
「いや」
けれど、そうと口に出すと、又四郎はきっぱりと言った。
「不都合は生ずる」
「どのような?」
「膳を調える者たちが混乱する」
「なにゆえに……」
御藩主が料理を残して混乱するのなら、それは混乱するほうに落ち度があるのではなかろうか。
「御藩主は常に膳をきれいに召し上がるからだ。御膳の掛の者から見れば、料理を残す御藩主は御藩主ではない。それゆえ、おぬしもけっして残してはならぬ。戻った膳を見ただけで、人が代わったと気取られる」
「ならば……」
身代わりが残してはならぬことはわかった。しかし、なんで御藩主が残してならぬのかはわからぬままだ。答えたようで、答えていない。
「なにゆえに御藩主は膳をきれいに召し上がらなければならぬのでしょう」
「だからっ」
即座に、又四郎は返した。
「御藩主とはそういうものなのだ」
どうやら堂々巡りらしい。
「しかし、そうだな……」
剛が別の問い方を思案しかけたとき、しかし、又四郎がぽつりと言葉を足した。
「言われてみれば、これにしても大事な、要らぬ話なのかもしれんな」
二人は屋敷内の竹林をゆっくりと歩んでいる。それも、声が伝わらぬようにするための用心なのだろう。わずかな風でも揺らぐ枝葉の擦れ合う音で、話す側から声が掻き消される。