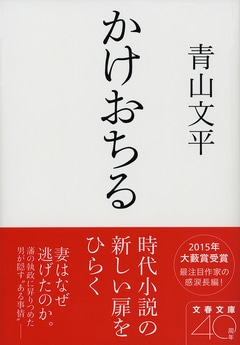「自明と見なしていることを人に説くのはなかなかにむずかしいものだが……」
又四郎はおもむろに語り出す。
「我々は皆、役を務めておる、とでも言えばよいか」
「役、ですか」
能役者にはとっつきやすい説き様だ。舞台はシテ独りでは立ち上がらない。諸役そろっての能だ。地謡方と囃子方が脈を打たせ、ワキ方が温めて、初めてシテは橋掛りを渡り、横板を踏んで、本舞台の常座に足を踏み入れることができる。
「ああ、俺であれば、いまは目付の役を果たしておる。江戸屋敷に入ったら、御側御用取次と御小納戸頭取の役に替わる」
それは、すでに又四郎の要る話のなかで聞いている。御側御用取次は江戸家老をはじめとする重臣と藩主の仲立ちをする役で、御小納戸頭取はこの国にあっては藩主の身辺の世話に当たる小姓と小納戸の両方を束ねる役である。要するに、身代わりが藩士と接する場には常に鵜飼又四郎が介して、化けの皮が剥がれぬよう対処するということのようだ。手始めに、小姓と小納戸は、皆、入れ替えたらしい。
「それぞれがそれぞれの役をまっとうすることで御家が回り、御国が成り立つ。これは、わかるな」
「ええ」
わかる、と言うよりも、わからざるをえない。剛が己れを能役者と認められないのも、それゆえかもしれぬと思えるくらいだ。
おそらくは能ほど、それぞれがそれぞれの役を究めようとする世界はない。一人一人が孤立しているかに映るまでに、各々が各々の能を探る。能ならではの鍛え上げられた構造が、それを許す。
シテに型があるように、囃子方には手組があり、唱歌がある。シテがたとえればサシ込ミヒラキからスミトリ、サシ回シヒラキへと型をつないで舞うように、鼓は三ツ地三クサリにツヅケと手組をつないで囃す。
その構造のなかで己れの能を研ぎつづけてきた諸役は、舞台に上がってもあっさりとシテの能に合わせたりはしない。己れの能を貫き、ぶつかれば組み伏せんとする。それぞれの能が競い、闘い、発した熱が舞台に溜まりに溜まり、それがまた演者の躰に移って満ちて舞台へ還って、そうして諸役の躰を廻り廻って、目には見えぬ世界が立ち現れてくる。
他に合わせれば、己れの能が濁る。諸役の能が濁れば、舞台が濁る。孤立する諸役が、互いに合わせることなくひとつになる……つまりは能になるための闘いが、シテを主役にする。剛は誰よりも孤立して野宮の役者となったが、孤立した者どうしが統合へ至るための格闘を、まだ知らない。