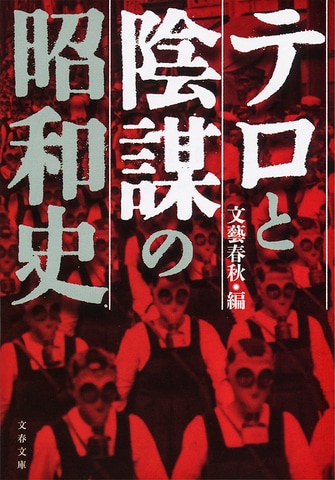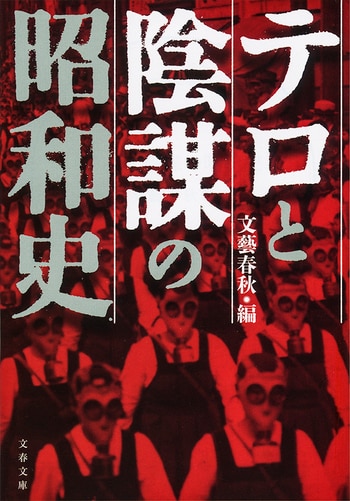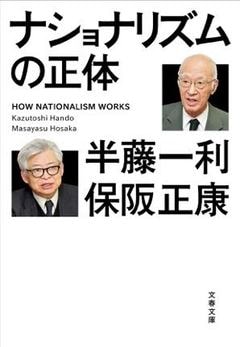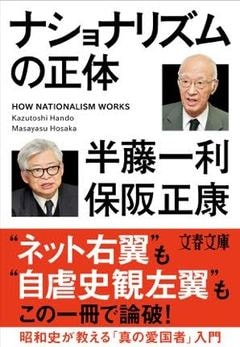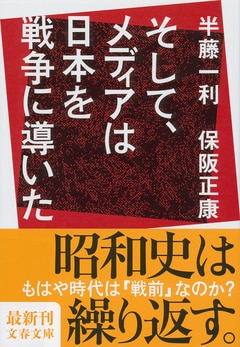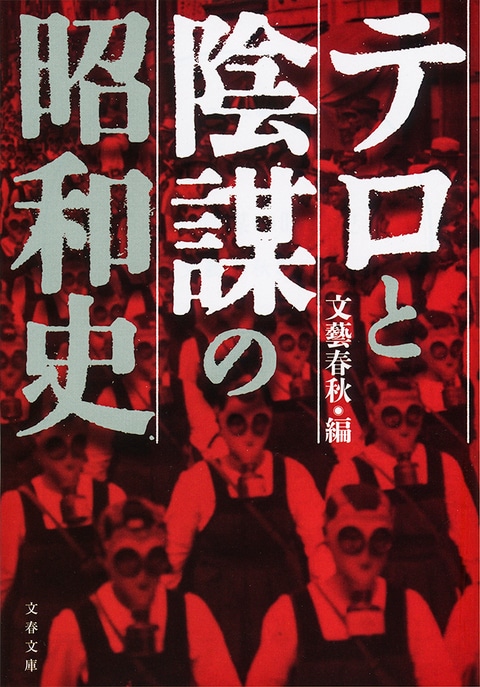
昭和史は人類史の見本市である――と私はこれまでなんども書いてきた。人類史が体験した政治・社会現象のほとんどすべてが、昭和史という時代には凝縮している。だからこそ昭和史は知恵の集積空間となる。
本書は、その中でもテロと陰謀のおどろおどろしい局面に関わった人物たちの証言、あるいはその回想である。昭和の年表を繙くとわかるのだが、昭和三年の満州某重大事件(中国・東北地方の軍閥張作霖暗殺事件=本書でも取り上げている)から始まり、六年九月の満州事変、その後の中国での各種事件はテロと陰謀のくり返しだったといってもいい。もともと日本人はこのような政治的、軍事的手法は得手なほうではなかっただけに、どういう考えで、あるいはどのような手法でこうした不穏当な事件を起こしたのだろうとの疑問がわいてくる。
そのような疑問を軸に、月刊「文藝春秋」等に掲載された関連記事をまとめたのが、本書ともいえる。
本書に収められている証言、回想は、二つのタイプを代表している。ひとつは、「文藝春秋」昭和六年十月号の当時の軍人、政治家、ジャーナリスト、研究者たちによる座談会(「満蒙と我が特殊権益座談会」)や、同誌昭和七年九月号の菊池寛や直木三十五らによる「荒木陸相に物を訊く座談会」などである。いわば同時代史としての興味がある証言である。同誌昭和八年二月号の平野嶺夫による「満州国執政・愛新覚羅溥儀に謁するの記」などもこの系列なのだが、新進作家の平野は文藝春秋の特派記者として溥儀への単独インタビューを試みた。これに協力したのが川島芳子で、その手づるを通じて満州国執政に就任した溥儀に会えたようであった。
実際に溥儀への面談は、この記事を読んでもわずかな時間、というより儀礼的な挨拶をしただけなのだが、それでも溥儀について次のように書いている。
「スラリと立たせられた執政は、心持ち横を向いて、抑揚の大きくないきわめて上品らしい言葉で、何事かを通訳に言われた」
溥儀は平野に、新京に永住されるつもりかと尋ねたというのだ。平野はその意思はないようであったが、それでも「この新京が、執政の御治政とともに、ますます繁栄に赴かんことをお祈り致します」と答えている。すると溥儀は、通訳からその言を聞き、「再び軽い微笑みを浮ばせられて、静かにうちうなずかれた」とある。
こうした描写だけでは、溥儀の心中そのものはなかなか窺い知れないのだが、しかし極東国際軍事裁判の法廷での、日本側から半ば脅されるようにして執政の地位に就いたとの証言とは異なった印象を受ける。あえてつけ加えるなら、溥儀も一九一一年の辛亥革命によって清朝帝政が倒されたあとの自らの復権を期待していたことは明らかなように見受けられるのだ。