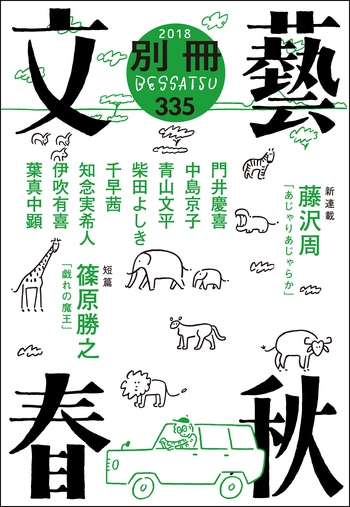「咲子なら銀行強盗だってできそうだ」
「銀行強盗ってこんなんだっけ?」
「西部劇に出てくる強盗は、ニトログリセリンで金庫の扉ごとぶっ飛ばしてたんだよ」
「へえ、そうなんだ」あまり関心はないようで、「侑さん、早く、乗って、乗って」と中に入るように急かされた。
「えっ、咲子が運転する気?」
助手席側のドアは凍ったままなので、先に乗った方が助手席まで移動することになる。
「たまには私にも運転させてくれないと、腕が鈍ってしまうわ」
モスクワの冬は幹線道路であっても白線が見えないほど積雪し、スケートリンクのようだというのに、咲子に臆する様子はない。
窮屈な姿勢で助手席に達した時には、咲子は運転席でキーを回していた。何度か回さないとかからないエンジンが一発でかかった。
「おっ、幸先がいいな」
「ライラさんに感謝しないとね」
今週の初め、咲子はCNN特派員の妻から「新しい不凍液が手に入ったからどうぞ」とプレゼントされた。珍しく暖かい日で、彼女は交換までしてくれたそうだ。それで「せっかく新しい不凍液になったんだから、これから早朝ドライブに行かない?」と咲子が言い出したのだった。
咲子がアクセルを踏むと、サニーは尻を振ってからスタートした。スノータイヤらしきものに履き替えてはいるが、日本製ほど良質のゴムを使っていないので信用ならない。ソ連では道路が傷むという理由でチェーンもスパイクタイヤも禁止されている。
「頼むから、そんなに飛ばさないでくれよ」
片側四車線もある大通りには、まばらにしか車は走っていなかったが、咲子はハミングしながら軽快に速度を上げていく。
「信号が赤だぞ」
まだ百メートルほど先だが、土井垣の声を合図に咲子はブレーキを踏んだ。車は止まる気配もなくソリのように氷上を滑っていく。前に車が停まっていたので、心臓が縮み上がったが、車の一メートルほど手前でなんとか停止した。
「セーフ」
二人同時に手を横に広げた。前に一度タクシーに当たってしまい、タクシーのバンパーがへこんだ。運転手は「お互い様だ」と弁償を請求せずに許してくれた。
青になったが、咲子はすぐにスタートさせない。けっして前の車を信じてはいけないのがソ連の運転の常識である。ソ連製のモスクビッチは何度かエンストした末、後輪を滑らせて走り出した。確実に走ったのを見届けてから、咲子もアクセルを踏んだ。
一九八八年十二月、土井垣がモスクワに来て二度目の冬を迎えていた。四月に咲子がモスクワに来て、新婚生活が始まった。明るい性格の彼女はアパートでも人気者で、海外特派員の妻からしょっちゅう声をかけられる。
本当なら一緒に帰りたかったが、十一月に咲子一人で帰国させた。九月に昭和天皇のご重体が発表されて以来、新聞社は皇居のすべての門に人を配置し二十四時間態勢を敷いた。デスクからも「悪いが今年はモスクワに代役を出せないかもしれない」と年末年始の休みがない可能性があると言い渡されていた。