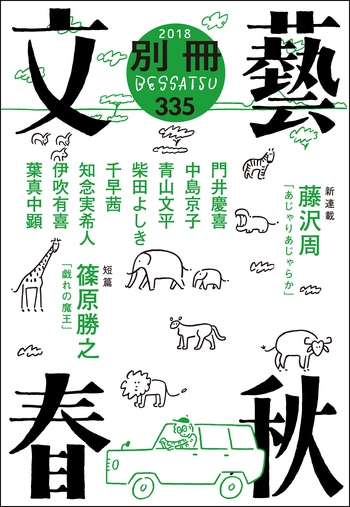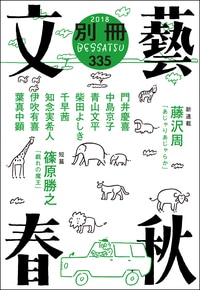
前回までのあらすじ
一九八七年四月、東洋新聞の土井垣侑は特派員としてモスクワに降り立った。当時のソ連では記者は政府の管理下でしか取材をすることができなかった。そんな状況にフラストレーションを溜めていた土井垣は、精力的に取材を重ね、タタールの独立運動のデモをスクープ。ついに「特ダネ禁止」に風穴を開けた。それと並行して土井垣は人脈を広げ、モデル事務所社長のハンナと知り合い親交を深める。だがある日、取材先のホテルで、偶然ハンナが政府高官の訪れた部屋にいたのを目撃してしまう。
第4章 裏切りの微笑
1
アパートを出ると辺り一面が雪景色だった。朝の強い日差しが雪に反射して目が開けられないほど眩しい。路面は完全に凍っている。踏みしめると足を取られてしまうので、靴底を少しずつ滑らせながら歩く方が安全だ。今週の半ばあたりからモスクワには大寒波が訪れ、この日の気温は氷点下二十二度。髭は一瞬で凍り、息を吸うたびに鼻毛が割れていく音がする。咲子の顔を見ると、目深に被ったシャープカから出た睫毛が凍っていた。
アパートの駐車場にやっとたどり着いたが、人一人いなかった。車のほとんどはカバーが掛けられ、雪解けする春まで冬眠中である。ワイパーを立てた状態で放置してある数少ない車が、土井垣の愛車サニーだ。ボディーも窓ガラスも、厚い氷で凍結している。
「本当にやるのか」
止めるつもりで言ったが咲子には通じない。
「だって楽しそうじゃない。モスクワは道も広いし、日曜のこんな早い時間は誰も外出なんてしないだろうし」
時刻は朝の八時五十分、冬の遅い太陽がやっと顔を出したばかりだ。
運転席のドアの前で、誰も見ていないか周囲を確認してから、土井垣はコートのポケットからかウオッカと脱脂綿を出した。まずキーの先を使って鍵穴を削り、そこにウオッカに浸した脱脂綿を詰め込む。チャッカマンを出して火を付ける。一瞬、火柱が立って消えた。鍵を挿し込んだ。
「入った。開いたぞ」
鍵が回ったことに喜んだものの、レバーを引っ張ってもドアはビクともしない。窓ガラスの氷は叩けば割れるのだが、隙間に入り込んだものは簡単には解けない。
「これだけ凍ると力ずくでは開かないんじゃないか」
諦めかけたが、咲子は「待って」と土井垣の手から残りの脱脂綿を奪った。それをほぐして細く伸ばし、溝を作ったドアの四辺に貼り付けていく。ドアの三分の一ほどが綿で覆われた。咲子は豪快にウオッカをかけていく。
「大丈夫か。火事になったら警察がくるぞ」
「平気、平気。これくらいしないと氷は吹っ飛ばないわ」
土井垣は完全に腰が引けていたが、咲子は迷いなくチャッカマンのスイッチを押した。
一カ所目はすぐ消えた。二カ所目と三カ所目は細い綿糸がちりちり燃えたが、氷を解かす前に火は消えてしまった。四カ所目は綿の量も多く、ウオッカもたっぷり沁み込んでいたようだ。点火とともに炎が走って氷がひび割れしていった。
「やったぁ、開いたわ」ドアを引きながら快哉を叫んだ。