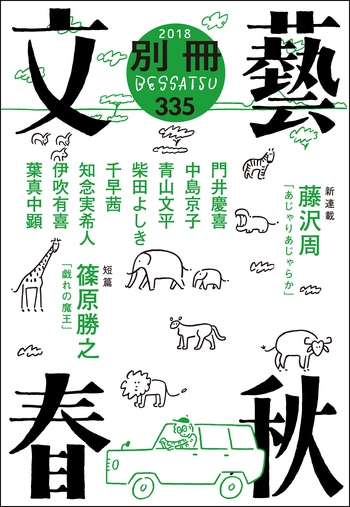「お正月まで二ヵ月くらいゆっくりして、親孝行をしてきたら」そう咲子を送り出したのだが、「侑さんが心配だから」とたった二週間で戻ってきた。しかも刺身など日本食を段ボール数個、百キロ以上も買い込んで。
それらをソ連で食生活に苦心している各国の記者にお裾分けした。そうするとお返しが来る。この新品の不凍液もお礼の品の一つだ。
ゴーリキー通りに入る。日本では雪の日は運転するなと教わったが、ソ連でそんなことを言えば一年の三分の二は車を使えなくなる。
さらに勝利広場を越えて北東へと走る。この道はソ連第二の都市、レニングラードまで七百キロ続いている。広くて真っすぐで、まるで滑走路のようだ。
「すごく気持ちいいね」
「極寒の国に来てるとはとても思えないな」
ヒーターがこもる車内に太陽が照り付けてきて暑くなってきた。走りながらコートを剥ぐように脱ぐと、咲子も「手伝って」とシートベルトを外し、片手ずつ袖を抜いた。
周りに車が一台もいなくなったことで、咲子はさらにスピードをあげた。
「おいおい、あんまり飛ばすなよ。こっちは生きた心地がしないんだから」
手すりにつかまったまま土井垣は言う。五十キロ程度だが、去年一年、冬の運転を経験した土井垣でもこんなに飛ばさなかった。
段ボールのようなものが雪に埋もれていた。
「あれ、猫?」
「違うよ、段ボール」
すでに咲子は急ブレーキを踏んでいた。車は左方向にスリップした。
「侑さん、どっちだっけ?」ハンドルを右に回しながら咲子が聞く。
「逆だよ、スリップしてる方向に切るんだ」
「あ、そうだった」
慌てて左に回すがもう遅い。制御を失った車は広い道路の真ん中を回転していく。思わず瞑目した土井垣が瞼を開けると、反対車線にちょうど方向転換した状態で停まっていた。
咲子を見た。両手でハンドルを握ったまま黙っている。だが怖がってはいなかった。
「なんか刑事ドラマみたいね」
そう言うと、右手を上げる。「よしタカ、犯人追走しよう」
今度は咲子の話が方向転換した。
「なんだっけ、それ?」
「あぶない刑事でしょ。鷹山刑事よ」
前にも言われたが、日本にいた頃もドラマはまったく見ていなかったので知らない。
「で、俺はなんて言うんだっけ」
「ユージでしょ、あるいは大下刑事」
「了解、大下刑事」
土井垣が調子を合わせると彼女は力を入れてアクセルを踏む。車は再びスピードに乗ったが、そこで土井垣の右側からシャンパンのコルクが抜けたような音がして、ドアが開きかけた。
「咲子、こっち、半ドアだったぞ」
きちんと閉まらないまま凍っていたのが解けたのだ。閉めようとするが氷が挟まっているのか完全には閉まらない。
「ダメだ。閉まらん」
「停まるのは怖いから、そのまま押さえといて」
「そんな無茶な」
土井垣がずっとドアを引っ張ったまま、サニーはなんとか無事にアパートに戻った。