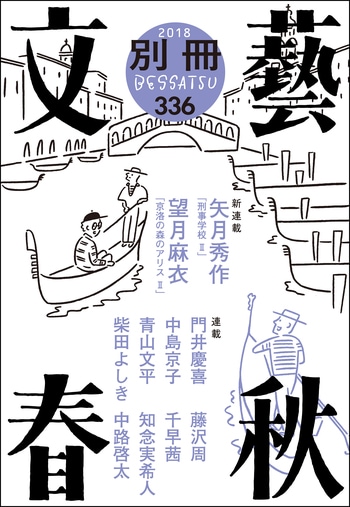「くそっ、先を越された」
「繋がらないの?」
「たぶんすべてふさがってる。モスクワの特派員たちが回線を繋げたままにしてるんだろ」
東京の外信部デスクも焦っているのではないか。そこで気が変わった。
「悪いけど、咲子はここにいて電話番しててくれないか。俺はちょっと出かけてくる」
「こんな時間にどこ行くの」
「まだ十時だ。誰かいるかもしれない」
「こんな日、誰も出歩かないんじゃない?」
「なにも知らずに飲み歩いてる者がいるかもしれないだろ」
自分だって今の今まで知らなかったのだ。きょう会った相手もそんな話は一切せずに、気持ち良く酔っていた。
今、俺がすべきことはテレビを観ることではない。ソ連という国が、この歴史的転換をどう見ているのか、自分の目と耳で確認することだ。
タクシーを拾って街に戻る。一時間前まではそれなりに賑わっていたバーはどこもかしこも閑古鳥が鳴いていた。
東側からの西側への移動は半年前の、初夏から始まっていた。五月、いち早く民主化運動が始まったソ連の衛星国のハンガリー兵士が西側のオーストリアとの国境沿いにある有刺鉄線をペンチで切断。その情報を知った東独国民がチェコスロバキア経由でハンガリーに入り始めた。警備によって流出はいったん阻まれたが、八月に「ヨーロッパ・ピクニック計画」という政治集会に紛れておよそ千人が脱出した。国境警備隊の隙をついてハンガリーから西側に脱出する東独国民はその後も増える一方で、その数は九月だけで三万三千人、十一月には十三万三千人にも及んだ。
東独政府が国民の不満を抑えられなくなってきたことから「近々、国民の出国ビザの申請に応じるようだ」といった情報は方々から出ていた。だが十ヶ月前にはホーネッカー東独議長が「壁は必要な理由がある限り、今後百年は残り続ける」と宣言していたのだ。いくら政府の力が弱まっても、当面は旅行の自由が段階的に認められるだけだろうと思っていた。まさか二十八年もの長い間、ドイツを東西に隔ててきた「ベルリンの壁」が存在意義をなくすなど、土井垣は想像もしなかったし、取材相手や海外特派員の誰も、そんな話はしていなかった。
三軒目のバーに入った。重たい二重扉を開けると、ポマードで髪をオールバックに固めた男が、黒いコートの襟を立てて出てくるところだった。以前、ボリスに教えられた、父親をKGBの幹部に持つ保守派のエリートだ。男も土井垣を覚えていたようでメタル製の眼鏡の奥で灰色の瞳が光った。