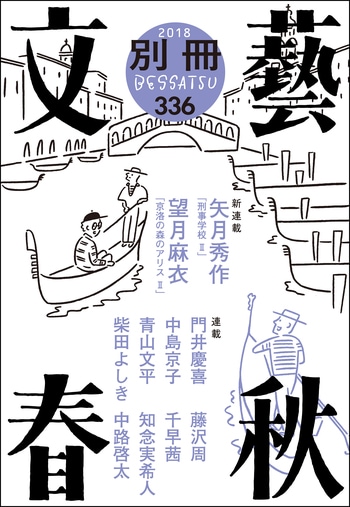「日本の東洋新聞の記者、タスク・ドイガキだ。きょう東ドイツ国民が国境を越えて西ベルリンに入っているのを知っているか」
自己紹介した勢いで質問した。一八五センチ以上はある彼は、目線だけを動かし土井垣の顔から足元まで見下ろしていく。映画俳優のような整った顔をしているが、表情がなく、心が読み取れない。無視されるのだろう、そう思いながら立っていると薄い唇が動いた。
「私はユリアーン・クラーヴジエヴィチだ」
舌を噛みそうな名前だ。ソ連では米国のようにファーストネームで呼ぶ習慣がなく、親しくない相手はフルネームで呼ばなくてはならない。声に出して確認すると、彼は「ユーリでいい」と許してくれた。
「ユーリ、もう一度聞く。ブランデンブルク検問所のゲートが上がり、多くの民衆が東ドイツから西側に移動しているのを知ってるか」
「もちろんだ」とくに驚くことなく答えた。
「どこのバーにも人がいないのに、あなたは関心がないのか」
「その質問は、私も自宅のテレビの前に座っていなければならないという意味か」
「それなら、あなたはこの騒動を予想していたということか」
「さぁどうかな」微かに口角に皺が寄った。この男、なにか事情を知っている……。
「少し話を聞かせてくれないか」
そう言うと、彼は土井垣の顔を凝視した。
「あなたはボリスの知り合いだったな」
この男の大学の同期であるボリスは急進改革派のエリツィン支持者、この男は保守派だから思想は対極にある。だが一緒にいるところを見られている以上、隠しても仕方がない。「そうだ」と認め、ボリスから聞いたことを口にした。
「ボリスがエリツィン陣営の選挙を手伝っているように、あなたが保守派の選挙を手伝っているのを知っている」
「ボリスがエリツィンだって?」
訝しげな顔をされたので、「ボリスはあなたが将来、政治局員候補になると言っていた」と話をすり替えた。
「私はそんな器ではない」と謙遜したが、それ以上言ってこないから満更でもないのだろう。
「もう一度バーに行かないか」
「構わないが、短い時間にしてくれ」
「聞きたいことを聞いたら帰る。こっちも記事を送らないといけないんだ」
二人でバーに戻った。彼の体からはオーデコロンの匂いがした。髪も今さっきポマードを塗ってきたかのように艶がある。仕事を終えて、一度自宅でシャワーを浴びてから出てきたのか? ベルリン報道を観てから外出してきたとしたら、この男ずいぶん余裕がある。