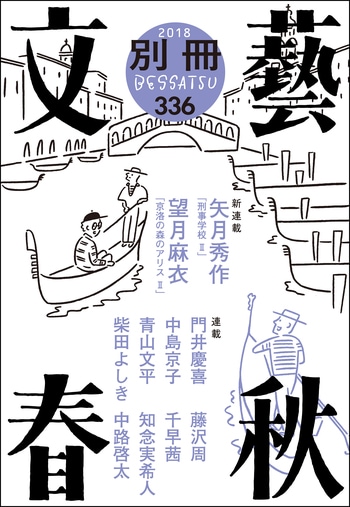私は曖昧に相づちを打つ。
今にして思うと『終パラ』の現場は、最初から予定も人員もギリギリな上に、スタッフ同士の連携もよくとれていたとは言えなかった。ガネのやつがバックレたことで水面下で燻っていた諸問題が一気に噴出し、現場は事実上、崩壊してしまった。
そんな状態でいいものがつくれるわけがない。作画は、本来放送に乗せられないレベルまで崩れ、それでも間に合わず、放送済み素材で急ごしらえした総集編でお茶を濁さざるを得なかった回が二度もあった。全部で十二話しかないのに、だ。ストーリーも当初予定していたものから、大幅変更せざるを得ず、作品は完全に迷走した。
自分が担当した作品に対してこういうことは思いたくないけれど、今日、納品してきた第十話など、正直、見るに堪えない出来だ。
つくってる側でさえ、そう思うくらいだから、視聴者の評判はさんざんだ。ネットでは駄作の評価がすでに固まり、SNSや掲示板では、『終パラ』がいかに駄目かという話題で盛り上がってしまっている。
「いい経験したと思いなよ。この仕事は修羅場の連続なんだから」
「そうですね」
確かにあの現場をどうにか回して、自分の担当話数をきっちり納品できたことは、自信になったかもしれない。
「ところで、あんたは今日で終わりなの」
「はい、まだ多少、資料の返却とか残ってますけど、一応は」
『終パラ』は、外部の制作会社が元請けで、私は下請けとして制作進行に入っているかたちだ。だから、自分の話数が終われば、基本的にお役御免になる。
「じゃあさ、次は私の作品の、血になってくれない?」
血――制作進行のことを指す七瀬監督独特の呼び方だ。
「は、はい」
私は即答した。
「大丈夫? これ、灰原さんとも話してるんだけど、もし気が進まなかったら断ってもいいんだよ。初めに言っとくけど、私の現場は、『終パラ』より修羅場になるかもよ。もちろん『終パラ』みたいな作品をつくる気はないけどね。途中で折れるくらいなら、最初から入らないで欲しいの」
「大丈夫です。やらせてください」
「そう。よかったあ。実は断られたらどうしようと思ってたのよ」
七瀬監督は、胸に手を当てて息をつく。
「断るだなんて、そんな」
七瀬監督の作品を手伝うのは、いわばこの会社に入ったときからの夢だ。断るなんてあり得ない。
むしろ私は、七瀬監督が、私がスタッフとして加わることを望んでくれていたことに感激していた。
「島田くんもさ、あんたこの一年でめっちゃ成長したって言ってたよ」
「え、そうなんですか」
島田さんは、すでに七瀬監督のスタッフにデスクとして入っている。島田さんに対する私の印象も、この一年でずいぶん変わった。たぶんかなり、いい方に。