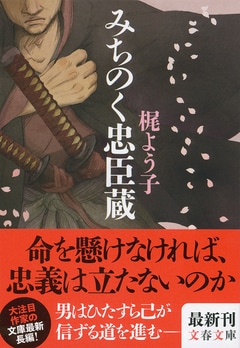朝顔や薬草など江戸の植物について造詣の深い梶さんが、次の長編の題材に選んだのは、江戸初期としてはエコな農法を実践していたとして、注目を集めている農地の開拓だ。
「舞台の埼玉県・三富新田は、五代将軍綱吉の頃、柳沢吉保が川越藩主時代に開拓しました。現在は、さつまいもの名産地としても知られています。航空写真で見ると、細長く人工的に短冊状に区画されているのがよくわかります。この形状だと、水利を引く手間が少なく、雑木林を植えることで堆肥もすべてその土地で賄えるというきわめて理想的で効率的な循環システムが、三百年前から実現していたんです」
小説は、当時、薪を取るために設けられた境界未定の荒野“秣場”で、農民同士の争いが起きたことから始まる。大塚村の少年・正蔵は、父の吉二郎とともに秣場へ薪を取りに行く帰りに、手に大豆のような黒子のある鶴間村の藤兵衛らに襲われる。身を挺して正蔵を守った父だが、やがてその傷が元で亡くなってしまう。
時は過ぎ、元禄。川越藩主に就いた柳沢吉保から、広大な秣場を二年で農地に変えるよう命じられた、筆頭家老の曾根権太夫は入植者を近隣の村から募り、開墾を始める。そこには、正蔵、そして藤兵衛らしき男の姿もあった……。だが、開拓を指示する権太夫の息子、啓太郎は、高圧的で農民たちと対立、なかなか開拓は進まない。
「綱吉に重用された柳沢がどのように出世したのか、その過程にも興味がありました。また江戸の人口が増加し、舟運が盛んで江戸に近い地としての川越の役割も重要になっていきます。さらに泰平を迎えるなかで、赤穂事件のように、武士の在り方に関わる問題も生まれます。そこで先祖の土地を守り、生きることを大切にする農民との対比で、三富の地から、元禄という時代を切り取れれば、と考えました」
しかし、水のない土地での農民たちの苦労は想像を絶する厳しさだった。
「『赤い風』というタイトルは、乾燥した赤土が、たびたび巻き上がる様子を、地元では“赤い風”と呼んだことからとりました。水が貴重な土地なので、風呂のかわりに、萱で体を拭く萱湯という習慣もあったそうです。資料を調べるうち、厳しい状況下でも、土地に順応していく人びとに驚かされました。改めて感じるのは、政治がどう変わろうと、そこで生きていく農民たちの力強さ。新たに土地を造り、育てていくことは、今以上に重みがあったはずです。もし、この小説で三富に興味をもって、実際に行っていただけたら、とてもうれしいですね」
かじようこ 東京都生まれ。二〇〇八年に「一朝の夢」で、松本清張賞を受賞し、単行本デビューする。一六年には、『ヨイ豊』で、歴史時代作家クラブ賞作品賞を受賞する。