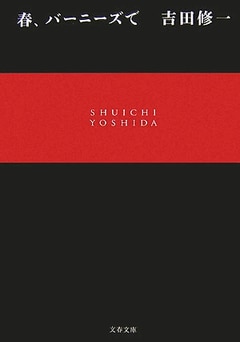吉田の作品に現代風俗が描き出されるようになったのは今に始まったことではない。その再現力には定評がある。『悪人』には九州特有の「匂い」が濃厚に漂い、博多、久留米、佐賀といった土地の細部が、相互の物理的な距離感とともに実にうまくとらえられていた。最新作の『国宝』は歌舞伎役者への綿密な取材に基づいた作品で、舞台の表裏の描き込みぶりは念の入ったものである。
そんな吉田流のリアリズムを支えるのは、登場人物に寄り添ったやわらかい視線だと言える。決して背伸びをしない。激しい情緒やドラマチックな盛り上がりがあっても、おだやかな常識と安心感が覆う世界へと「目」が戻ってくる。だからこそ、この視線は小さなずれや揺らぎをとらえ、不安にも駆られうる。危機の予感にも敏感だ。
たとえば本書の冒頭。老朽化したビルの取り壊し工事を主人公の新宮明良と妻の歩美がながめやる場面がある。半分がすでに取り壊されたビルの屋上にショベルカーが乗っている。
「あれ、どうやって乗せるの?」
「さぁ、大きなクレーンで吊り上げたんだろ。まさか階段を上っていくわけにもいかないし」
半壊したビルの屋上に乗っているだけでも危なっかしいのに、小型ショベルカーはまるで自分の足元を自ら狭めていくように、そのアームでガリガリと足元のコンクリを崩している。更に恐ろしいのは、崩れたコンクリの塊が未切断の鉄筋で宙づりになり、ゆらゆらと空中で揺れていることだ。
「なんか、見てるとぞっとしてくるね。自分があそこの運転席に座ってるみたいで、ここにいても足が震えてこない?」
歩美の言う通りだった。
おだやかな常識と安心の世界に住む人にとって、危険は対岸の火事に見えるかもしれない。そういう意味では、対岸の火事は安心感を補強している。しかし、いつ自分がその対岸に放り出されるかわからない、そんな予兆をこの一瞬から読み取ることも不可能ではないだろう。