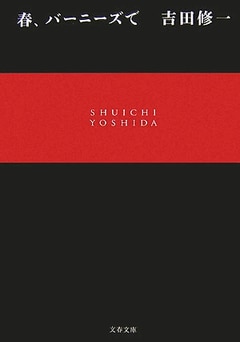私が思い出すのは『悪人』の一場面である。主人公の祐一は、出会い系サイトで知り合った佳乃が、別の男によって山中の道路に置き去りにされているのを見つける。佳乃は祐一のことなど相手にしていないが、その祐一に助けられてしまった屈辱から感情的になり、逆に祐一をなじり始める。彼女が口走るのはまるで事実と違うことだった。「絶対に言うてやる! 拉致られたって、レイプされたって言うてやる!」。
祐一はすっかり動転する。彼が思い出したのは、幼い日に「戻ってくる」と言いながら、自分を置き去りにした母親のことだった。
そのときふいに「母ちゃんはここに戻ってくる!」とフェリー乗り場で叫んだ、幼い自分の声が蘇った。誰も信じてくれなかったあのときの声が。
(中略)
「……俺は何もしとらん。俺は何もしとらん」
祐一は目を閉じていた。佳乃の喉を必死に押さえつけていた。恐ろしくて仕方なかった。佳乃の嘘を誰にも聞かせるわけにはいかなかった。早く嘘を殺さないと、真実のほうが殺されそうで怖かった。
「早く嘘を殺さないと、真実のほうが殺されそうで怖かった」。何という意味深い言葉だろう。祐一のこの感覚が、この小説の決定的な場面へとつながってしまう。
「正しさ」や「真実」が足元から崩れたときの、底知れぬ不安。ニュースを含め、私たちを日々とりまく言葉は、どぎつくはあってもどこかで私たちの安心を支えてもいる。しかし、その安心は脆弱なものだ。ひとたびそれがほころんだとき、向こう側には言いようもなく気持ちの悪い「見知らぬもの」がある。