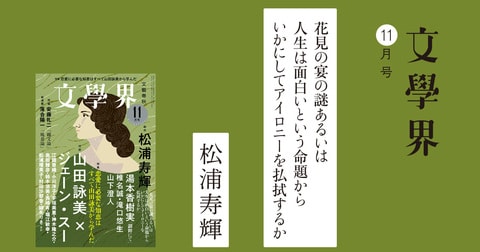麻原の荒唐無稽な物語を放逐できるだけの「力を持つ物語」を「私たちは果たして手にしているだろうか?」という最後の問いに、わたしはむしろ、否定的なニュアンスを読み取る。村上春樹自身、この問いを受けて、「私は小説家であり、ご存じのように小説家とは「物語」を職業的に語る人種である」とあえて断わりながら、「だからその命題〔最後の問いを指す〕は、私にとっては大きいという以上のものである」と言っている。「そのことについて私はこれからもずっと、真剣に切実に考え続けていかなくてはならない」とさえ語っている。麻原の差し出すジャンクの物語を放逐できるだけの、つまり浄化できる「まっとうな力を持つ物語」をわれわれは手にしていないのではないか、という小説家の忸怩(じくじ)たる思いとともに、そこには小説家ゆえの負い目が刻まれている。
小説家ゆえの負い目とは、文字どおり、小説を書いていなければ感じない負い目である。もっと言えば、麻原彰晃の用意したジャンクの物語に、自分の負けを認めるということだ。同時代で、小説家は大勢いるのに、これほどはっきりと負い目を、自分の負けを表明した小説家は寡聞にして村上春樹の他にわたしは知らない。「麻原の荒唐無稽な物語を放逐できるだけのまっとうな力を持つ物語を」、「私たちは果たして手にしているだろうか?」、いや、いない、と考える村上春樹は、この負い目の自覚によって、同時代の小説家の王位に就いたと言えるだろう。「目じるしのない悪夢」とは、それくらい重要な小説家のマニフェストになっている。
ではいったい、村上春樹によって自覚された負い目、つまり麻原彰晃に負けたという意識とはどういうものなのか。「麻原の差し出す荒唐無稽なジャンクの物語」に、村上春樹がそれまで書いてきた物語が負けたということでは、もちろんない。村上春樹の発言に感じられる負い目とは、誤解のないようにいえば、いわば麻原彰晃の発揮した“小説家としての読み”に対する負い目と言ってよい。言い換えれば、麻原彰晃は地下鉄サリン事件を引き起こす際に、この“小説家としての読み”を行使したのに、そのことに同時代の小説家で気づいたのが村上春樹ひとりだったということだ。“小説家としての読み”なのに、それはひとえに小説家だけが行使できる特権ではなかった。そのことに気づいた村上春樹は、おそらく愕然としたのではないかと想像される。だからこその、負い目の表明であり、言うまでもなく、それは小説家ゆえの負い目なのだ。