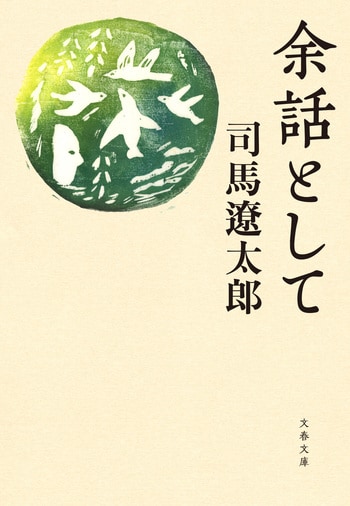司馬さんは「自・社とも電池の切れた政党で、誰がやっても電気はつかない。どんな組織でも三、四十年で電池が切れるんだね。細川さんはよくやるなあ」と読後感を洩らされた。そして自民党・社会党の政治家何人かについて触れた後、「文春は戦後、文藝春秋新社になったとき新しい電池が入った。それでも四十数年経ったね」と言われた。「ジャーナリズム」の反対語は「マンネリズム」だという。『文藝春秋』のような歴史の古い雑誌(会社)は、伝統に支えられてやり易い部分もある一方、ともすれば前例踏襲のマンネリに陥る危険も常にあった。かつて一世を風靡した雑誌や会社が、時代の変化とともに消滅していった例は枚挙にいとまない。「伝統」の何を廃し何を残すかは、私にとっても切実なテーマであった。ある時期から私は、文藝春秋にとって「その時」が来るとすればどういうときか、と漠然と夢想し、冷戦終結という激変が、あるいはそのきっかけになるのではないか、とぼんやりした不安を感じていた。それだけに、「電池が切れる」というタトエは深く記憶に残ったのである。
もう一つ、私が「オヤ」と思ったのは、話題が日韓関係に及んだ時であった。
この原稿を書いている二〇一九年十一月現在、日韓関係は戦後最悪と言っていいほど悪化しているが、まだそれほどでもなかった一九九三年の話である。と言っても、韓国は当時から付き合うのが難しい国だった。政権が代わるたびに「日韓新時代」を謳いつつ、他方で植民地支配に対する新たな「謝罪」と「賠償」を求めてくるのである。日本側は、戦後処理は一九六五年の日韓基本条約ですべて解決済みと考えていたから、うんざりする日本人は多かった。