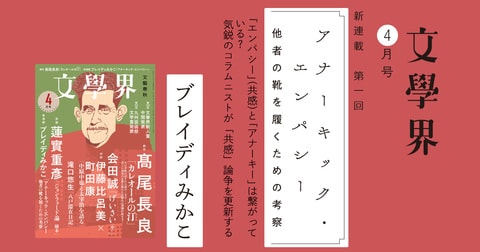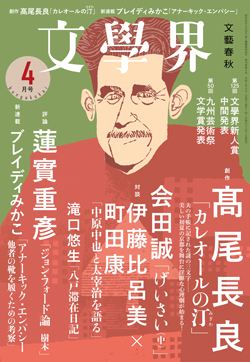
とはいえ、フォード的な風景が太い木の幹なしにも充分に成立しているのは、すでに述べておいた通りだ。『駅馬車』(Stagecoach, 1939)から『シャイアン』(Cheyenne Autumn, 1964)までのほぼ二十五年間にわたって、『荒野の決闘』(My Darling Clementine, 1946)や『アパッチ砦』(Fort Apache, 1948)や『黄色いリボン』(She Wore a Yellow Ribbon, 1949)、さらには『リオ・グランデの砦』(Rio Grande, 1950)、『捜索者』(The Searchers, 1956)、『バファロー大隊』(Sergeant Rutledge, 1960)などにいたるまでの作品の主要な舞台となったモニュメント・ヴァレーの岩石砂漠が、樹木を排することで特権的な風景たりえていたことからも明らかなように、(註2)太い木の幹があらゆる作品を律する主題論的な一貫性におさまるものだとはいえぬかもしれない。また、疲労しきったものたちが思わず吸い寄せられてゆくのは黒々とした木の幹のかたわらとはかぎらず、たとえばその流れが月の灯りに映える夜の川辺であったり、庭先と表通りとを隔てる木製の白い柵であったり、家の前にしつらえられた木製の回廊だったりもする。
にもかかわらず、ジョン・フォードの映画では、モノクロームのサイレント作品であろうと、色彩のついたトーキーであろうと、とうてい忘れがたい何本もの太い木の幹がまぎれもなく画面を彩っている。だが、それは、木という抽象的な概念ではなく、あくまで太い木の幹という具体的な画像として見るものの瞳を惹きつけていることが肝心なのだ。モノクロームの画面であれば黒々と構図の一部を占め、そのかたわらに立つ男女を直射日光から保護し、その向こうに拡がる風景との影の濃淡をきわだたせる太い木の幹がここでの問題となるのだが、その梢がフレームにおさまることはごく稀である。