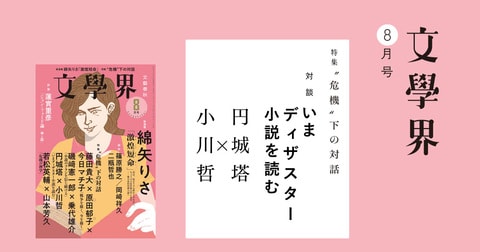III―3 歌が歌われ、踊りが踊られるとき
アマチュアであることの特権
ジョン・フォードの作品にあっては、いたるところで、あらゆる機会に、少なからぬ数の男女が、ひとりで、あるいは集団で歌を口ずさみ、ダンスを踊る。この映画作家にあっては、人間というものが、リズミカルな足さばきを披露したり、その声があたりに響かせる妙なる旋律で何ごとかを伝えようとする動物であることは、誰の目にも明らかなフィルム的現実にほかならない。実際、多くの研究者や批評家たちがそのことを指摘しており、「歌うこと」と「踊ること」についての言及は、いまではフォードをめぐる評論の「紋切り型」の一つとなっているとさえいえようかと思う。たとえば、キャサリン・カリナックの『西部はどのように歌われたか――ジョン・フォードの西部劇における音楽』(Kathryn Kalinak, How the West Was Sung - Music in the Westerns of John Ford, University of California Press, 2007)などという書物さえ刊行されているほどなのである。(註1)
それ故、ここでは、「そして人間」の断章のこれに先だつ「『不自然さ』に導かれて」や「雨と鏡」の場合とはいささか異なるアプローチが要求される。つまり、列挙による希少性や意外性の確認という視点からではなく、フォードがしばしばキャメラを向ける歌と踊りの中で、唯一にして最高の歌は、さらには唯一にして最高の踊りはいったいどの作品に描かれているのかが問われることになるだろう。だが、はたして、そんなことは可能なのだろうか。それがまったく不可能でもなかろうと思わせてしまうあたりに、フォードの磊落(らいらく)性が露呈されているように思う。
だが、批評家たちは、その磊落性を、さまざまな分析や説明によって遠ざけようとする。例えば、これまで何度も引用したことのあるタグ・ギャラガーの『ジョン・フォード――人とその作品』(Tag Gallagher, John Ford - The Man and His Films, University of California Press, 1986)の『幌馬車』(Wagon Master, 1950)をめぐる章には、次のような文章が読める。「歌うことは、例えばジョン・フォードの作品では、結婚式や葬式のようなごく普通の集団的な儀式における重要さ以外に、しばしば、ひとりの個人にとって可能な、これ以上ないほど内密なかたちでの社会への加担の象徴である」(265頁)。そう指摘してから、ギャラガーは、『わが谷は緑なりき』(How Green Was My Valley, 1941)、『メアリー・オブ・スコットランド』(Mary of Scotland, 1936)、『静かなる男』(The Quiet Man, 1952)などにおけるしかるべき集団への帰属行為と歌うこととの関係を指摘しているのだが、さらに『幌馬車』をめぐって、彼はこうも語り始めている。