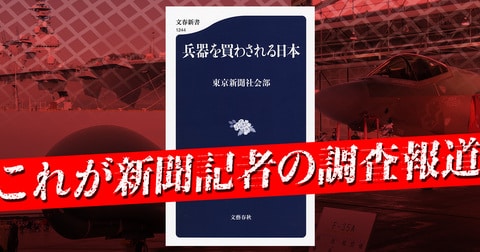雲は厚く、重かった。流れる、というよりも蠢くといったほうが適切に思えた。隙間なく広がる鉛色の空から雨が降る。雨脚は一定で、激しくなることも弱まることもなく、朝から今に至るまで降り続けていた。
安達はバインダーに視線を落とす。ラミネート加工されたA4用紙には、十八世帯三十二名の住所と住人の家族構成、年齢・性別といった簡易な個人情報が表形式で記載されている。今この地域に残っている人々は手のかかる者ばかりで、まだ三軒目であるにも拘わらず、すでに正午近くになってしまっていた。裏面には、縮小コピーされたゼンリンの住宅地図が印刷されており、残留住民の区画はピンクのマーカーで塗りつぶされている。
安達は、地図と現在地とを照らし合わせた。目の前には二階建てのアパートがある。世帯主は「カナムラ アキコ」なる三十四歳女性で、六歳の娘「ナナ」と同居している。
アパートの前には広い駐車場があったが、軽自動車が一台止まっているだけだ。カナムラ氏のものだろう。
アパートは国道44号に面している。国道、と言ってもその両脇にパチンコ屋があるわけでもモールがあるわけでもなく、閑散としている。ぽつりぽつりと戸建てや古いアパートがあって、砂利を敷いた空き地が広がる、とにかくそんな侘しい集落を抜ける国道だ。安達とその部下、立松は今その歩道を歩いている。雨粒が鉄帽にあたり、つばから滴り落ちる。雨衣を着ていたので戦闘服や下着が濡れることはないが、もう十日も風呂に入っていなかったからいっそのこと今身にまとっている全てをそこらへんに投げやって走り出したかった。背中が、頭が痒い。安達は手袋をしたままで、額から顎までを拭う。迷彩柄の手袋は雑巾のにおいがしたが、それでも思いのほかすっきりした。
カナムラ氏は「203号室」に住んでいた。アパートには、左右両方に階段がついていた。人気はない。これは別にこのアパートに限った話ではなく、この町全体がそうなのだ。この町で車が走るのを目にすることはほとんどないし、この町唯一の駅、別保駅に根室本線の列車が止まることは、しばらくの間はまず確実にない。目にするのは同業者ばかりだ。
「変なひとばっかりですね」
小隊の無線通信手たる立松士長が、ひとりごちるように言う。
「まあ、な」