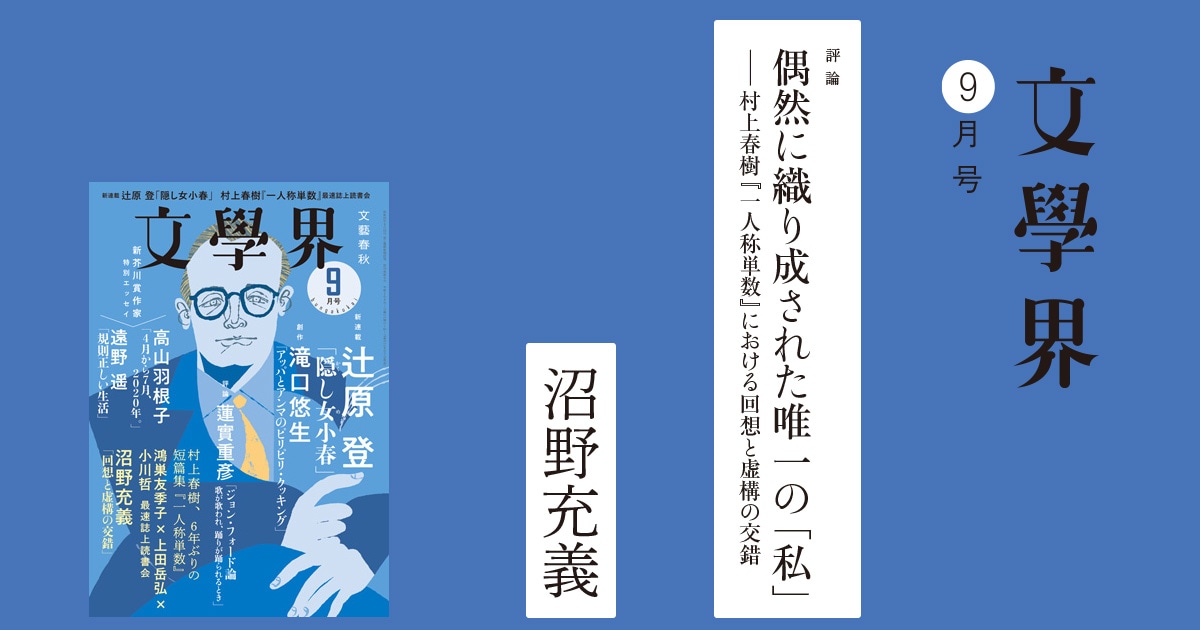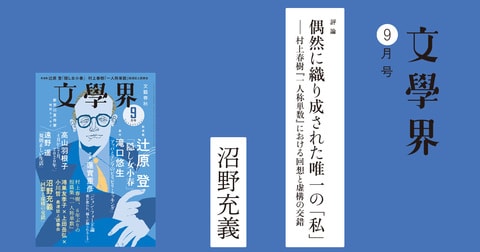一人称単数の語りと回想される人生行路

おそらくこれが、村上春樹の作家生活四十年を経てたどり着いた語りの境地なのではないかと思う。ここで最後に、一人称単数の語りの意味について考えてみよう。村上春樹における語りの人称については、長い変遷があるが、あえて簡単に振り返れば、ごくおおざっぱに言って、初期は「僕」という一人称単数を一貫して使い、やがて大きなスケールの長篇を書くためには「僕」の限界も見えてきて、『世界の終りとハードボイルド・ワンダーランド』では「私」と「僕」の章ごとの交替、『海辺のカフカ』ではカフカ少年の語る章は一人称を使いながらも、それ以外では三人称となっている。村上春樹自身は、あるインタビューで、デビュー以来使い慣れていた一人称から三人称に本格的に切り替えるのに二十年かかったと言っている。
それが今回の二作品では完全に、意図的に一人称単数に戻されている。あえて図式的にいえば、初期の一人称は物語というよりは現在の気分を表現するための抒情的な一人称、次の三人称は大きなキャンバスで物語を展開するための叙事的な三人称だったと言えるだろう。そしていま私たちが目撃している一人称は、当然のことながら、初期の一人称への単純な回帰ではない。それは一人称の語りを通じて、自伝的回想の枠を作りながら、そこに自由に虚構をはめこみ、回想と虚構を交錯させる手法になっている。
そういった一人称の回想する語りを通じて、「僕」の人生観もまた様々に変奏されながら、これらの作品では語られている。それを一言で要約することは難しいが、『猫を棄てる』の結末に現れるいくつかのアフォリズム的な言葉が――『一人称単数』の多くの短篇の人生観にも共通するものとして――受け止められるのではないだろうか。
「我々は結局のところ、偶然がたまたま生んだひとつの事実を、唯一無二の事実とみなして生きているだけのことなのではあるまいか。」
「父の運命がほんの僅かでも違う経路を辿っていたなら、僕という人間はそもそも存在していなかったはずだ。歴史というのはそういうものなのだ――無数の仮説の中からもたらされた、たったひとつの冷厳な現実。」
こういった人生観、いやむしろ運命観について考えるために、補助線として、ここでやや唐突だが、文化的キーワードの意味論的比較分析を行うことを通じて各国文化の特色を明らかにする研究で著名なアンナ・ヴェジビツカの論を援用してみたい。彼女には、英語・ドイツ語・ポーランド語・ロシア語・イタリア語・フランス語などにおける「運命」を表す単語の詳細な意味論的分析を通じて、それぞれの文化における「運命」のニュアンスの違いを明らかにした研究がある(Anna Wierzbicka, Semantics, Culture, and Cognition: Universal Human Concepts in Culture-Specific Configurations, Oxford University Press, 1992)。そこで論じられていることだが、ロシア語で運命を表す一般的な単語である「スジバー」(судьба)には「運命、宿命」(多くの場合はあらかじめ定められているもの)という基本的な意味のほかに、「めぐりあわせ」という偶然の織り成すもの、そして「前途、行く末」といった未来にかけてある程度可変的な意味もあり、またロシア語の場合に特徴的な意味として、「辿って来た道、沿革、歴史」の意味で使われることさえある。その場合、ロシア語の「スジバー」は英語のfateなどとは異なり、「運命」「宿命」というよりは、むしろ「人生行路」と訳したほうが理解しやすい場合もある。