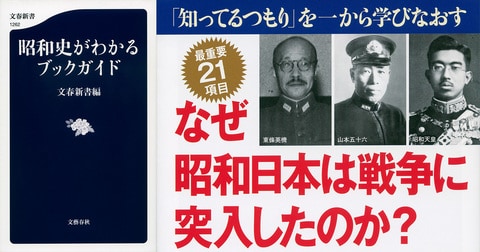終戦直後の闇市にマーケットができて盛り場となり、1964年の東京オリンピックの前後の市街地改造事業によって建てられたニュー新橋ビルと新橋駅前ビル。二つのビルは、今ふたたび「再開発」に直面し、取り壊されようとしている。本書は、昭和から平成、令和の時代をこの二つのビルとともに歩んできた人々の物語を掘り起こしている。
本書には、マーケットを遊び場にして育った靴屋の店主、『およげ! たいやきくん』で借金を完済した洋食屋の主人、中国系マッサージ嬢から経営者になった女性、図書館司書だった立ち呑み屋のママ、Gショックをはめた元官房長官、時代にあわせて商材を変えてきた金券ショップの商売人など、同ビルで生計をたてる人々が登場する。彼らの人生に織り込まれた記憶からは、社長や政治家、プロスポーツ選手、サラリーマン、「昼間から囲碁や麻雀を楽しむ浮世の達人」らが新橋で見せた顔も垣間みることができる。そして、高度成長期からバブル、平成不況をいかに生き、このビルを拠り所にしていたかを浮かび上がらせる彼らの人生譚は、二つのビルとともに一つの時代が終わりを告げようとしていることも雄弁に物語る。
カプセルホテルに暮らすケンちゃんは、1962年に上京し、渋谷で電車賃を借りた「兄貴」に弟子入りして以来、「流し」の演歌歌手をしている。70年代後半にカセット式再生装置が出回り、やがてカラオケが主流となっていくなかでも、ケンちゃんは歌手を続けてきた。彼は「最後まで頑張ったのはケンちゃんだけだよって温かい目で見てもらえるしね、頑張ってればいいことがある」と言う。けれどケンちゃんも歳だ。人気のない階段で座り込む彼に声をかけても、ほんの1か月前に話を聞いた著者をすぐには思い出せない。
北京出身のスナックのママは、バブルの終わりに店を構えた。震災時にも引き上げず、母親の死に目にも会えなかった。「お客さんが家族」という彼女の店には、オープンして以来、足しげく通う常連客たちがいて、かりそめの団欒を築いている。再開発について尋ねると彼女は、店をやめるきっかけになるので「早く壊してほしい」という。このままだと「自分の人生は全部この店」で終わってしまうと。
異業種が肩を寄せあう怪しげなビルは、個々の人生にそれぞれの居場所を提供してきた。過去と断絶するスクラップ&ビルドを繰り返す東京で、土地の記憶をとどめたビルの存在意義はより一層高まっていると著者は言う。猥雑で渾沌としたビルは、日常を非日常に変貌させる「パラダイス」だった。漂白されたテーマパークのような商業施設からはきっと排除されてしまう、大人の社交場、日常と非日常の間隙、寄る辺、社会の余白。これからの時代にもこの猥雑な空間が生きのびることを願う。
むらおかとしや/1978年、神奈川県生まれ。『BRUTUS』や『翼の王国』など雑誌媒体を中心にライターとして活動している。他の著書に『熊を彫る人』や、『酵母パン 宗像堂』などがある。
おがわさやか/1978年、愛知県生まれ。文化人類学者。『チョンキンマンションのボスは知っている』で大宅壮一ノンフィクション賞受賞。