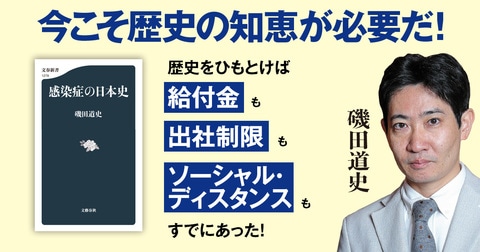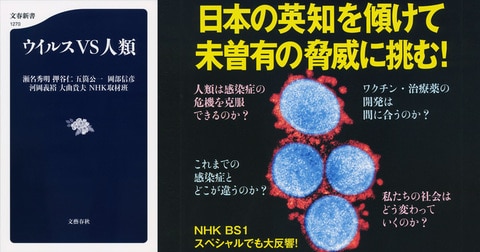「自分は、そう云う人を見付け出すごとに、自分一人マスクを付けて居ると云う、一種のてれくささから救われた。自分が、真の意味の衛生家であり、生命を極度に愛惜する点に於て一個の文明人であると云ったような、誇をさえ感じた」
WHOが中国から始まったこの感染症をなかなかパンデミックだと認めきれなかった時から、すでにこれは恐ろしいことになる、とぼくは警告をし続けていた。自分が長年書き続けている公開日記ではたびたびテドロス事務局長への批判を繰り返してきた。それはこのままでは多くの犠牲者が出ることになる、と心配していたからだ。ようやくWHOが「今世界はパンデミックの状態にある」と宣言した時、すでに世界はおよそ取返しのつかないところへと向かっていた。この菊池寛の一節は、世界を予見できない政治家や国際的組織のリーダーたちにこそ、聞かせたいくらいに、私には小気味よく響き渡った。
「マスク」の後半、それは5月の少し暖かい季節の話しになるが、主人公はマスクをつけなくなっていた。すると不意に目の前に「黒いマスク」を付けた男が出現する。この百年前の唐突な展開に、ぼくはこの「マスク」という作品の一番の読みどころを見つけることになる。当初、フランスでも、黒マスクは中国の観光客の方々が付けていた。白マスクが当たり前だった今年の初め、中国本土から渡ってきた観光客の団体が黒マスクをつけてシャンゼリゼ大通りを闊歩する光景が、ぼくの記憶に焼き付いた。何か、言葉に出来ない恐ろしい視覚的印象を持った。中国の人へ、ではない。その黒マスクに対して、である。ぼくは今、自分が黒マスクをつけるようになった。なぜ、あれほど不快を覚えた黒マスクに手を伸ばすのか、分からない。この作品の主人公は、感冒の脅威を想起させられたことで、この黒いマスクの男を憎悪する。この憎悪というものは一体何か、と2020年の現在、ぼくらはこの作品を読み込んだ上で、もう一度、考える必要がある。百年前のパンデミックの時代に、不意に登場した黒マスクの正体こそ、この作品に隠された黙示ではないか。
菊池寛はスペイン風邪で命を落とすことはなかったが、59歳の3月、近親者や主治医を招待し、病の快気祝いを自宅で行っていた最中、狭心症に襲われ、急死している。コロナ禍のパリで生きる61歳の自分にとっては他人事とは思えない話なのである。菊池寛がもしもこの時代に生きていたら、新型コロナで明日さえも見えないこの世界に対して、どういう行動を起こしていたのか、それを想像するのも、この作品のもう一つの醍醐味かもしれない。