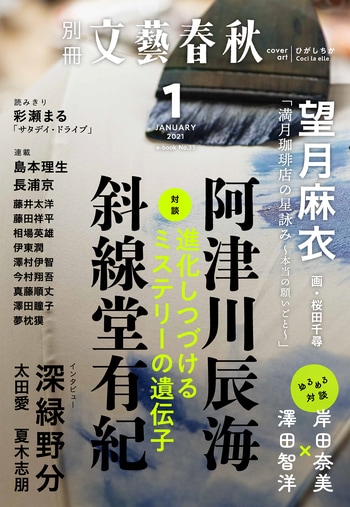1
「やっぱり、この国、おかしいですよ」と花奏は言った。
「そうか?」とおれは言った。
おれたちは琵琶湖のほとりにいた。
信子の遺灰を湖に撒いたあとのことだ。
わずかな残照におたがいの輪郭だけが見え、湖風がやたらと吹きつけて、寒かった。
「お坊さんにお経を読んでもらってないです。これだけのことをしたのに、お墓もないです」
不服そうだった。
「本人の遺志だ」とおれは言った。「〈いかなる種類の宗教的儀式も禁ずる。遺骸は火葬とし、灰は琵琶湖に撒く。撒く場所はどこでもかまわないが、綿貫情報官が決めること〉」
「どこでもかまわないって?」
「あんまりいろんな人間に来られないようにしたんだろうな。自分と関係のない場所が、自分のせいで荒らされるのが、いやだったんだろう」
「荒らされるって、だれに?」
「おまえの言う、これだけのことをしたあとでも、官邸に届く手紙の半分は、政府への怒りを表したものだ。至極当然だとおれは思う。これだけのことをやったんだ。手紙で済んでいて、ありがたいくらいだ」
「でも、信子さんのことを思って、彼女のために祈りたいひとは、どこで祈ればいいんですか」
「どこだっていいが、もしもそうしたいなら、琵琶湖のほとりに来て祈ればいい」
「こんな、寒々とした場所で?」
おれは琵琶湖を見た。
湖に光はなかった。周囲に人が住んでいないからだ。
この湖は、国を作るときに神がよろけて手をついたので、できた。
「ここは、わりとうまくおれたちの精神風景を表していると思うけどな。荒涼としていて、風が肌を刺すようで、見渡すかぎりなにもない」
「どうして?」
「どうしてって、何が?」
「どうしてそんなふうに感じなきゃいけないの?」
うーむ。
「おまえ、十六歳だよな」
「はい」
「戦争が起きたとき、何歳だったことになる」
「六つでした」
「それじゃあ、わかるはずないよ。それに、戦地から遠く離れた下関だろう。苦労はしたかもしれないが、暮らしそのものは、ほとんど戦前と変わらなかったんじゃないか」
「わかるはずないって、何がですか。わたしと兄さんがどんな目に遭ったか、知らないくせに」
おれは自分の額に手を当てて、撫でた。
「信子ちゃんの故郷は、沖縄なんだ。いまは存在しない、あの南の島だよ。家族で本州を旅行しているとき核が落ちて、本島が消し飛んだ。帰る家を失って一年間、放浪した。人々はなにひとつわたしたちに与えなかった、と彼女は言ったよ。それであの子はああいう人間になったんだ。年賀状を送り、中元を交換しあっていた親類にさえ拒まれた。農家の軒先で、土下座をした父親の頭が踏みつけられるのを見た。ある夜、母親がどこかへ消えて、髪を乱して帰ってきた、米がたったの二合入った袋を携えてな。これがどういう意味かわかるか?」