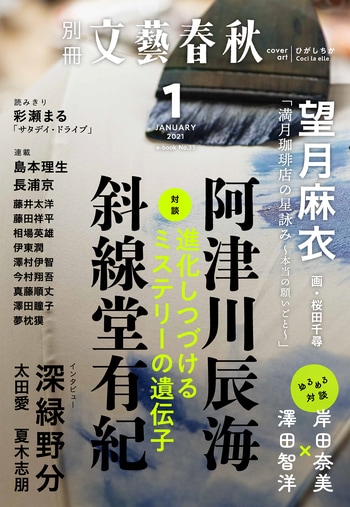しーんとして薄暗い、病院の一角だった。
だれもいない。
明かりもついていない。
「ここ、どこ?」
花奏が駆けてきた。
「先輩、さっきからなにやってるんですか! 助産師さんが呼んでます、来てください!」
「おっ!」おれは奮起した。「産まれたのか!」
「それがまだなんです!」
「ああ、いつまでやっとるんだ!」
「わたしに言われても困ります!」
おれたちは分娩室の前まで歩いた。
「もうちょっとなんです、ここでへこたれたらもっと切らなくちゃいけません、そばについて応援してあげてください!」と助産師が言った。
「わかりました!」と花奏が言った。
「ええっ。おれが入っていいの?」とおれは言った。
怒れる獅子がうろついているような緊張感が、分娩室につづく扉越しに伝わってきていた。
「さあ、しっかり手を洗って! 肘まで!」
覚悟を決めるしかないようだった。
赤ん坊の産声を天使のらっぱに喩えることがある。のんきな比喩もあったものだと思っていたが、考えを改めた。天使のらっぱは、すなわち黙示録のらっぱなのである。このらっぱが鳴り響くとき、東の空に明けの明星が輝き、神と悪魔の軍勢がものすごい戦争をはじめる。昼も夜もなく天から炎が降り、おれたちの街を破壊する。そしてらっぱが七度鳴ったのち、神に選ばれた者だけが生き残る。
新しい子の誕生だ。
というようなことを、子を抱えて微笑みながら気絶した百夏を眺めながら、考えた。
ちなみに花奏も気絶し、別室に運ばれ、点滴をぶちこまれていた。
覇気を送ろうとして有線接続し、逆にお産の覇気にあてられて、もらい気絶をしたのだ。
あほである。
目覚めたあと、百夏はあっけらかんと言った。
「名前、決まってないんだよね。あんた、決めてくんない?」
「えっ?」おれは動揺した。「えっ、おれが決めるの? なんで? 野口に託されたりとかしてないの?」
「おねがいしまーす」
「えーっ?」
しかし、断るに足る理由も見つからなかった。
この続きは、「別冊文藝春秋」1月号に掲載されています。