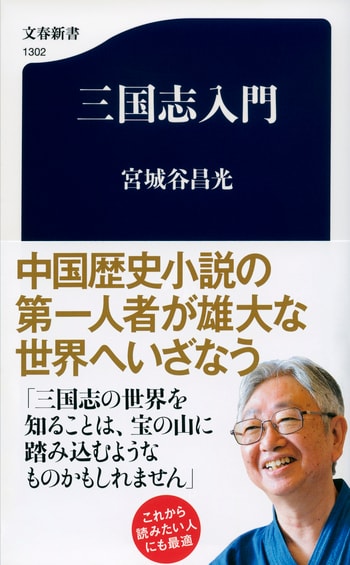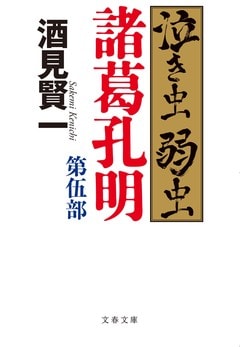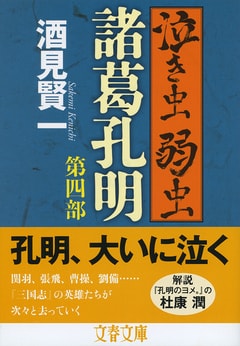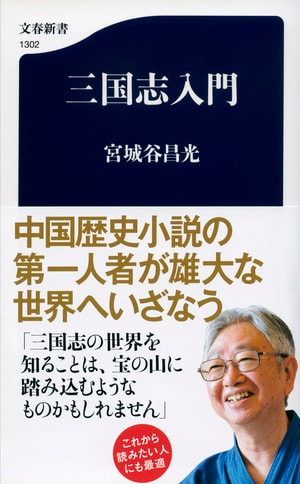
桃園の誓い
中国でもっとも多くの人々に読まれた小説は『三国志演義』でしょう。その小説のおもしろさは日本にも伝わり、いまでも多くの人々に読まれつづけています。
この小説の作者は羅貫中といい、出身は山西省の太原であろうといわれていますが、生年と歿年はわかっていません。王朝名でいえば、元の終わりから明の初めにかけて生きた人とおもってもらうしかありません。革命期を生きたということは、激動する世相をみたことになり、その体験が、過去の革命期を書くうえで大いに役立ったにちがいありません。
それでは、『三国志演義』の世界とはどのようなものなのか、ながめてゆくことにしましょう。
そのまえに、よけいなことかもしれませんが、『三国志演義』とは、小説ではなく物語ではないか、という人がいれば、それに答えておかなければなりません。小説と物語は、なにがちがうのか。そのちがいについて、もっともわかりやすく説いてくれたのが、イギリスの作家のE・M・フォースターです。
「物語はand(そして)で続いてゆくが、小説にはwhy(なぜ)という問いかけがある」
この定義に従えば、『三国志演義』は小説です。『三国志演義』の基になっているのは、陳寿の『三国志』(正史)や范曄の『後漢書』などで、そもそもそれらの歴史書には、
──なぜ国(王朝)は興り、なぜ亡んでゆくのか。
という問いがかくされているからです。
たとえ単調な物語でも、そういう構造の上にのせれば、小説の様相をみせることになります。羅貫中があつかったのは、後漢の霊帝の中平元年(一八四年)に勃発した黄巾の乱から、呉の国が滅亡する晋の武帝の太康元年(二八〇年)までです。百年ちかい長大な時間がその小説にふくまれているとなれば、内容が単調なはずがなく、時代を忠実にうつしてゆこうとすれば、複雑きわまりないものになってしまいます。小説をわけのわからないものにしないために、羅貫中はひとつのしっかりとした軸をつくりました。その軸とは、
「劉備」
という人物です。
幼いころに父を亡くして、貧しい家で母に育てられた劉備は、動乱の世を生きぬいて、ついに蜀の国の皇帝になります。つまり、
「なにももっていなかった劉備が、なぜ皇帝になることができたのか」
という問いを、小説の主題にうつしかえて、時代の複雑さを整理して、わかりやすくしたのです。
では、その小説の内容をざっとみてゆくことにしましょう。
劉備はあざな(通称)を玄徳といい、幽州の涿郡涿県に生まれ育ちました。涿県はいまの北京市の南に位置し、郡の政府が置かれていたのですから、大きな県でした。
あるとき、劉備は州の高札に目をとめます。高札にあったのは、黄巾の軍と戦うために義勇兵を募集する、という文字です。黄巾の軍とは、叛乱軍です。太平道という新興宗教を信ずる者たちが、中央政府の腐敗をいきどおって各地で挙兵したのです。かれらはいちように黄色い布を頭にまいたので、黄巾とよばれました。その軍はまたたくまに巨大となり、州郡の兵では鎮圧できなくなり、義勇兵を集めることにしたのです。
高札をみた劉備は、ため息をついて、立ち去ろうとしました。そのとき、
「すぐれた男が、国家のために働こうともせず、ため息をするしかないのか」
と、声をかけられます。声の主は、劉備より年下の若者でした。豹のような顔をした若者は、身長も体格も劉備よりまさっていて、声もきわめて大きい。この若者が張飛で、あざなを翼徳といいます。
劉備は自分の先祖が前漢の皇帝の子であることを告げたあと、
「黄巾の賊を討って、民を安らかにしたいのに、力がおよばない」
と、正直にうちあけたのです。この態度に好感をもった張飛は、酒屋に劉備をつれてゆき、酒をくみかわしました。ふたりが意気投合したころに、屈強な男が酒屋にはいってきました。身長は張飛よりも高く、赤黒い顔が特徴の男です。かれはこれから義勇兵の隊にはいる、といいました。
──尋常な男ではない。
と、みた劉備は、さっそくその男を自分の席に招いて名を問いました。すると男は、
「姓は関、名は羽という。あざなは雲長だ。出身は河東郡だが、悪辣な者が腹にすえかねることをしたので、そやつを斬って出奔した。五、六年、各地を渡り歩いてきたが、この地で義勇兵を募集しているときいたので、それに応ずるためにきた」
と、いいました。劉備は関羽の男ぶりに惚れこみ、自分の志をうちあけます。関羽も劉備のなみなみならぬ志に感動し、劉備とともに張飛の家へゆき、さらに語りあったすえに、兄弟のちぎりを結ぶことにしました。